活版印刷が教えてくれること
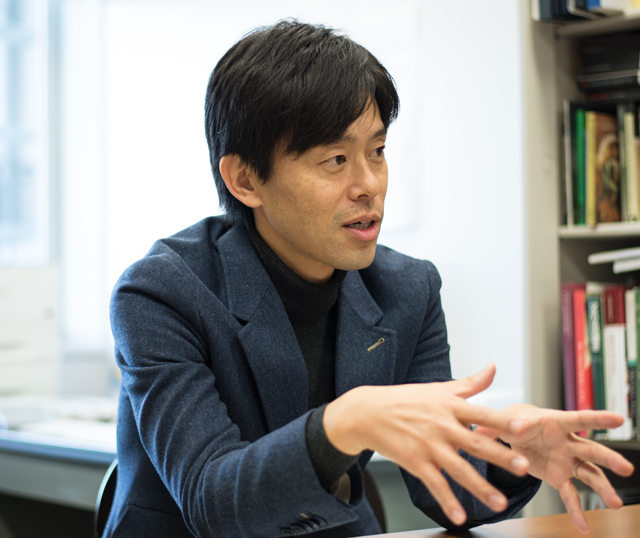 数年前のことですが、私はこの活版印刷というものの実態を知りたくなり、港の人という出版社を通じて、活版印刷による批評書を出版してみました。それは『ロケットの正午を待っている』というタイトルのハードカバー書籍として刊行されたのですが、本文はすべて金属活字を実際に組んだもので印刷しました。その活版印刷所は雑司が谷にあるのですが、そこで目の当たりにした活版印刷の現場は、想像を超えてたいへんなものでした。植字工と呼ばれる職人さんが、鉛を鋳造した活字を棚からひとつひとつ拾い上げて、そしてページごとに文字列に組んでいくのですが、まずそうした姿を拝見できたことは、デジタル入稿の現場しか知らなかった私にとって衝撃でした。
数年前のことですが、私はこの活版印刷というものの実態を知りたくなり、港の人という出版社を通じて、活版印刷による批評書を出版してみました。それは『ロケットの正午を待っている』というタイトルのハードカバー書籍として刊行されたのですが、本文はすべて金属活字を実際に組んだもので印刷しました。その活版印刷所は雑司が谷にあるのですが、そこで目の当たりにした活版印刷の現場は、想像を超えてたいへんなものでした。植字工と呼ばれる職人さんが、鉛を鋳造した活字を棚からひとつひとつ拾い上げて、そしてページごとに文字列に組んでいくのですが、まずそうした姿を拝見できたことは、デジタル入稿の現場しか知らなかった私にとって衝撃でした。
次に驚いたのが、そうやって仮印刷されたものの校正作業です。ワープロではなく、職人さん一人一人の手と目によって並べられた文字列は、もちろんありがたみに溢れてはいるのですが、同時に、コンピューターの誤植とは異なったエラーも散見されて、それが校正する私の脳の、いつもとはまったく違ったところを刺激してくれたのです。たとえば、同じ明朝体なのに、よくよく見てみると「言」(ごんべん)のかたちがわずかに違うフォントが混じっているとか、あるいは、文字の上下が逆さまになっているとか。確かに、編集用の校正記号には、そうした上下反転を正すものもあって、校正作業そのものが、職人さんとの身体的な対話をしているようでした。こうした作業を通じて、私は、自分の文章をいつもとは違った視点から眺めることができ、それはやはり、自身の執筆活動の拡充につながりました。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




