多角的な「はじめに光ありき」がブレイクスルーを生む
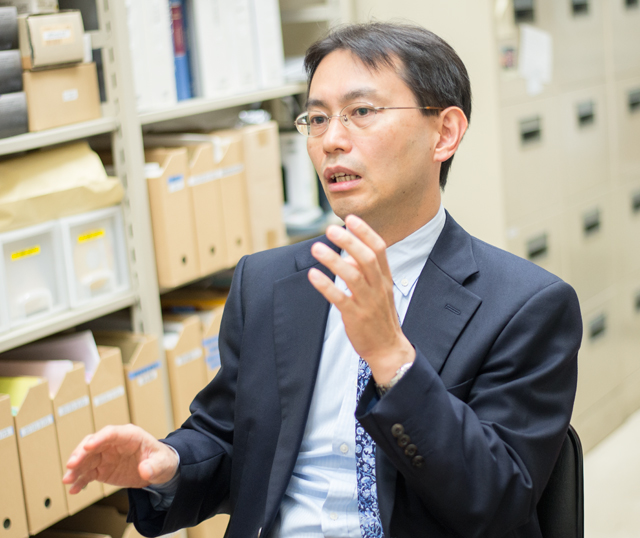 SIPは横断的に取組むプロジェクトと言いましたが、民間企業の組織的なサポートを受けて、40以上の大学や研究所が参画しています。従来の自動車開発における産学連携は、個別のメーカーと個別の大学が共同研究をするスタイルでした。しかし今回のプロジェクトでは、私たちのグループだけでも4つの大学が参加しています。それぞれの大学に得意分野があり、その観点から知恵を出し合い、毎日のように意見交換をし、データの共有を行っています。違う角度から多角的に攻めるというのは、ものすごく有意義であり、重要なことです。長い間エンジンの開発にたずさわってきた専門家の感覚では、「それは常識ではあり得ないこと」でも、それに囚われず、新しいアイデアや発想を活かすことができるからです。
SIPは横断的に取組むプロジェクトと言いましたが、民間企業の組織的なサポートを受けて、40以上の大学や研究所が参画しています。従来の自動車開発における産学連携は、個別のメーカーと個別の大学が共同研究をするスタイルでした。しかし今回のプロジェクトでは、私たちのグループだけでも4つの大学が参加しています。それぞれの大学に得意分野があり、その観点から知恵を出し合い、毎日のように意見交換をし、データの共有を行っています。違う角度から多角的に攻めるというのは、ものすごく有意義であり、重要なことです。長い間エンジンの開発にたずさわってきた専門家の感覚では、「それは常識ではあり得ないこと」でも、それに囚われず、新しいアイデアや発想を活かすことができるからです。
実は、私自身もエンジン開発の専門家ではありませんでした。学生時代にエンジンを研究する研究室に所属していましたが、そこで私が専門に取組んだのはレーザーを使った光計測です。燃焼のレーザー計測、ディーゼル火炎内におけるすす粒子の生成・酸化過程について研究してきました。今回のプロジェクトにあたっては、研究計画の準備段階で自動車メーカーの技術者の方々から研究ニーズを詳しく聞き、それに対して私の得意分野である光計測をフルに活用して、何ができるのかをまず必死に考えました。その結果、どの自動車メーカーでも光計測は必ず活用していますが、光計測の新しいタイプの応用を提案をすることができたのです。その手法による計測結果によって、「それは常識ではあり得ないこと」をむしろ活用することが良い結果につながることをつかみました。実験を重ね、目標の「後燃え低減」を実現できそうな結果も出始めています。新しい計測手法によって初めてわかったことをエンジンの開発に活かすというアプローチは、今回のプロジェクトのような高いハードルを突破するときには絶対に必要であることを実感しました。私に限らず、他の分野の専門家がエンジンの開発に加わり、新しい風を吹き込むことで、ポンッとブレイクスルーが起こる。その意味で、研究開発における“多様性”は重要なキーワードになると思います。
旧約聖書の創世記冒頭に「はじめに光ありき」という言葉があります。本来の意味とは異なりますが、光計測を専門に研究してきた私にとって、これは象徴的な言葉です。何か問題に取組もうとしたときに、光を差してきちんと見る。前例や常識に囚われるのではなく、いま何が起きているのか自分の目できちんと見て理解する。それによって、問題の対策を考えるポイントをつかむことができるのです。このプロセスは、すべての研究分野において同様だと思います。様々な分野で、多角的に「はじめに光ありき」から取組むことで、大きな変革(イノベーション)も、現状の打破(ブレイクスルー)も起こし得るものだと思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




