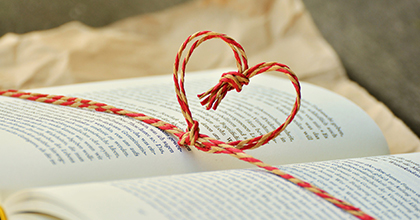マンガを体系的に保存することの学術的意義
そのような発展の結果として、日本のマンガは、日本の人々の価値観や生活の変化を、性別や年代ごとに、細やかに、かつ幅広く映し出す、類い希な記録としての側面を持つようになりました。たとえば、1960年代の少女は何に憧れていたのか。同年代の少年とは、あるいは10年後の70年代の少女とは、それぞれ見えている世界がどのように違っていたのか。その彼女らが80年代になって家庭を持つようになったとき、どのようなライフスタイルを指向するようになったのか。
こうした観点からマンガを参照することによって可能になるのは、マンガ自体の史的研究にとどまりません。マンガの体系的な閲覧を可能にすれば、とりわけ戦後から現代にいたる日本の人々の変化に関する、肥沃な研究材料の採掘源になるわけです。本学が、大学としてマンガの専門図書館を設けた意義の一つが、そこにあります。
この意義をひときわ大きくしているのは、マンガが従来、低俗なサブカルチャーともみなされてきたことから、日常的に幅広く読まれてきたものであるにも関わらず、体系性と一定の網羅性をもって収蔵している機関が極めて少なく、かつ学術研究の対象としても比較的新しいことです。研究者にとって、処女地がまだまだ残っている状態といえるでしょう。
マンガの雑誌や単行本は国会図書館でも収蔵していますが、出版社が納本し損ねて欠本が目立つ雑誌が意外に多くあります。加えて単行本については、これはマンガに限らずですが、ごく一部の資料を除き、本の顔ともいえるカバーを省いて収蔵しているのです。このため、刊行時に書店でどのようなカバーイラストを目にして人々が手に取ったのかがわからず、原装の書影も撮れないという大きな問題があります。
本学のマンガ図書館では、資料が提供された時に付いていたカバーやオビ、付録類を含めて保存しているだけでなく、バーコードラベルを貼ったり蔵書印を押したりせずに管理しており、一点一点が展示資料としても運用可能な状態に保たれています。
また、国会図書館に納本されるのは書店流通する本や雑誌が中心で、1950年代から60年代初頭にかけて親しまれていた貸本屋専用のマンガ本や、1970年代後半以降マンガ・アニメ・ゲーム等文化の大きな基盤となっていったマンガ同人誌の収蔵は手薄です。そして貸本マンガと同人誌こそ、本学のマンガ図書館が充実している領域です。その意味においても、国会図書館と相補性の高い、貴重な蔵書を抱えているといえるでしょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。