変化する日本と東南アジア関係 ―多民族社会から学ぶ日本社会へ
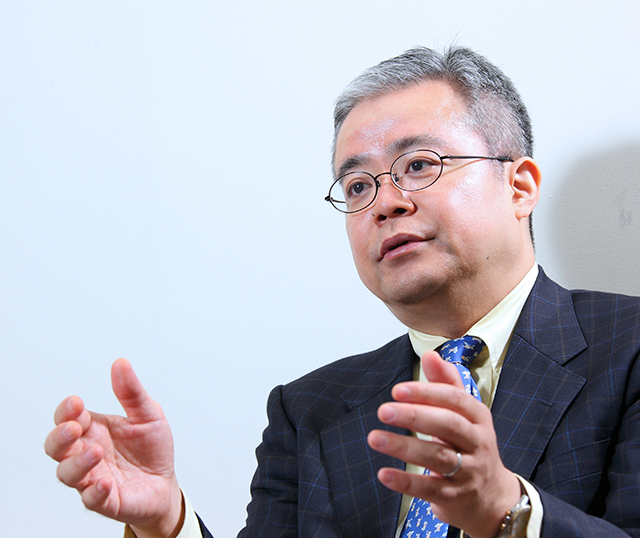 もう1つの代表的な棲み分けの例が、高等教育である。マレーシアでは国立大学はこれまでマレーシア語、私立大学は英語で講義が行われてきた。英語による授業運営が基本となれば、教育対象は世界に広がる。多民族の社会基盤を持つ東南アジアの国々では、高等教育をサービス産業として捉え、世界から学生を集め、人材を育成しようとしている。日本の製造業が東南アジアで圧倒的なレベルにあった時代には、苦労してでも来日して、知識や技術を習得してきたが、もはや、後発の東南アジア諸国を除けば、日本への関心は薄い。むしろ、高等教育ではJapan Passingともいえる状況にある。
もう1つの代表的な棲み分けの例が、高等教育である。マレーシアでは国立大学はこれまでマレーシア語、私立大学は英語で講義が行われてきた。英語による授業運営が基本となれば、教育対象は世界に広がる。多民族の社会基盤を持つ東南アジアの国々では、高等教育をサービス産業として捉え、世界から学生を集め、人材を育成しようとしている。日本の製造業が東南アジアで圧倒的なレベルにあった時代には、苦労してでも来日して、知識や技術を習得してきたが、もはや、後発の東南アジア諸国を除けば、日本への関心は薄い。むしろ、高等教育ではJapan Passingともいえる状況にある。
他方、日本企業の東南アジア関与も変化してきた。かつての製造業の生産拠点と位置づけられた、島嶼部東南アジアでは日本のサービス業の海外展開も本格化してきた。コンビニエンスストアや小売・流通業が主流だが、次は教育産業であり、ケアビジネス産業などである。日本企業がグローバル化を標榜するならば、多民族社会への理解は必須となっている。
翻って、日本の学生も、国内のアルバイト先などで南アジアや東南アジアからの留学生に接する機会が増えているため、多民族社会という現実には違和感がなくなっている。どの民族へもフラットな視点で、肌感覚で多民族に接している。そういう意味では、日本社会も確実に多民族化してきているといえる。
多民族社会化への道は、すなわち、国際標準化の現れともいえる。現状認識をもう一歩進めて、多民族化によってどのような問題が起こるのかということを想定したルールづくりや社会システムの構築を「参加を保証しながら」促進することが早期に求められる。その時、マレーシアなどの島嶼部東南アジアは、非常に重要な視座を含んでいる。
(注)15世紀を中心に、明王朝が敷いた朝貢・冊封体制という国際環境もとで、マラッカ海峡に面したマレー半島西海岸という地の利も得、東アジアとイスラーム世界とを結ぶ東西貿易の拠点として栄えた港市(こうし)国家。1511年にポルトガルの手によって、マラッカの地を追われ、マレー半島南部にその後継国家ジョホールラマを開いた。
※掲載内容は2013年7月時点の情報です。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




