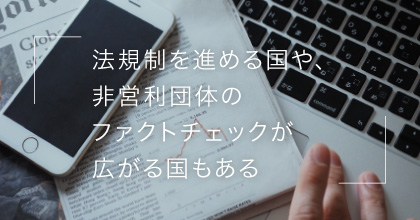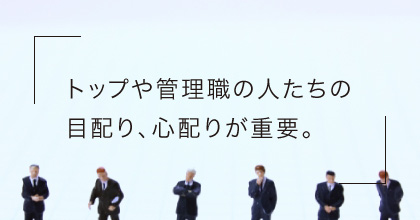
トップや管理職の人たちの目配り、心配りが重要。
この連載の第1回で、人は何のために働くのかというと、収入を得るためだけではなく、自分の夢や目標をかなえたり能力を発揮することであったり、だれかとつながったり役に立つことであったり、自分の存在を認めてもらうことと言いました。実は、こうした働く動機が、「活力」、「熱意」、「没頭」を高めること、すなわちワーク・エンゲージメントを高めることにつながるのです。しかし、仕事がいつも自分の思い通りとは限りません。むしろ、その逆のことが多いかもしれません。そこで、会社としては、働く人をきめ細かく見てサポートすることが重要になってくるのです。
まず、その人がなにをやりたいのか希望を聞き、それに添った仕事を与えましょう。そして、その人の能力やキャリアに応じて、負うのに適当な裁量権や、仕事をコントロールすることを認めてあげるのです。つまり、仕事へのやり甲斐や満足感を高めるのです。しかし、その人の希望ではない仕事を与えざるを得ないこともあるでしょう。そのときは、その仕事の意味を上司がちゃんと説明することです。将来、希望の仕事に就くために必要な経験や知識が得られるとか、この仕事は会社にとってとても重要だから、あなたにやって欲しい、ということです。そして、進行状況に目を配リ、必要に応じてサポートをし、仕事の成果はきちんと評価することです。日本の企業は、長時間労働する人を、よくやっている人と評価しがちですが、それが無意味な長時間労働を助長する一因になっています。むしろ、成果をきちんと見て、それを褒めることや、その人の成功体験とすることが、ワーク・エンゲージメントを高めることにつながります。
逆にいえば、従業員の希望に関係なく会社の都合だけで仕事を与え、フォローもサポートも充分せず、裁量権も認めず、できて当たり前という見方で、成果を正しく評価しない。こんな会社では、従業員のワーク・エンゲージメントが高まるはずはありません。メンタルヘルスを悪化させ、最悪の結果を招いたり、労働生産性は上がらず、業績も伸びないということにつながります。我が社はそんな会社ではないと思っているトップの方や、そんな労働環境ではないと思っている管理職の方は多いと思います。では、なぜ日本では、労働者のメンタルヘルスの悪化が年々増えているのか、諸外国に比べてワーク・エンゲージメントが圧倒的に低いのか。その理由を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。
次回は、ワーク・エンゲージメントを高めるために一人ひとりができることを紹介します。
#1 長時間労働を是正すればすべてが上手くいく?
#2 ワーク・エンゲージメントって何?
#3 ワーク・エンゲージメントが高いのはどんな人?
#4 会社の工夫でワーク・エンゲージメントは高くなる?
#5 仕事時間が短くなったら何をする?
#6 長時間労働是正がダイバーシティの推進を生む?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。