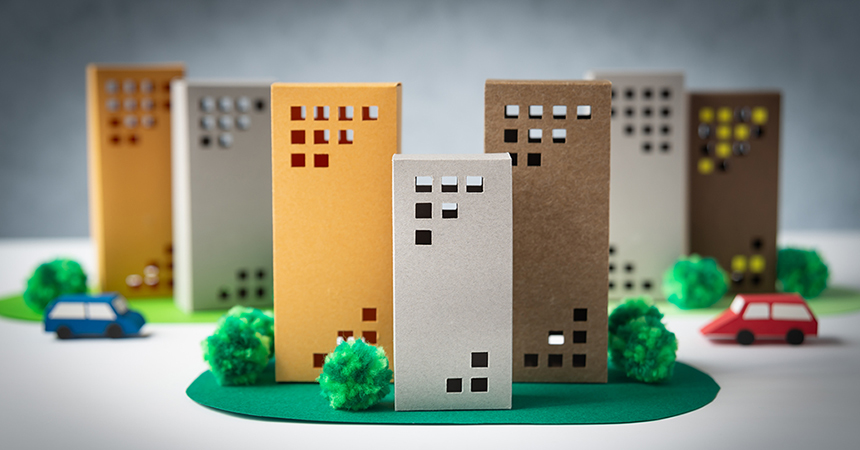
古びたマンションの外壁にヒビ割れを見つけたとき、「これ、大丈夫かな?」と不安になったことはありませんか? 日本ではいま、老朽化した鉄筋コンクリート造の建物が増えています。そこで注目されるのが、建物を守る“衣服”とも言える「仕上材(しあげざい)」。本記事では、建物の寿命と仕上材の関係、そして持続可能な建築の未来について考えます。
ゴーストタウン問題の背景にあるコンクリートの劣化
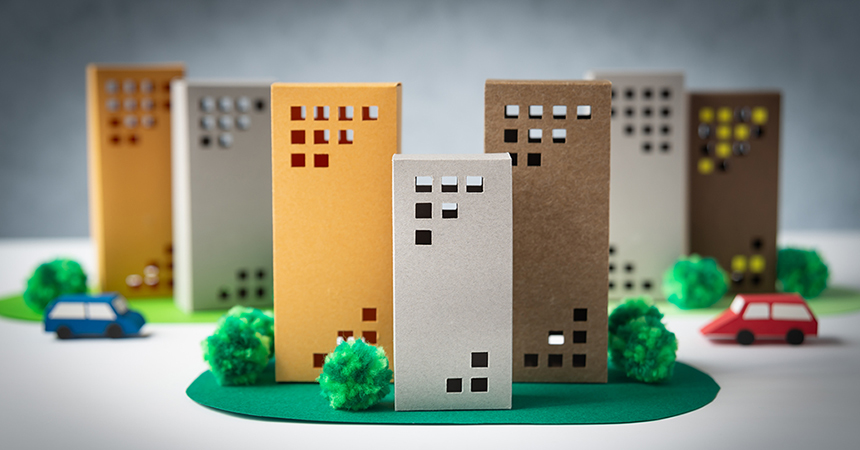 近年、かつて活気のあったニュータウンや集合住宅がゴーストタウンと化し、社会問題として注目されています。その背景には、少子高齢化や工場閉鎖などの産業構造の変化がありますが、建物自体の老朽化、とくに鉄筋コンクリート造建物の経年劣化も見逃せない要因です。
近年、かつて活気のあったニュータウンや集合住宅がゴーストタウンと化し、社会問題として注目されています。その背景には、少子高齢化や工場閉鎖などの産業構造の変化がありますが、建物自体の老朽化、とくに鉄筋コンクリート造建物の経年劣化も見逃せない要因です。
高度経済成長期に建てられた多くの住宅は、いまや築50年を超え、老朽化しています。こうした建物では耐震性の懸念だけでなく、外壁のタイルが剥がれたり、廊下や階段が崩れたりといった目に見えるトラブルが増えています。人々にとって安全で親しみやすい建物であったはずの住宅が、次第に社会的・物理的に受け入れがたい存在になっているのです。
そもそもコンクリートとは、砂、砂利、水、セメントを練り混ぜて固めたもので、私たちの日常生活において非常に身近な存在です。道路や下水道、電柱や住宅など、あらゆる場所に使われています。安価で耐久性があり、「メンテナンスフリーの建設材料」と信じられていた時代もありました。その硬さゆえに、「コンクリートは壊れない」というイメージが浸透していたのです。
しかし現実には、コンクリートは圧縮する力には強くても、引っ張る力には弱いという性質があります。そのため、鉄筋を中に埋め込むことで補強した「鉄筋コンクリート」が広く使われてきました。ですが、どれほど高品質な鉄筋コンクリートであっても、さまざまな外的要因により、時間とともに劣化は進行するのです。
劣化が進んだコンクリートは、壁面や天井等の崩落・剥離・落下の危険性を伴います。条件次第では100年以上もつとされるコンクリートも、適切に管理しなければ、その寿命ははるかに短くなってしまいます。また、比較的近年に建てられた建物が、コンクリートの真の寿命を迎える前に解体されるケースも少なくありません。
とはいえ、老朽化したらすぐに壊して新築するという発想は、現代の社会では見直されつつあります。日本は欧州に比べて、スクラップ・アンド・ビルドの発想が強いとされてきましたが、そのような時代は終わりを迎えつつあるのです。現在では、廃材や建築資材の環境負荷を考慮した「再利用」「長寿命化」が求められるようになりました。
その一方で、本来は耐久性の問題から取り壊すべき建物であっても、予算や法制度、住民の合意といった複雑な事情から、使用を継続せざるを得ないケースも増えています。そうした状況をふまえ、建物をどのように健全な状態で長く使っていけるのか、そのための新しい視点が必要とされています。
そこで注目されているのが「仕上材」の存在です。これは建物の表面に用いられる材料で、外部からの影響を防ぎ、建物を保護する役割を担っています。たとえるなら、構造体が人間の体(骨や筋肉)ならば、仕上材はその人が着ている衣類のようなもの。外の環境から身を守る「洋服」が、建物にも必要なのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




