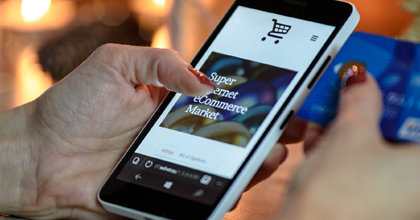近年、日本の大学の研究力が落ちている、という指摘があります。それは、日本の大学から出される論文が減少していることなどに表れていると言います。そこで、様々な施策が打ち出されていますが、状況が好転する様子はありません。それは、なぜなのでしょう。
研究力が落ちていると言われる日本の大学
 日本の大学から出される論文数は、2000年代に入ってから低下し続けています。また、論文の質の高さを示すといわれる、引用される回数の多い論文の数も同じく低下し続けています。研究現場にいる私たちにとっても、日本の大学の研究力が落ちているということは実感としてあります。
日本の大学から出される論文数は、2000年代に入ってから低下し続けています。また、論文の質の高さを示すといわれる、引用される回数の多い論文の数も同じく低下し続けています。研究現場にいる私たちにとっても、日本の大学の研究力が落ちているということは実感としてあります。
原因はなにかと言えば、ひとつには、科学技術研究費が充分ではないことです。実際、論文数が急激に伸びている中国などは、この20年間で科学技術予算が8倍になっていると言われます。
確かに、経済成長が鈍化している日本では、科学技術予算を伸ばす余裕がないことはわかります。しかし、その経済を活性化させるイノベーション創出の基になるのは科学技術であることも、また、事実です。
例えば、新型コロナウイルスに対するワクチンには、これまで実用化は難しいのではないかと言われていたmRNA技術が応用されています。
アメリカの製薬会社はこの技術の研究を以前から進めていました。そのため、このパンデミックに際して、スピーディーなワクチン開発に成功し、世界各国が多大な予算を組んで調達に動く状況になっています。
一方、日本の科学技術力を活かしたイノベーションはなかなか起きていないのが実情です。
つまり、経済力の低下によって科学技術研究予算も低下することは、イノベーション創出の低下に繋がり、それがまた経済力の低下を招くという悪循環に陥ることになるわけです。そこで、政府も様々な施策を打ち出しています。
例えば、10兆円規模の大学ファンドを設立するプロジェクトがあります。これは、当初は期待が大きかったのですが、いまは、各大学とも困惑の状況です。
実は、このファンドから資金を受けるには様々な条件があるのです。例えば、大学に、外部有識者を入れた理事会を設置することや、毎年3%の事業成長率を達成することが求められたりします。
そうした条件をつける意図はなんなのか、私は推察することしかできませんが、大学の自立性が失われていくことは言えます。大学から、自由な研究や、自由な討論が失われていくとしたら、それは、大学の価値や意義を失わせることに繋がります。
すなわち、日本の科学技術の低下による危機感から始まった大学に対する施策は、実は、必ずしも当を得ているとは言えないのです。
なぜ、そのようなことになったのか。それは、科学とは実際にどのように進むものなのか、ということに対する理解が浅いからではないかと考えられます。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。