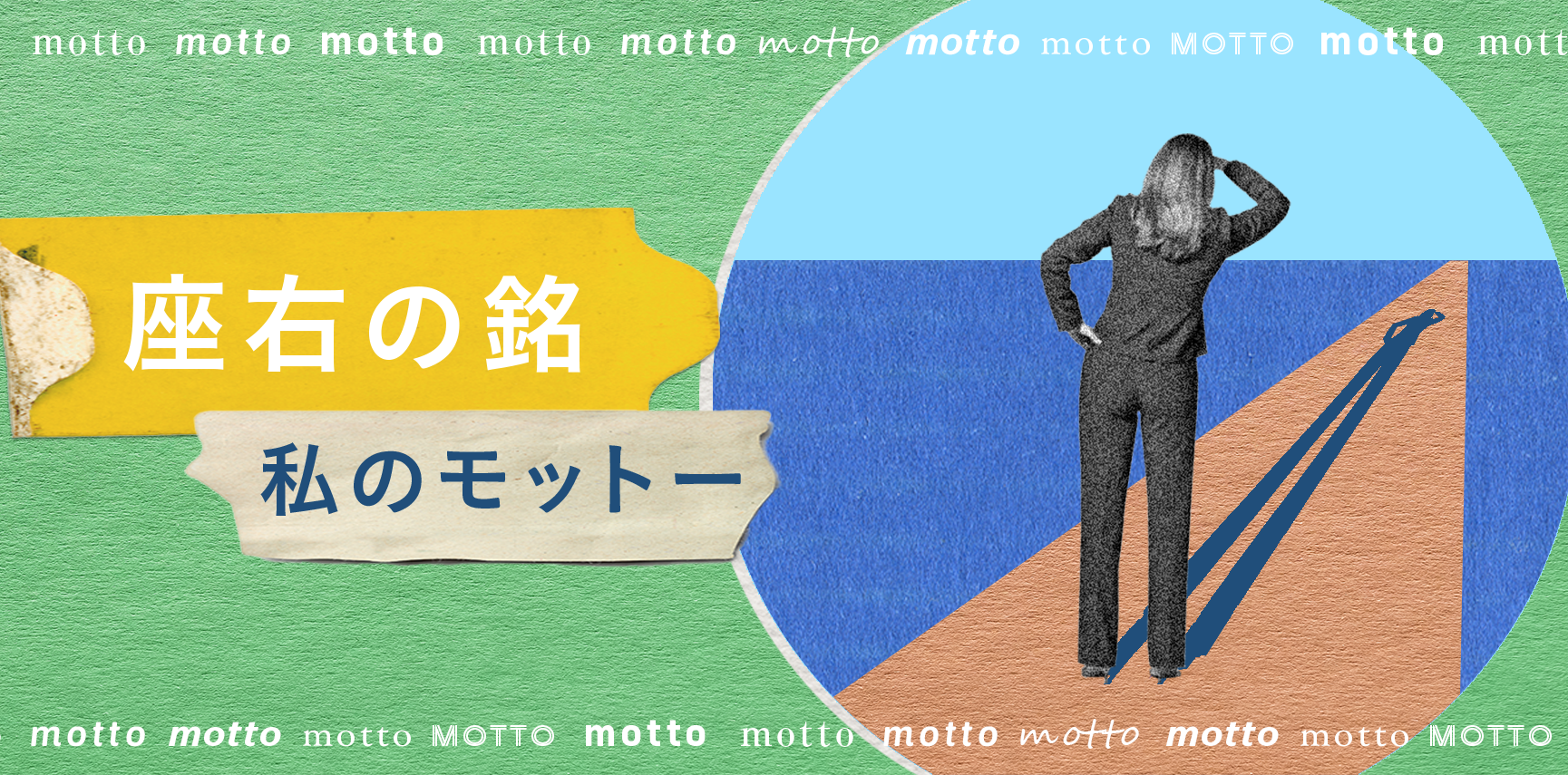
座右の銘、私のモットー遠回りのように感じることが実は近道となる「迂回原理」
教授陣によるリレーコラム/座右の銘、私のモットー【3】
私が大切にしているのは、19世紀の歴史経済学者ロッシャーが展開した「迂回原理」です。与えられた目的を達成するために、その目的に直接働きかけるような戦略設定は望ましくなく、間接的な方法や迂回的な手段が有効であることを示す考え方です。
たとえば魚を捕りたいなら、すぐさま海に飛び込まず、山から木を伐りだして船を造り、さらには大きな網をつくって捕ったほうがいい、といった考えです。いきなり潜って魚を捕ろうとすると溺れて死んでしまうかもしれません。一見、海にいる魚を捕るために山に行くのは無駄なことのように見えますが、より効率的で本質的な、先を見据えた解決法を提案しているように思います。
若い頃は論文を書けば偉いと思っていましたが、三十代も半ばになると、「何のために役立つのか」を考えるようになりました。経済学者は、医師のように人を直接助けることもできないし、便利な道具をつくれるわけでもありません。何か困ったとき、経済学に何ができるのか。そう考えていたときに、指導教授から教わったのが「迂回原理」であり、この考えに励まされました。
経済学は、世の中全体のメカニズムを考えることに優れています。たとえば何らかの金融政策について、それがどういう結果になるかを考え、今やるべきことは何かを提示するのが、経済学者にできることです。貧困の問題も、泳ぎが得意な人に任せるのではなく、網をつくって船で出かけたほうが社会のためになる。そういう考えをもてたことで、全体像を理解することに注力できるようになりました。「社会科学は迂回原理が本質だ」と捉えることで、自分のなかでモヤモヤしていた部分が晴れたように感じています。
問題の本質的な理解や解決をするために、今も迂回的なものの見方を心がけるようにしています。論文などを書く際、研究の良さや売り方をアピールするときにも、指針としているのが迂回原理です。物事を捉えるにあたり、迂回原理のような視点をもつことは、迷いを打ち消すのにも役立つのではないでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




