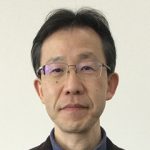座右の銘、私のモットーフィリピンで敗戦を迎えた父から聞いた言葉、「最後のイモはタバコに換える」
教授陣によるリレーコラム/座右の銘、私のモットー【2】
父がよく口にしていた「最後のイモはタバコに換える」という言葉が、幼い頃から私の心にずっと残っています。
私の父は第二次世界大戦の兵士としてフィリピンに行き、1945年の敗戦をそこで迎えました。そのときフィリピンに行った約400人のなかで、日本に帰ってきたのは父を含めわずか4人。大岡昇平が『俘虜記』に記しているような、また、横井庄一さんや小野田寛郎さんについて報道されたような、大変な苦労をしたようです。
最後はゲリラ戦になって、フィリピンの住民とも戦うことになり、民間人と兵士との区別はつかなくなったと思われます。国際法では民間人は撃ってはならないとされています。その理念は非常に重要ですが、しかし、こちらが撃たなければ自分が殺される戦場で、それがどれだけ有効性をもったか。戦いの経験について父は死ぬまで何も語りませんでした。子どもには言えない、口にすることのできないつらい出来事があったのでしょう。
しかしお酒を飲むと、断片的に同じ話をよくしていました。深刻なものではなく、豚の鼻を食べたとか、アメリカ兵は食パンの耳を捨てていたとか、面白おかしく語っていました。その一つとして聞いたのが、この言葉です。
日本兵は食糧としてイモを携帯してあちこち逃げ回っていたようですが、もうダメだと覚悟したときには、戦友にイモをタバコと換えてもらい、ゆっくり一服して死んでいくんだと言っていました。死を悟ったとき、人はイモを食べてわずかでも長生きしようとするのではなく、タバコを楽しみ、終わりを迎えるということです。人間とはそういうものかと、子どもごごろに思った記憶があります。
子どもの頃はなんとなく聞いていましたが、今、生きるとは、死ぬとは、幸福とはなど、根源的なテーマについて考えるとき、この言葉がふと頭をよぎります。たとえば貧困の問題を解決するのに食糧を送ることは重要ですが、それだけでは人間は幸福になれません。安楽死の問題とは、もっと直接に関係しそうです。
もう死ぬかもしれないという経験を何度もした父の、重い言葉ですが、それを語る父の表情は、いつもおだやかでした。その表情とともに、今もよくこの言葉を思い出します。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。