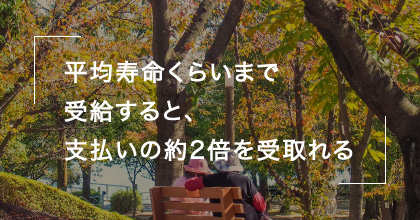人生のターニングポイント人にものを教えるのは「一番ない選択肢」だった
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【68】
大学に残ったのは自分でも予想外でした。私がいた工学部は6、7割が大学院に進む環境だったので、私も修士ぐらいは行っておくか、という程度の気持ちで進学しました。ところが研究室に入ってみたら、同期や先輩・後輩と一緒に取り組んだ経済学、統計学・データ解析の基礎についての自主学習がとても楽しかった。
さらに「大規模インフラ整備の経済効果計測手法の開発」という共同研究にも夢中になりました。兄弟子のような先輩と3人で、東北新幹線整備によって周辺の資産価値がどれぐらい上がるかという変化を調べるものでした。リアルなデータを解析し、ロジックを実証するのが非常に面白くて、結局は博士課程まで進むことに。このときの経験がなかったら、私は修士課程で終えて就職していたと思います。人にものを教えるのは「一番ない選択肢」だと思っていましたが、それでも教員・研究者の道を選んだのは、恩師や先輩の存在、それにデータを自分なりに分析し、アウトプットすることの楽しさに魅了されたからだと思います。このときの出会いや出来事が、私にとってターニングポイントの一つだったといえるでしょう。
もう一つ、90年代初頭に経験したバブル経済の崩壊の影響も大きかったですね。学部時代から修士、博士へ進む過程と、バブルの生成、膨張、崩壊の時期がちょうど重なり、バブル現象のデータをリアルタイムで把握し解析することになりました。非常に魅力的かつ大変な経験でしたが、データから社会の実相を正確に把握することの重要性を学びました。しかし一方で、モデルを作って予測を立てても、そのとおりにはいかないということも実感しました。重要なのは予測に固執することではなく、予測とのズレに備えた幅を持っておくことです。
現在、当時の経済状況がバブルだったか否かという論争にはほとんど結論が出ています。しかし当時の地点に立って将来を見れば、ほかにも複数の可能性のあるパスが存在していたと思います。経済予測とはそういうもので、人の行動や統計データに加え、現在と過去と未来の時間軸も併せて考えなければなりません。
データをもとにした経済予測は、暗い道を歩くときに先を照らす灯りのようなものだと思います。暗闇を突き進むのは危険ですが、ぼんやりとした幅を含みつつも未来の方向を示し照らしてくれる、社会にはそんな予測情報があります。見極めながらも、ぜひよりよい意思決定の参考にしてください。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。