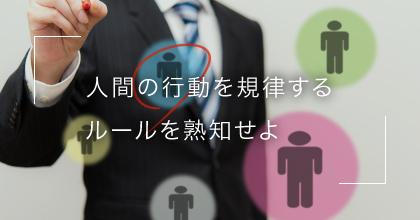人生のターニングポイント高校以来の親友「笑い飯」哲夫との会話
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【66】
私が「組織論」あるいは「組織の理論社会学」という分野の研究に至ったきっかけは、思い起こせば少年時代まで遡ります。
私の父親は、とある県の教育委員会におり、文部省(現文科省)が進める教育を県に広める活動に携わっていました。結果、多くの学校に大なたを振るったと聞いています。
しかし、私が通うこととなる公立中学校は、それに反対する教職員組合の牙城であり、両者の「争い」の最前線でした。教育委員会側と教職員側の「2つの職員室」があるようなところ、といえば理解しやすいでしょうか。
そこでの私の存在は、当然のように、入学前からどちらの勢力にも知られていました。組織メンバーは、その組織に入るまでは基本的に匿名の存在のはずです。しかし、私はそうではなかった。この環境で生き残るためにはどんな「役割」をこなさなければならないのか、最大限の注意とともに立ち回りました。
思春期の私にとって、「組織」というものは非常に居心地が悪く、得体の知れないものであり、かつ、その圧倒的な存在感を意識しないわけにはいきませんでした。その結果、この奇妙な「組織」という存在を研究する覚悟ができたのかもしれません。
そのようなバックグラウンドを有しつつ、高校に入るとはじめて自由を知りました。大学に進学後は、大学生らしく貧乏だったほかは充実した学生生活を送り、私のアパートの6畳間は多くの友人(友人の友人の友人という他人も含む)のたまり場となって、夜通し飲んだり麻雀をしたりしました。
その中には常連として、高校以来の親友であり、後にM-1チャンピオンとなる「笑い飯」の哲夫もいました。ある日、みんなで私の家で飲んで何人も潰れていくなか、最後まで起きていたのが、哲夫と私でした。
夜も明ける朝方、「俺、漫才で生きていこうと思うねん」「そうか、俺も研究で食えるかどうか試してみるわ」という会話をしたのを覚えています。
その後、お互いに苦しい時代もありましたが、今はふたりとも、それなりに目標を達成しつつあるのではないでしょうか。研究者としては素晴らしい師匠との出会いも大きかったことはもちろんのことですが、やはりターニングポイントとなった大きなものは哲夫との会話であったように思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。