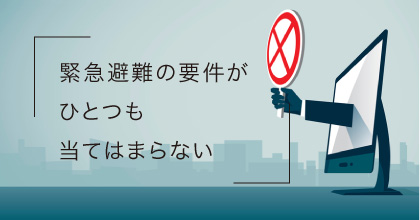人生で影響を受けた人物異文化交流をきっかけに、人生の本質を見直そう
教授陣によるリレーコラム/人生で影響を受けた人物【10】
わたしはかつて植民地だった地域や、西洋近代文化が突然入ってきたことで独自の文化から大きな変換を迫られた地域、そうした土地出身であったり、出身の祖先をもつ人々の文化や文学を研究対象にしています。
研究を通じて、オーストラリアを皮切りに、サモアやフィジーなどの南太平洋、カリブ海、インド、アメリカ、イギリスなど、様々な国を訪れ、たくさんの方と出会いました。
そのなかで最も印象深いのは、カリブ海の英語圏地域を代表する作家のひとり、アール・ラヴレイスです。出会いは、1991年に東京で開催された国際比較文学会という学会でした。
会期中、彼の通訳をつとめ、話をしたことがきっかけになり、ラヴレイスの小説『ドラゴンは踊れない』を翻訳(みすず書房、2013年。原作は1979年)、交流が続いています。
トリニダード・トバゴに行ったとき、しばらく彼の家に泊めてもらったのですが、そのとき近くで見た彼の仕事ぶりにとても驚きました。
彼は新作の小説を執筆中でした。もの書きはみんな、執筆の邪魔をされるのを嫌がる、他人などそばにいてもらいたくないものだと思っていたのですが、彼はわたしがいても少しも気にならないようでした。
もっといたらいい、というのです。とてもおいしい魚のスープもつくってくれました。
わたしの方が逆に気を遣ってソワソワし出すと、彼は「おれは一日にひとつの仕事をやる。今日、おれがやるのは魚のスープをつくること。それだけだ」というのです。
もちろん、スープづくりだけをしていたわけではなく、小説を書き、講演をし、作家たちの集会に顔を出すなど、色々なことをしていたので、それはひとつの考え方、姿勢ということだろうと思うのですが、人生を急がず自由に、悠然と歩き、楽に呼吸をしている彼の姿勢を、とても魅力的に感じました。
カリブ海や南太平洋でも感じたことですが、とくにアーネムランドなど昔ながらの暮らしの気配が色濃いオーストラリアの先住民族コミュニティでは、ライフスタイルのリズムが日本とは違うと思いました。
時計の時間ではない、人間の時間というものがあるのではないか、そう考えました。
日本で生きている多くの人たちの呼吸は、時計に刻まれています。5分刻みのスケジュールを立て、きまった時間に間に合うようにつねに時計を見て動く。
一日にいくつもの用事をこなすのが当然で、多くこなすほど優れている、といった価値観がひろまっている。でも実際は、息が上がっている、ときどきそんな気がするのです。
脇目も振らず努力をし続けて成果を上げるのは、人間にとって最良の生き方なのでしょうか。新たな幸福論がいま、人間には必要なのではないか。そう考えるとき、ラヴレイスのことを思い出すと、そうしたことに考えをめぐらせることは危機状況を生きのびるために不可欠な、大切なことであると同時に、とてもわくわくする楽しいことでもありえる、そんな風に思えてくるのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。