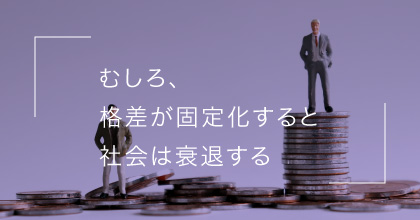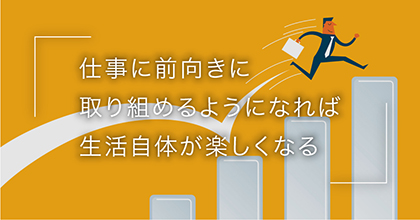人生で影響を受けた人物「虫の目」と「鳥の目」で物事を相対的に捉えよう
教授陣によるリレーコラム/人生で影響を受けた人物【5】
私は人文地理学を専門にしていますが、もともと地図が好きで、地図を片手に紀行文や地域研究の書籍を読むのが趣味でした。
その中で、地理学の道を進むにあたり特に影響を受けたのは、若い頃に読んだ3人の学者によるものです。
シルクロードの楼蘭を発見した探検家で、地理学者でもあったスヴェン・ヘディンの『さまよえる湖』に、民俗学者の宮本常一が手掛けた日本各地の記録。
そして、地理学や民俗学の観点から人間活動が自然界に及ぼす影響を研究した、千葉徳爾による『はげ山の研究』。
私はこれらの書物を通じ、研究者として大事な視点を教わった気がします。
彼らに共通しているのは、虫の目でフィールドに入って細かく調査すると同時に、そのフィールドを鳥になって俯瞰的に見ているところです。
このことは、フィールドワークを行ううえで極めて重要です。
例えば、学生たちはゼミや卒論研究のために現地に赴くと、一生懸命に調査して少しでも多くの情報を収集しようとします。
しかし一方で、現場に夢中になるあまり全体像を見失うこともあります。調査対象への情熱を持ちつつも、常に冷静に俯瞰することが大事なのです。
ビジネスの世界でも、こうした物事の捉え方が有益となる場面も多くあるのではないでしょうか。
一つのことを掘り下げる「虫の目」と、全体を俯瞰する「鳥の目」。この二つを意識すると、これまでとは異なる新しい考え方やアイデアが見つかるかもしれません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。