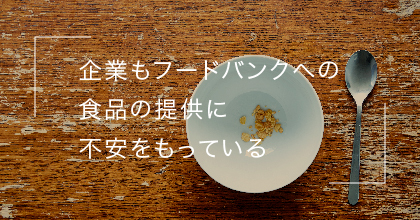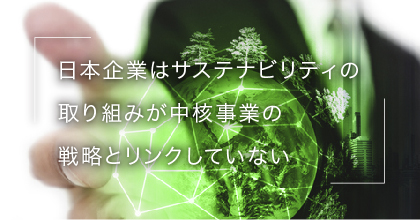
日本企業はサステナビリティの取り組みが中核事業の戦略とリンクしていない
2014年に、世界4大会計事務所のひとつであるPwCが、ロンドン証券取引所に上場する時価総額上位100銘柄と、日本のTOPIX100構成銘柄に含まれる100社に対して、サステナビリティ報告書の調査を行っています。
その結果、「日本企業はサステナビリティの取り組みが中核事業の戦略とリンクしていないことが多く、長期的な視点で何が重要な課題であるのかを明確に示せていないこと、具体的な取り組みにおいてもその実績が計測可能なKPIによって示されていないこと」が指摘されました。KPI(Key Performance Indicator)とは、企業目標の達成度を評価するための指標を指します。
要は、世界基準から見ると、日本企業はサステナビリティの取り組みが不十分であり、その達成度も実績も曖昧であるということです。
私は、日本企業がグリーン・ウォッシュばかりであるとは見なしていません。それより、マネジメント・コントロール・システムとサステナビリティ・コントロール・システムを別個のものとして捉え、その統合を考えていない、もしくは、統合の方法がわかっていないことが問題なのだと思います。
この連載の第1回で述べましたが、日本の企業は、サステナビリティに関することは企業にとってコストだという旧態依然の認識からなかなか進歩していないのです。
サステナビリティ課題は、事業活動を通じて解決でき、企業の収益に結びつくものを選択する必要があります。広告宣伝や単なるIRではありません。その企業の技術やサービスで社会が抱える課題を解決し、対価を受け取るものであり、その仕組みは長期的に企業価値を高めることに繋がるマネジメント・コントロールとも言えるわけです。
自社にどのようなサステナビリティ・マネジメント・コントロールの仕組みを構築していくのかは、各企業それぞれによって異なります。
なにが自分たちの強みで、サステナビリティの課題への解決に対して、自分たちの強みをどのように活かすことができるのか、それは各社で異なるからです。
例えば、女性の活躍推進もそのひとつかもしれません。日本は役員に占める女性比率がG7の中でも極端に低くなっています。固定的な価値観の中では思考が硬直しがちです。多様な視点を取り入れるためにも女性の活躍を推進することは、その企業にとって強みとなるはずです。
その意味では、長時間労働の是正に繋がるテレワークや働き方改革がコロナ禍によって普及したことは、ひとつのきっかけになるかもしれません。
企業によって長時間拘束される状況では難しかった、家事や子育て、介護、あるいは副業が促進され、その体験が本業に還元されれば、新たな発想やイノベーションも起こりやすくなるかもしれません。
サステナビリティ経営はトップや経営陣だけが考えるものではなく、現場の従業員が当事者意識をもち、自分たちの強みや自分たちになにができるのかを、ボトムアップしていくことも重要です。
日本企業が世界の企業の中で時代遅れになっていかないためにも、私たち一人ひとりにできることはあると思います。
#1 企業もサステナビリティに関わる必要がある?
#2 サステナビリティ経営を株主は認める?
#3 日本の企業はサステナビリティを重視している?
#4 サステナビリティ経営は政治に左右される?
#5 日本の企業は時代遅れになる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。