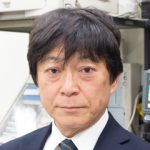アイデアの泉「聞く、見る、動く」をベースに発想を広げよう
教授陣によるリレーコラム/アイデアの泉【31】
本学では知的財産を社会に還元する生涯学習を行っており、私も社会人に向けた健康科学の講座などを担当しています。
講義後は受講生の皆さんから色々な質問を受けるのですが、自分はまだその方々の年代に達していないため、高齢者の方が何を考え、どう思っているのか、生の声を実際に聞ける貴重な機会になっています。
そこでは自分自身が考え及ばない老化の現実に気付かされることが多々あり、いままで自分を基準に物事を考えていたのが、違う視点に立つと「求められているのはこういうことなのか」などとわかってくるのです。
このように性別や年齢を問わず様々な意見を聞くことは、自分にはなかった発想を呼び起こす良いきっかけになると思います。
また、観察を行うことも着眼点を変えるのに役立ちます。
私の主な研究テーマは、走る、跳ぶ、投げるなどの動作分析なのですが、実験を計画する際は簡易的に動画を撮り、徹底的に観察します。
たとえば「立ち幅跳び」ひとつをとってみても、年代によって特徴があります。幼児のときは脳の発達が未熟で、跳ぶときに腕を振らない子が多かったのに対し、小学校にあがってしばらくするとみんな腕を振ることを覚えるようになるのです。
逆に、高齢者になると脳の中のネットワークが萎縮してしまい、ジャンプするときに腕を使うことを忘れ、再び幼児のように脚の力だけで跳んでしまうようになります。
こうした観察を通じて動作と脳には密接な関係があることを意識しながら研究ができ、新しい発想のヒントへと繋がっていくのです。
最後に、アイデアが生まれないときや考察が行き詰ったとき、私が実践している方法をお教えします。
どうしてもここから話が進まないな、というときには走りに行きます。懸念事項を頭の片隅に置いたまま走っていると、研究室では思いつかなかった発想がふっと浮かんでくるのです。
脳の中が一度リセットされると同時に、脳内で色々なホルモンが分泌されて、新しい考えが出てくるのだと推測しています。ジョギングが難しい方はウォーキングでも何でも構いません。常に考えながら体を動かすことでアイデアを進展させること、お勧めです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。