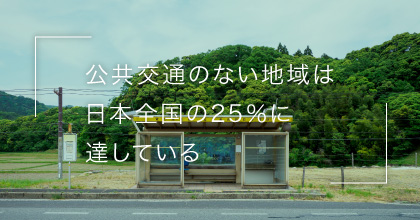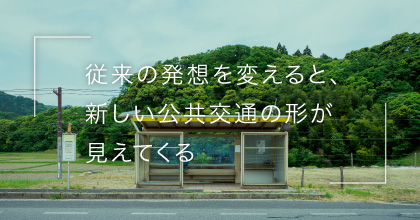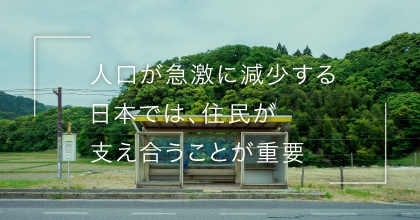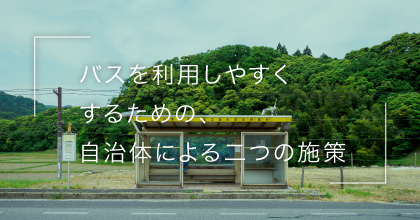
バスを利用しやすくするための、自治体による二つの施策
新しい地方公共交通に取り組んでいる自治体のひとつに、兵庫県豊岡市があります。
従来の発想では、バスが住宅地をきめ細かく回ることが良いサービスでした。しかし、人口が急激に減少している現在では、これは非効率になりがちです。
そこで豊岡市では、バス路線を、住宅地をきめ細かく小さく循環するフィーダー線と、都市部の病院や駅、ショッピングセンターなどの主要施設間を走る基幹線に分けました。
住民は近くの停留所からフィーダー線のバスに乗り、結節点といわれる基幹線に接続する停留所に移動し、そこで基幹線のバスに乗ります。
基幹線とフィーダ線の運行頻度は、それぞれがそれぞれの需要にあわせて変えることが可能で、バス路線全体の効率を高め、より経済的に運行できるようになるわけです。
この豊岡市と、ある意味、反対の発想から取り組んでいるのが、富山県富山市です。
住民が住んでいる地域にバスをどう走らせるかではなく、バス路線のある周辺に、住民に住んでもらおうという取り組みです。
市では、指定した地域に移り住む人に補助金を出して推進しています。人口密度の低下が続いている地域では、住む場所を「面」で考えるのではなく、必要な施設と繋がる「線」で考えてもらおうという発想は、他の多くの自治体からも共感を呼び、注目されています。
さらに、公共交通の路線を意識した住宅計画は、国交省も立地適正化計画という政策で推進しています。人口がさらに減少する今後は、私たち生活者にとっては、交通インフラを意識した住み方が重要になってくるかもしれません。
次回も、交通空白地域問題に取り組む自治体の例を紹介します。
#1 交通空白地域って、なに?
#2 コミュニティバスって、なに?
#3 バスを利用しやすくするためには?
#4 コミュニティバスの財源をどうする?
#5 公共交通を支えるために住民にできることは?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。