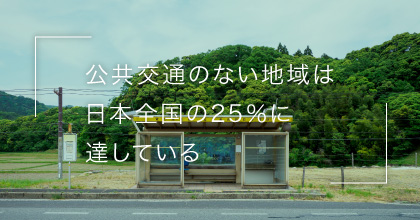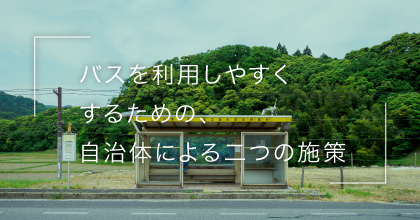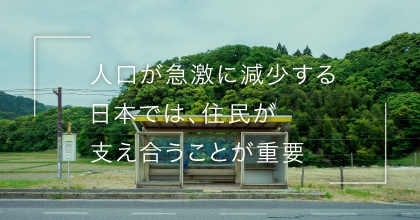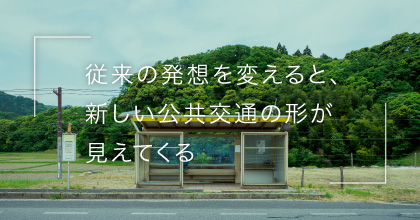
従来の発想を変えると、新しい公共交通の形が見えてくる
バスは、私たち生活者にとって最も身近な公共交通です。民営と公営のバスがありますが、ここ数年は両者とも経営が厳しく、民営の6割、公営の9割が赤字になっています。
そこで、公営バスも様々な工夫を行っています。人件費を抑えて事業をスリム化したり、あるいは、一部の路線を民間に委託するなどです。しかし、採算はなかなか上がらず、赤字は税金で補填する状況です。
そこで、新しい発想による公共交通が始まっています。そのひとつが、コミュニティバスです。
従来のバス経営は、料金収入で運営していくという発想でしたが、コミュニティバスは、料金を100円とか200円と、利用者が利用しやすい安い料金に設定しています。
つまり、料金収入で運営しようというのではなく、最初から、税金で運行することを前提としているのです。
そこで、車両を、従来のような大型ではなく、必要十分なサイズのマイクロバスにしたり、路線も、従来のように住宅街をとにかくきめ細かく走るのではなく、本当に必要なコースに絞ったりと、できるだけ経費を抑えて、効率的に運行するようにしています。
すると、料金収入で運営することが前提で、赤字になると税金で補填していては職員の士気は高まりませんが、最初から税金で運営することが前提だと、利用者や住民にどんなサービスができるか考えたり、経費をできるだけ抑えたり、他の財源を工夫しようとします。
その中で、料金+税金の他に、受益者負担金や沿道法人の協賛金という発想も生まれてきました。大切なのは、公共交通を維持するために、自治体だけでなく、地域住民や法人も協力し合い、工夫していくことです。そうすれば、コミュニティバスは今後も発展していくと思います。
その他にも、デマンド交通を活用する発想もあります。例えば、病院に行こうとするとき、1人で配車するのではなく、同じ病院に行く人たちを誘って、乗り合いで行くのです。
すると、一人ひとりの料金負担は軽くなりますし、近所で声を掛け合うことで、引きこもりがちになる高齢者を外出させることにも繋がります。また、それによって交通の使用頻度が上がれば、運営会社の採算性も上がります。
近年、シェア経済が注目されていますが、住民が交通の需要をまとめて移動手段をシェアすることはこうした活動にも繋がり、今後も発展する可能性があると思います。
次回は、交通空白地域問題に取り組む自治体の例を紹介します。
#1 交通空白地域って、なに?
#2 コミュニティバスって、なに?
#3 バスを利用しやすくするためには?
#4 コミュニティバスの財源をどうする?
#5 公共交通を支えるために住民にできることは?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。