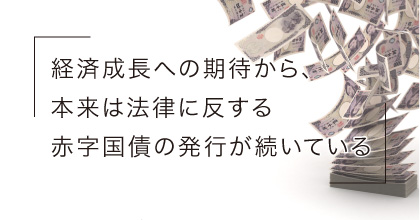40歳までに読んでおきたい本自分の専門外にも目を向けて、可能性を広げよう
教授陣によるリレーコラム/40歳までに読んでおきたい本【26】
私の知り合いに柔道の元オーストリア代表でアスリートのキャリアについて研究している研究者がいるのですが、彼女が日本に来て驚いたのはデュアルキャリア(「人としてのキャリア形成」と「アスリートとしてのキャリア形成」を同時に取り組む考え方)の環境が整っていたことだそうです。
日本の大学スポーツでは、大学で勉強して学士の資格を取りながら、立派な施設と一流のコーチ陣のもとでスポーツに集中できる。ヨーロッパには学校スポーツ(運動部活動)がありませんので、なんて素晴らしい環境だろうと思ったとのことです。
ただ、彼女が研究を進めていく上で違和感を持ったのが、選手たちの意識だったそうです。頭のなかは柔道でいっぱいで、休日は部屋でボーっとしているかゲームをするだけ。映画や音楽など柔道以外にほとんど趣味を持たず、将来の目的もビジョンもない。
つまり、せっかく学業とスポーツを両立できる素晴らしいデュアル環境に恵まれているのに、肝心のアスリートの意識がデュアルになっていない。
また、Jリーガーのキャリアサポートをしている方によると、サッカーだけに専念して他のことにほとんど関心を持ってこなかった選手は、引退後に次のキャリアに進むのに苦労する傾向があると仰っていました。
もし現役時代に少しでも他に関心のあること、人生のオプションを持っていれば、サッカーがダメだったら次はこれをやってみようというふうに、もっと切り替えが早くいくのではないかと。
もはや使い古された言葉ですが、このように人生の選択肢を増やすのが「教養」であり、教養を積むうえでもっとも重要な行為が読書です。
引退後も幅広く活躍しているスポーツ選手には読書家の方が多いようです。ボキャブラリーが豊富でなければマスコミの仕事も務まらないでしょう。
これはスポーツ選手に限らないと思います。日本はすでに経済の停滞期に入り、大企業といえども盤石ではありません。
終身雇用、年功賃金といった日本的雇用慣行も確実に後退しており、1つの企業に定年まで勤め続けることが、いままでのように当然ではなくなってきています。
そうしたなか、企業にとって都合の良い資本だけ身につけようとしていてはリスクが大きい。あるいは、現代はかつて以上に「教養」が必要な時代なのかもしれません。
ちなみに私からお薦めする「40歳までに読むべき本」はありません。それは皆さん自身が決めるものだと思います。何より、読書は習慣です。日ごろから読むクセがついていない人に本を薦めても、たいてい読まないでしょう。
若いうちに本を読んで読書の習慣をつけておけば、いずれ必ず自分にとっての「読むべき本」に、たくさん出会えるでしょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。