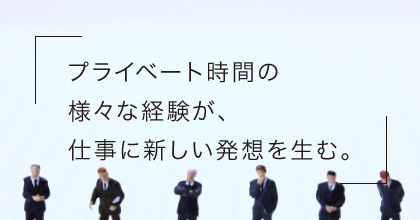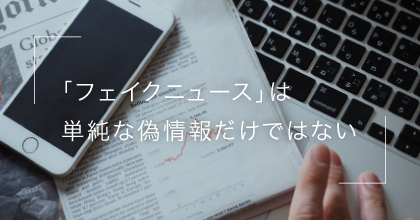フェアネスを大事にすることが長期的な成長に繋がる
セイラー教授の指摘の中に「フェアネス」があります。これは、企業活動においてとても重要なことです。例えば、急に雪が降ってきて積もったとき、住民たちは雪かき用のシャベルを求めて店に行きます。すると、店はシャベルの価格を大幅に値上げしていました。住民たちは腹を立てますが、高いシャベルを買わざるを得ません。この場合、需要の上昇にあわせて商品の価格が上がることは、従来の経済学ではまったく問題のない商業活動と説明されます。しかし、実際の顧客に調査をすると、自分たちの足元を見ている、アンフェアだという答えが多いのです。すると、店側は短期的には利益を上げて儲かりますが、顧客の信用を失い、長期的には利益が落ち込むことになってしまいます。そこで、行動経済学では、顧客の信用を失うようなアンフェアなことはしてはいけない。フェアネスを大事にすることが企業の成長に繋がると説明するのです。とにかく利益を追求し、市場の競争に勝ち、生き残るのが企業経営だと思いがちですが、そうではないことを明らかにしたのです。この連載でも述べてきましたが、顧客の心理を突いた販売テクニックもアンフェアになると、顧客の信用を失います。大問題になった事件として記憶に新しいところでは、2013年にプロ野球チームの優勝記念セールで、77%オフを打ち出したネット通販大手が、公正取引委員会の価格表示ガイドラインに抵触するような二重価格表示を行っていた例があります。販売テクニックを過信してアンフェアを行ってしまうと、顧客の信用を取り戻すのは大変です。
また、社員の働き方や働く環境を行動経済学を基に考えると、成果主義のようにお金で人を動かすやり方は短期的には良くても、長期的にはマイナスになることがわかると思います。もちろん、人は収入を得るために働いているのですが、ある程度の収入が得られれば、仕事に対するモチベーションや、会社に対するロイヤリティを高めるのは、やり甲斐のある仕事に取組み、達成感を得たり、自らの有能感を覚えることではないでしょうか。
人は、お金だけで動くのではないという考え方は、行動経済学が一番重視している考え方です。それは、顧客に対しても、働く社員に対しても言えることです。この行動経済学の考え方に基づく経営戦略が、企業の長期的な成長に繋がっていくと思います。
#1 いま注目の行動経済学って、なに?
#2 行動経済学で賢い消費者になれる?
#3 失敗しない買物テクニックとは?
#4 行動経済学で政策も成功する?
#5 行動経済学で企業経営も成功する?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。