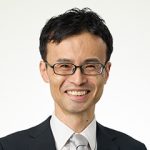今後の課題:理論的なレベルと具体的なレベルの両方を掘り進めることが重要
これまでの労働法のなかでも、雇用関係にない人たちを保護する仕組みが一部には設けられていましたが、今回のようにフリーランスをターゲットとする一般的な法律が制定されるのは初めてのことです。フリーランスをサポートするプラットフォームとしての役割が期待されます。
フリーランス法施行後の次の段階では、理論的なレベルと具体的なレベルの両方を掘り進めて検討することが重要です。
理論的レベルに関しては、経済法的なアプローチも労働法的なアプローチも、働く人を保護する点では同じですが、どちらのアプローチをとるかは、より深い検討が大事です。たとえば労働組合法は、働く人たちが集まることを保護する規制であるのに対し、経済法では、カルテルの禁止を謳うなど、事業者が集まって何かをすることについて消極的な側面もあります。両者のアプローチが同じ方向を向いていない分野もあるため、その関係性を考えていく必要があるでしょう。両法の関係を突っ込んで考えることがあまりなかったのですが、今後はそういうわけにもいきません。
具体的なレベルに関しては、フリーランスのサポートについては、すでに一定の手当てがなされている事項もありますが、まだこれからというところもあります。たとえばフリーランスとして働いている人がケガをしたとき、どう対応することが求められているのか。労災保険では、一定の要件を満たした場合、労働者でない人も特別に加入できるという仕組みが追加的に設けられました。フリーランスも任意で加入できるよう、制度改正がなされたというわけです。
他方で、仕事を失った場合、なんらかの所得保障が必要なのか。今後、フリーランスとして働いたり、フリーランスと労働者を行き来したり、労働者として働きながら副業でフリーランスをしたりと、さまざまな働き方が考えられるなかで、労働者であれば雇用保険で対応しているものをどうするか、外国の制度も参照しながら検討していくことが大切でしょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。