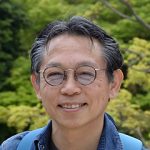植物には素晴らしい温度センサーの仕組みがある
例えば、それぞれの植物は、なぜ、決まった季節に芽を出したり、花を咲かせたりすることができるのか。その仕組みは長い間わかっていませんでした。
おそらく、植物は温度センサーのようなものを備えていると思われますが、それがなんなのか、わからないのです。ただ、植物の反応を調べる実験などを行うと、1℃の違いも感知していることがわかります。
5年ほど前に、植物の光センサーが温度センサーの役割も担っているという論文が出され、さらに、昨年の夏には、「プリオン」の性質を持つタンパク質が温度の反応と関係しているという論文も出されました。
このプリオンは狂牛病やヒトのプリオン病の病原物質として知られていて、アルツハイマー病の患者の脳に溜まることもわかってきており、関心が高まっています。元々持っているタンパク質ですが、立体構造が変化して病原性を発揮します。一方で、長期記憶の形成と維持などに働き、悪さをするだけではない可能性も示されています。
私たちは植物の種子が「どんなしくみで発芽の季節を決めるか」をメインに研究しています。種子は土壌の中にあるので光を感じることができないことがあります。でも、土壌も、日光の当たり方で温度が変化します。植物はそれを感知していると考えられます。
すると、光センサーとは別の温度センサーも働いているということになります。つまり、植物の温度センサーの仕組みはひとつではなく、非常にたくさんあるのではないかと考えられるのです。
例えば、日光が当たる角度や時間の長さによって地中の温度も変わるので、種子の温度センサーはそれを捉えて、自分が発芽すべきかどうかを決めていると考えられます。
しかし、そのときどきの温度を感知するだけでは、いまが春なのか秋なのかわかりません。ところが、種子は、低い温度が続いてから上がってきたから、いまは春、高い温度が続いてから下がってきたから、いまは秋と捉えることができるのです。
つまり、温度データを、いわば記憶することができるのでしょう。そこで、夏に成長する植物は春に芽を出し、暑さに弱い植物は秋に芽を出すことができるのです。
さらに、昼夜の温度差を利用している植物もあります。日光が直接当たる地面は、昼間温まり、夜になると冷えるので、地中の温度差も大きくなります。日光がなにかに遮られている地面は、昼間の温度がそれほど上がらず、夜との温度差はあまりありません。
すると種子は、本来、発芽する季節になっても発芽しないで、そのまま休眠を続けます。種子によっては何十年間も休眠し、生き続けるものもいます。
一方、昼と夜の温度差が大きいところだと、発芽すべき季節にちゃんと芽を出します。それは、その場所は日光がよく当たるところなので、芽を出したあとに光合成が充分に行え、成長していけるからです。
そうでない場合は、良い条件になるまで種子は芽を出さずに休眠し続けるわけです。
このように、種子は温度センサーによって芽を出す季節を捉えるだけでなく、発芽後の成長が保証される時季を逆算して、芽を出す選択をすることができるのです。
植物がもっている、こうした一連の仕組みを解明することを私たちは目指しています。それによって、地球温暖化の進行によって、発芽や開花の時期が狂ったり、しなくなる植物を、正常な成長に戻すサポートの方法が見つかるかもしれません。
すると、元気な植物を増やし、それによって大気中の二酸化炭素を固定する量を増やすこともできることになります。
それは、植物にとってもストレスとなる地球温暖化を抑え、気候変動を抑えるとともに、持続可能な食料生産に繋がっていくことにもなります。つまり、植物は、こうした好循環の要にいるのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。