バイオプラスチックの普及のために消費者の意識が高まることにも期待
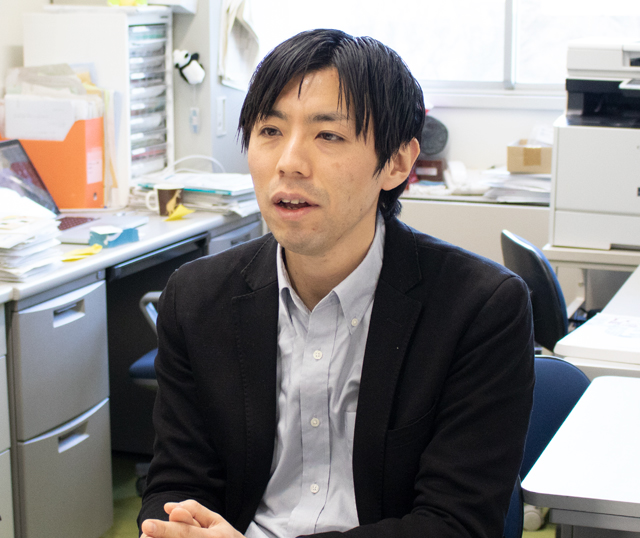 つまり、バイオマスプラスチックを作る技術は開発されているものの、製品として、コストに見合う生産方法がまだ確立されていないのが実情です。どうしても、従来のプラスチックよりもコスト高になってしまうのです。
つまり、バイオマスプラスチックを作る技術は開発されているものの、製品として、コストに見合う生産方法がまだ確立されていないのが実情です。どうしても、従来のプラスチックよりもコスト高になってしまうのです。
その結果、バイオプラスチックの普及はなかなか進まず、全プラスチックの1%にも満たない量にとどまっています。
例えば、私たちの身の回りの製品では、ペットボトルやシャンプーの容器などに使われているものがあります。それらには、日本バイオプラスチック協会が認定した、グリーンプラ・マークや、バイオマスプラ・シンボルマークが付けられていますが、それを意識して購入する消費者はあまり多くありません。
メーカー側はそれらの商品の価格があまり高くならないように企業努力していますが、バイオプラスチックを使っていることが購入に結びつかないのであれば、その努力にも限界があります。
つまり、多少高くても、環境に良いのだからバイオプラスチックを使うべきだ、という理屈は通用しないのが現実なのです。
そこで、いきなり、大量生産されるバルクケミカルを目指すのではなく、高付加価値によって、多少高くても売れる製品を作ることから始めるのが得策だと考えています。
例えば、現在、その代表的な例が農業用マルチフィルムです。畑の畝を覆い、畑に雑草が生えることや、土壌から水分が蒸発してしまうことなどを防ぐ資材です。
従来の石油由来のビニール製のものは、収穫が終われば剥ぎ取らなければなりませんし、廃棄するにも廃プラ処理費用が必要でした。でも、生分解性のバイオプラスチックであれば、そのままの状態にしておけば自然に分解されてなくなります。労力も費用もかからなくなるのです。
このような付加価値のある製品でバイオプラスチックの普及を図り、安価で大量なプラスチック製品の生産につなげていく二段構えが必要だと考えています。
私たちは、目の前の問題が劇的に改善されると感心しがちです。例えば、病気を治してもらえると感謝します。でも、実は、病気に罹らないように予防することが大切です。
バイオマスプラスチックの開発もそれと同じで、石油由来のプラスチックが使われ続けることによって、廃プラスチックの処理が追いつかずゴミが溢れたり、海洋汚染が進んだり、CO2の排出が増え続けて、私たちに重大な影響が出てから、それを直そうとするのではなく、そうならないように、先んじて対策を行おうということなのです。
そのために、私たち研究者はバイオプラスチックの開発を目指しているのですが、消費者の皆さんが意識を高めることにも期待しています。
実は、日本は、欧米に比べて、一般生活者の環境問題に対する関心が低いといわれています。多少高くても環境に良いものを買う、という理屈は通用しないと述べましたが、その傾向は欧米より日本の方が強いのです。
でも、海に囲まれた日本が、石油由来のプラスチックで海洋汚染をし続けることは、本当に取り返しのつかないことになるかもしれないのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




