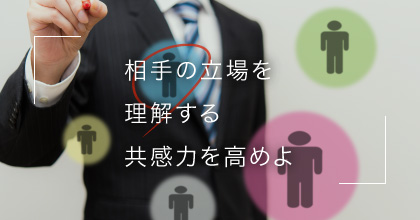人生のターニングポイント「朝顔やつるべ取られてもらい水」
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【51】
日本語、日本文学、日本文化に興味をもつきっかけは、中学生のときに(1974年ごろ)、台湾出身の父親に俳句を教わったときでした。
最初に教えてくれたのは、加賀の千代女の「朝顔やつるべ取られてもらい水」という句でした。つるべに絡む朝顔を傷つけず、井戸の水を汲まないで、どこかへ水をもらいに行く、という歌人の優しさに感動しました。
文化大革命(1966年〜1976年)の殺伐な社会で暮らしていた自分は、この思いやりをとても新鮮に感じました。また、わずか17音でこれだけの感情を表すことができる俳句という詩形に驚きました。
それまでは欧米の小説を読んでいた自分は、日本文学の翻訳を読むようになりました。原文で日本文学を読みたいと思って、日本語の学習を一生懸命にしました。上海の復旦大学では日本語日本文学を専攻することにしました(1980年〜1984年)。
大学を卒業してからすぐお茶の水女子大学に留学しました。まもなく京都へ遊びに行きました。
龍安寺の石庭を見ました。そのときにうけた衝撃は忘れられません。一面の小石と大きな岩数個だけで、茫漠たる海とぽつんとした孤島を即座に連想させてくれました。
このように極めて簡素な形で、限りない自然を表現することは、日本文化の真髄として伝わってきました。この石庭に心を奪われた私は、いくら見ても見飽きないと感じました。
私は外国人として日本文学を学び、日本文化を観察しているうちに、他の外国人の日本研究にも興味をもつようになりました。
ある時、青森県弘前市のカトリック教会に行ってみました。カナダ人宣教師の日本語のうまさに舌を巻きました。
宣教師は、日本語が上手でなければ、日本文化を深く理解しなければ、キリスト教を日本人に伝えることは困難だろうと思い及びました。そのときから、外国人宣教師の日本語著作を読むようになり、日本文化に対する宣教師たちの洞察の深さと、福音を伝える言葉の修辞性に感心してきました。
このようにして、私は「宣教師の日本語文学」を研究するようになりました。
そこから、自由、平等、博愛などの普遍的な価値観を学ぶことができたし、日本文化と日本文学に根ざしているキリスト教の深さにも改めて気づきました。キリシタン世紀から現在まで500年近い歳月に刻まれた宣教師の努力があるからこそだといえましょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。