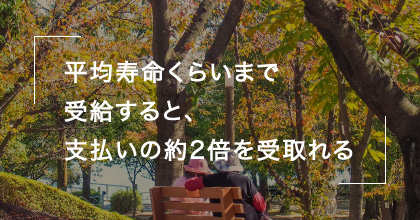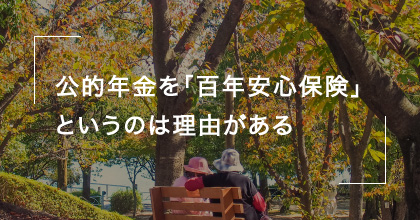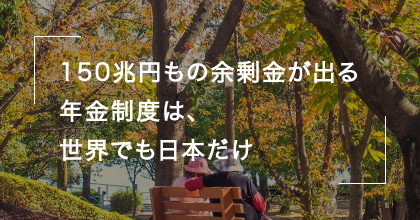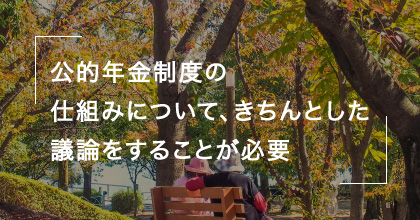人生のターニングポイント学び直して痛感した、実務と学術をつなぐ重要性
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【40】
私にとってのターニングポイントは、社会人として大学院で学び直したことです。もともと金融機関の研究所に勤めていたのですが、民間の研究と学術研究の違いを強く思い知らされました。
それまでは実務に直結していた点、物事の動きが早い点、最先端のものに触れられた点がとても面白くて刺激的でしたが、学術研究で重要なことは全く別。5年経っても100年経っても変わらない普遍性と、誰が試みても同じ結果が出る再現性が求められます。民間の研究所では、ライバル社もできるようなことだといけません。ほかを出し抜けるような独自なものがいい研究とされるので、ものすごく対極的だと感じました。
「変わらないこと」を見いだすのは、経営学の分野ではとても大変ですが、先人たちが書いている論文は本当に普遍的です。社会人として大学院で学ぶうちに、実務の分野で課題だと思っていたことは、すでに誰かしらが論文にしている可能性が高いことがわかりました。論文にする段階で抽象化されてしまうため探しだすのが大変ですが、たどり着けると「ここに答えがあったじゃないか」と気づく。ちゃんと学んでおけば良かったと思うことが数多くありました。
再現性の観点からは、OJT(職場内訓練)の限界を知ったことも大きな気づきです。日本には仕事をしながら覚えるOJT型のカルチャーが根づいていて、その良さもありますが、どうしても今の仕事に直結することしか学べません。しかしその業務に関することは、先輩たちが改良に改良を重ねているため、ある意味、限界が来てしまっていることも多い。それに対し経営学を知識として身につけると、自分とは関係がなかった分野でも、先達の知見から問題の本質を捉えて理論を実践することも可能となり、打開へとつなげられます。
在学中は、働きながら学ぶことのハードルの高さも、身をもって感じました。今年(2023年)の4月に専門職大学院に着任し、仕事を持ちながらさらに学びたいという方々の指導ができるようになり、この上ない喜びを感じています。複雑性を増す社会で、民間と学術的な部分とのコラボレーションが、ますます求められるようになる。その橋渡しをする人材はとても重要です。再進学だけに限らず、深く学ぶことで、橋の向こう側に眠っている役立つ知見が見えてくるでしょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。