
2022年7月、ドイツでは、人工妊娠中絶(以下、中絶)の宣伝に対する処罰規定である刑法219条aが削除されました。これは、旧西ドイツで「68年運動(学生運動)」直後に展開された中絶合法化運動と1976年の中絶法改正、および大論争の末に実現した1995年の中絶法東西統一を想起させる大きな出来事です。
ドイツ近現代史にみる中絶問題をめぐる論争
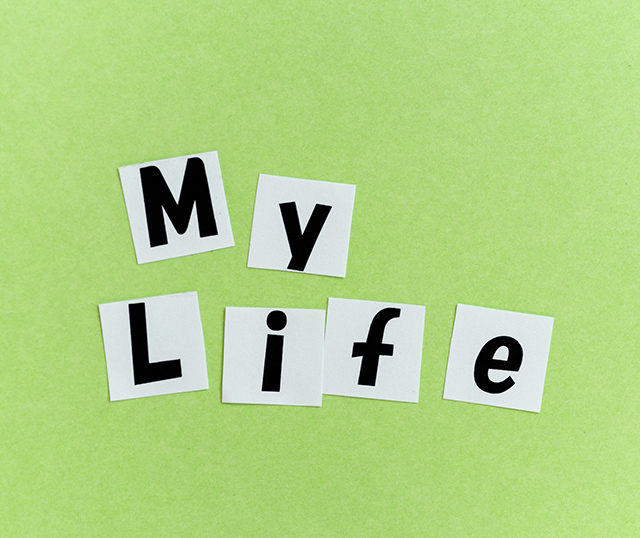 「セクシュアリティはもっともプライベートであるがゆえに公の場で話すようなことではない」という感覚が、日本では今もなお根強く残っているように思われます。日本でもセクシュアリティについて公的に議論しようという試みがなかったわけではありません。しかし欧米ではかなり前から、その動きがみられました。
「セクシュアリティはもっともプライベートであるがゆえに公の場で話すようなことではない」という感覚が、日本では今もなお根強く残っているように思われます。日本でもセクシュアリティについて公的に議論しようという試みがなかったわけではありません。しかし欧米ではかなり前から、その動きがみられました。
たとえばドイツでは、中絶が法的に禁じられるなか、1871年の統一後、とりわけ20世紀への転換期頃から、中絶に関する議論が公的な場でなされるようになります。その背景として、産児制限※1による人間の質(能力)の向上と貧困からの脱却を目的に、子ども数の制限および小家族化の必要性を説く新マルサス主義と、社会ダーウィニズムの広がりがあげられます。中絶はプライベートな事柄にとどまらず、政治と深くかかわってきたのです。
中絶をめぐる議論が論争・運動へと発展した例はドイツ史において、またドイツ以外の国でも歴史的に確認できます。その代表的な例として、1960年代後半以降、西側諸国で起こった第二波フェミニズム運動があげられます。1960年代に入ると人権概念が広く浸透し、それは女性の権利を訴える運動へとつながっていきました。
たとえば「68年運動」直後、旧西ドイツでは「私のおなかは私のもの」というスローガンが掲げられ、中絶合法化運動が起こります。1971年6月6日にはフランスの例※2にならい、実際に中絶を行った女性たち374人が、ドイツを代表する週刊誌の一つ『シュテルン』誌で自らの経験を告白しました。
この中絶合法化運動は、社会的身分も性差も超えて展開されました。女性ばかりではなく、男性も男性の立場からこの問題を考え、なかには女性と協力して大々的なデモを行うなどの動きもみられました。
また、キリスト教徒の間では、相対的にカトリック教徒よりもプロテスタント教徒の方が中絶に理解を示すといえますが、宗派・宗教を超えた議論が起こりました。さらに、各主流政党内でも意見が割れました。こうした論争を経て、1976年に医学的・優生学的・犯罪的・社会的(経済的)事由による中絶が違法とされなくなったのです。
他方、東側諸国の優等生である旧東ドイツでは、旧西ドイツのような「下からの」社会運動なしに、人民議会および国民の間で十分に議論されることなく、国家主導により1972年に妊娠12週以内の中絶が認められています。
中絶をめぐる論争は、戦後東西に分断されたドイツが1990年に再統一された際にも過熱し、中絶法の統一に至るまでに約5年を要しました。その間、この法律が成立しなければ、東西統一の実現は難しいとまでいわれました。
中絶の大きな争点としては、胎児の命や人権を守るという観点と、女性の自己決定権という観点があります。前者は無視してはならない観点です。他方で、中絶は女性個々人が抱えているさまざまな事情・問題を十分考慮したうえで下された“私”の決断です。女性たちは胎児の命を軽んじているわけではありません。
それゆえ、女性たちの決断を尊重し受けとめる社会であることも重要なのではないでしょうか。そのためには情報共有が必要です。しかしこれまでドイツでは、医師や病院が中絶について情報提供することは「宣伝」とみなされ、そうした行為を違法とする刑法219条aが存在しました。
これに対して、2017年にギーセンの産婦人科医クリスティーナ・ヘネルさんが妊娠中絶の詳細な情報をネットに公開するなどの抗議行動を行ない、以降、同条の是非をめぐり数々の論争や社会運動が行なわれました。その結果、刑法219条aが撤廃されたのです。
今、こうして中絶への社会的関心が再燃したことは、中絶問題にとどまらず、セクシュアリティと政治社会との関係性や、セクシュアリティに対する政治的介入について今一度考える貴重なチャンスといえます。
※1 バース・コントロール。避妊・中絶など、人為的手段によって受胎・出産の制限や調整を行うこと。
※2 1971年4月5日、フランスの『ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール』誌に、シモーヌ・ド・ボーヴォワールを中心に企画された「343人の女性たちの宣言」が掲載された。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




