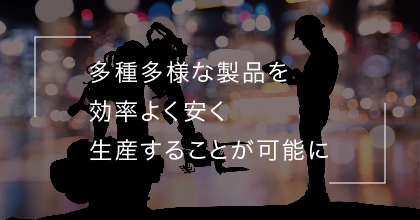
多種多様な製品を効率よく安く生産することが可能に
「インダストリー4.0」によって変わるのは、もちろん、製造の過程(プロセス)です。
従来は、製造過程をライン化、まさに線形モデルにすることが最も効率的でした。例えば、自動車工場の組付け工程では、通常、直線状にプラットフォームに載せられた車体に、ワイヤーハーネス、窓ガラス、ダッシュボード、そして椅子等々の部品が組付けられていきます。
これを淀みなく流れ作業することが、マスプロダクション、すなわち大量生産を可能にしてきたのです。
その結果、私たち消費者は、実に多くの工業製品を安く手に入れることができるようになったのです。
ところが、工業製品がある程度行き渡ると、消費者はカスタマイズを求めたり、企業は販促のためや消費者ニーズに合わせて、アップデートを頻繁に行うようになります。
すると、線形モデルではコストがかかったり、生産にタイムラグが生じたり、あるいは、対応しきれなくなることも起こります。
つまり、従来は最も効率的だった線形モデルが、むしろ、非効率な製造モデルになってきたのです。
そこで、市場のニーズを仮想としてのデータとして吸い上げるとともに、そのデータを製造のすべてのステークホルダーが同時に共有し、オートマティックに、必要な現実の物を必要な量だけ必要なときに調達する進化したジャスト・イン・タイムというシステムが必要になってきたのです。
それを実現するのが「インダストリー4.0」のひとつの使命です。
それは、製造モデルの非線形化から可能になります。
例えば、従来はAという製品を作るためのラインでしたが、市場からのデータなどを基に、どこの工程を換えれば、製品Bにも製品Cにもすることができるか把握できれば、組付け可能な工程から歪曲・迂回させ、工程を順序とは異なる方法で進めることができます。
この非線形モデルを可能にすると考えられるのが、サプライチェーン全体との即時ネットワーク化によるデータの同時共有であり、それによって進化したジャスト・イン・タイムのように部品が調達されるシステムなのです。
結果として、私たち消費者は、カスタマイズ製品を安く手に入れられたり、最新の製品が入手しやすくなるような利便性が得られ、企業にとっては在庫のリスクが低減されることになるわけです。
加えて、この方法の延長線上にはすでに販売してしまった製品のプロセスを再生するリバースエンジニアリング(やり直し)をも念頭に置いています。これは、本企画の大きな枠組みとしての国連のSDGsとも関連した具体的な取り組みとして理解されます。
このように見ていくと、「インダストリー4.0」にはメリットがたくさんあるように思えます。
しかし、利便性の面だけにとらわれていると、その陰の面があることに気づきにくくなります。「インダストリー4.0」にも、確かに陰の面はあるのです。
次回は、「インダストリー4.0」の陰の面について解説します。
#1 「インダストリー4.0」とは?
#2 「インダストリー4.0」でなにが変わるの?
#3 「インダストリー4.0」によって疎外される人たちがいる?
#4 「インダストリー4.0」をより良い革命にするには?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。


