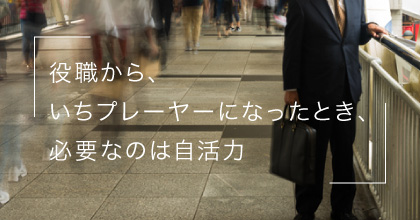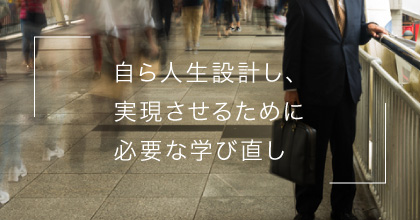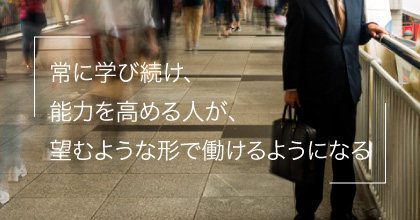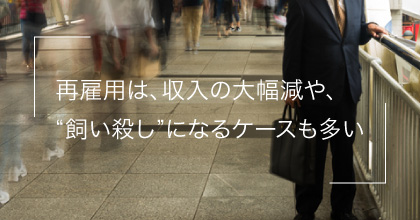
再雇用は、収入の大幅減や、“飼い殺し”になるケースも多い
希望すれば、原則として、誰でも65歳まで働けるようになりましたが、それで、みんなが満足しているかというと、そうでもないのが実情です。
まず、多くの会社が60歳定年制度は維持しており、一旦定年で退職した後、嘱託契約で再雇用という形をとります。すると、それまで課長や部長だった人も、いちプレーヤーになるわけです。
その場合、会社にもよりますが、能力があったとしても、再雇用後は雑務といわれるような仕事をするケースが多いです。職場によっては、元部長に雑務をお願いすることはできないと気を遣われ、なんの仕事も命じられないというケースもあります。
そのため、再雇用されたものの、65歳まで勤めず、途中退職する人が非常に多いのです。
また、嘱託契約になると収入が大幅に下がります。だいたい、ピーク時の3分の1ほどです。
しかも、近年では、55歳前後で役職定年がある会社が多く、例えば、役職のあるときは年収1千万円だった場合、55歳の役職定年で年収700万円くらいに下がり、これが60歳で再雇用になると、300万円くらいになるわけです。すると、55歳から65歳までの10年間の収入は5千万円で、年収500万円平均ということになります。
60歳を過ぎた人にとって、これは、若い頃と同じように満員電車で通勤してでも続けたいと思う収入であり、仕事といえるでしょうか。
一方、地方の中堅企業などの場合、役職に就いていて年収1千万円だった人が55歳で役職定年すると、だいたい年収600万円くらいに下がります。
しかし、地方は人手不足が厳しいこともあり、60歳以降もそのままの年収で、しかも、能力があれば年齢に関係なく、70歳くらいまで働き続けられることも珍しくありません。すると、55歳からの15年間で9千万円の収入が得られることになります。
このように、都市部の大企業に勤めていた人にとっては、地方の企業の方がより良い収入が得られたり、自分の能力を活かした仕事ができる機会があることは、定年後のライフプランを立てるうえで考慮するべきではないかと思います。
次回は、セカンドキャリアが上手くいった例を紹介します。
#1 なぜ、定年過ぎても働かなくてはいけないの?
#2 継続雇用でみんなハッピーなの?
#3 どうすれば再雇用に成功するの?
#4 能力があれば誰でも必ず活躍できる?
#5 社会人になっても勉強しなくてはダメ?
#6 高齢者も働きやすい社会になる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。