分野の違う研究者が「問い」をぶつけあうと、何が生まれる?
人と人との関係性。
そんな誰しもに関わる大きなテーマを中心に置いて、白熱した議論を3人の研究者たちが交わしました。
教育環境デザイン、脳科学、AIと法律といった、全く違った3つの視点。研究者同士がお互いに「問い」をぶつけあうと、どんな景色が見えてくるのでしょう?ゼミの学生に、高校生までを巻き込んだ、「問い」がぶつかる瞬間。新たな研究のタネが生まれる瞬間を、おたのしみください。
▼3人の研究者の関連動画を見てから、特別編を見るとより理解が深まります。
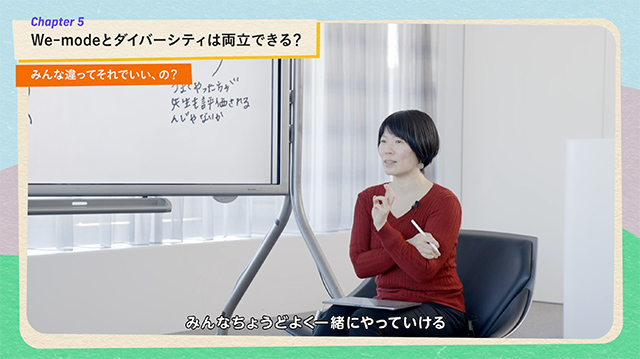 【教員プロフィール】
【教員プロフィール】
■岸 磨貴子(きし まきこ)
明治大学 国際日本学部 教授
誰もが自分の才能を発揮させられる学習環境をテーマに、多様性がつながる場のデザインを研究しています。ゼミでは学生と一緒に多文化共生の交流を積極的に行っており、国内外を駆け回るフィールドワーカーにしてバックパッカーという側面も。
<関連動画>場のデザイン×ICTで 誰もが輝ける世界に
 ■嶋田 総太郎(しまだ そうたろう)
■嶋田 総太郎(しまだ そうたろう)
明治大学 理工学部 教授
専門は認知脳科学。心が脳のどのような働きによって生み出されているのか、最新の計測装置を使って調べています。運動、感情、コミュニケーション、メディア認知などに着目し、脳のなかで自己と他者がどのように表象されているのかを研究しています。
<関連動画>“We-mode” で活性化する脳
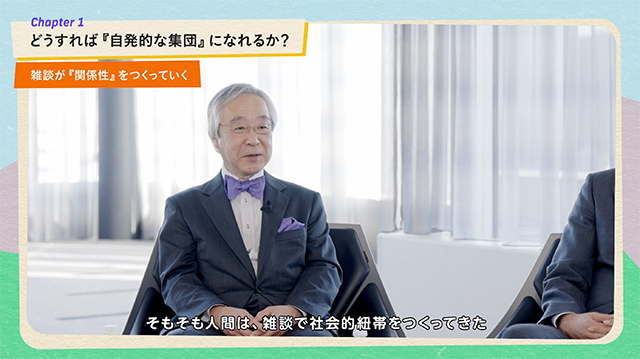 ■太田 勝造(おおた しょうぞう)
■太田 勝造(おおた しょうぞう)
明治大学 法学部 教授
専門は、社会科学の様々な方法・理論を用いて法律を検証する法社会学。裁判での事実認定や法的判断がいかになされるかといった事柄を、確率論、統計分析、経済学、脳科学などの知見を応用して考えています。AIによる法学へのアプローチも主要な研究テーマのひとつです。
<関連動画>想像できる?AIが裁判をする未来

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




