すべての当事者が社会を構想する
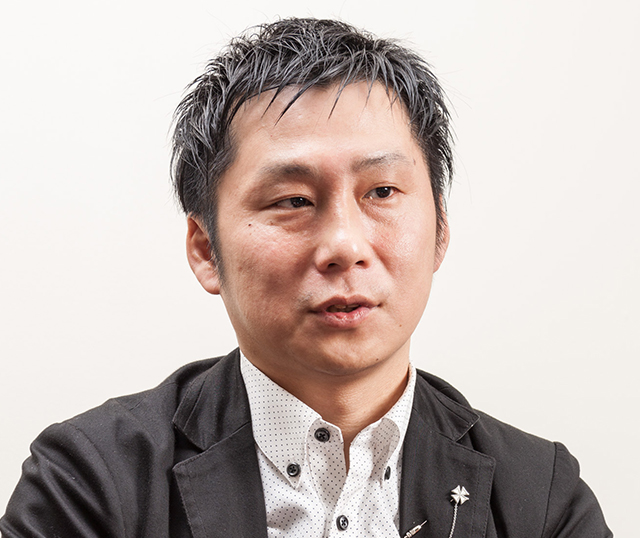 今の若い世代を見て感じるのは、誰かに認められたい、あるいは認められなければならないという、他者の承認を求める傾向が強いことだ。そのための有効なツールの一つとして、SNSも存在する。コミュニケーションの中で、無意識的に「自分が居てもいい」ことを確認し、承認を受ける作業が行われているのではないだろうか。そのような社会が健全とは言い難い。「居てもいいという承認を受けなくてもいい」社会であるべきだと考えている。
今の若い世代を見て感じるのは、誰かに認められたい、あるいは認められなければならないという、他者の承認を求める傾向が強いことだ。そのための有効なツールの一つとして、SNSも存在する。コミュニケーションの中で、無意識的に「自分が居てもいい」ことを確認し、承認を受ける作業が行われているのではないだろうか。そのような社会が健全とは言い難い。「居てもいいという承認を受けなくてもいい」社会であるべきだと考えている。
現代の社会では、組織というものに関与・所属することなしに社会生活を営むことは難しい。この組織の変遷・変質を追うことで、定義しがたい社会というものを捉えることが可能と考えている。社会とは少なくとも個人を超えた存在である。あらゆる当事者たちが個人という価値判断の基準とは別に、組織や社会といった価値判断の基準を意識しなければ、組織や社会は崩壊するだろう。
先に述べた、「個人になるということは、同時に社会の構成員としてその一部を引き受けること」という真意もそこにある。権力や知識を有する一部の人々が社会を構想するのではなく、すべての当事者(個人)が社会を構想していくことが求められている。
※掲載内容は2014年3月時点の情報です。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




