基礎研究を大切にすることで応用研究の成果も上がる
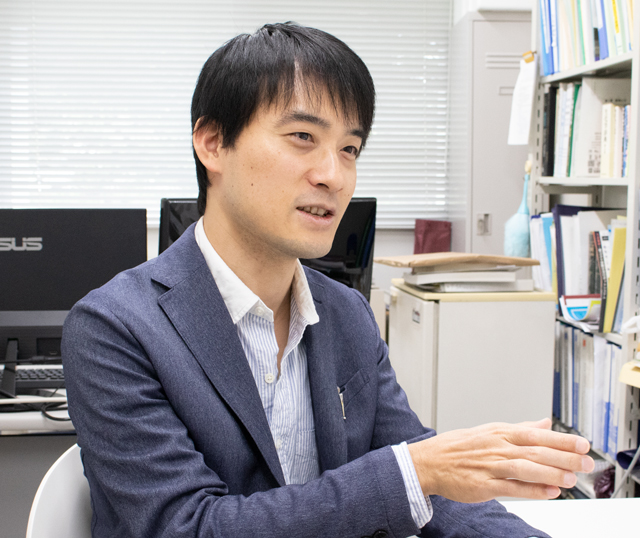 人が、人工的に遺伝子組み換えを行い、人にとって都合の良い作物を作っていくこと、それ自体は問題のあることではないと、私は考えています。問題なのは、目の前の利益に囚われて、自然界全体で起こりうることに目が向いていないことです。
人が、人工的に遺伝子組み換えを行い、人にとって都合の良い作物を作っていくこと、それ自体は問題のあることではないと、私は考えています。問題なのは、目の前の利益に囚われて、自然界全体で起こりうることに目が向いていないことです。
同様に、生命の全体像を理解せずに、特定の遺伝子だけを組み換えたり操作したりするだけでは、応用にも限界があります。それは、生命の基本的な仕組みの全体像が理解できていないからです。
例えば、ある遺伝子の関与する現象は、その生物の全体で起こっていることのほんの一部の局所で起きていることです。ところが生物の設計図であるゲノムはものすごい複雑なネットワークで繋がっていて、局所で起きたことが、思いもよらないところに影響を及ぼすような因果関係があるのです。
それを理解せずに遺伝子操作を行う事で生じる問題があります。これは、遺伝子組み換え技術だけでなく、ゲノム編集でも同様です。ゲノム編集はその生物の遺伝子に人が直接手を加えるので、他の生物の遺伝子を取り入れる遺伝子組み換えに比べて安全性が高いという認識がありますが、人が局所である遺伝子に手を加えたことで、様々な因果関係を通じて全体に出る影響については正確には理解されていません。
実際、中国で行われたと言われるゲノム編集ベイビーは、HIV感染のリスクを下げるために、DNAのある因子を外すことに成功したと言いますが、その因子を外したことで、インフルエンザのウイルスに感染しやすくなるのではないか、という指摘がされています。
いま、研究者たちは、目に見える結果を求められ、それに応えることを急ぐあまり、直接的な要因のみに囚われすぎています。
もちろん、応用研究は大事なのですが、遺伝子全体の仕組みやそのネットワークを理解する基礎研究も同様にとても重要なのです。
それは、リスク回避のためばかりではありません。例えば、作物を大きくするには、Aという直接的な因子に手を加えるだけでなく、全体の仕組みの解明から、BやCやDも関わっていることがわかれば、すべての因子に手を加えることで、より効果的に作物を大きくすることや、数を増やすこともできるようになるわけです。
基礎研究が大切であることは、近年、ノーベル賞を受賞された日本の科学者の方々が口をそろえて仰っていることです。時間はかかるものの、ことの本質に迫る基礎研究を、いま一度見直すべきだと強く思います。
そこに一定の研究成果が出るまで、遺伝子組み換えやゲノム編集の技術を私たちの生活に応用する事は、ある程度慎重であって良いのではないかと思います。
私は、主に大腸菌など微生物のゲノム制御の研究を行っています。それは、微生物は持っている遺伝子の総数も少なく、そこで起こる現象も、人に比べればシンプルで理解しやすいからです。
しかし、ブドウ糖を採り入れてエネルギーに変えたり、DNAをもとにタンパク質が作られるなど、基本的な仕組みはヒトを含めどんな細胞も同じです。
つまり、細胞の増殖や代謝といった生命の本質的な仕組みを理解するためには、それをシンプルに行っている微生物を研究することは、最も適していると言えます。
本質的な応用をするには、遺伝子全体を利用する仕組みを解明し、理解しなければなりません。
そこで、微生物の仕組みを解明することから始めるのが、有効なアプローチになると考えています。終局的にはひとつの生物のゲノム制御の全体像を理解したいと思っております。その知見は、ヒトを含め、動物、植物など、生物のもつ遺伝子全体の仕組みやネットワークの理解に役立つと考えております。
生物がもつ遺伝子の機能の因果関係、すなわちゲノムネットワークを理解したときに、遺伝子組み換え技術やゲノム編集による、本当に自由自在な応用が可能となるのではないでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




