人工骨の開発技術が再生医療の進歩に繋がる
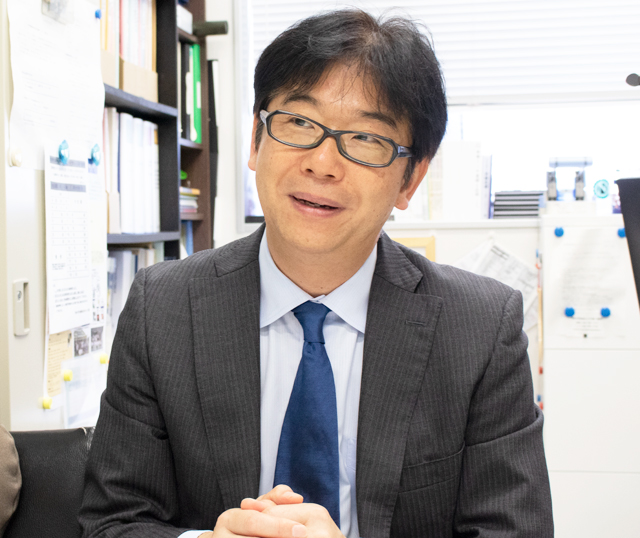 近年、「再生医療」が注目されています。多くの研究者が様々な形でアプローチしていますが、私たちの研究室でも、独自の観点から研究を行っています。
近年、「再生医療」が注目されています。多くの研究者が様々な形でアプローチしていますが、私たちの研究室でも、独自の観点から研究を行っています。
再生医療とは、人体の組織になんらかの障害が起こったとき、その組織に培養した細胞を移植し、再生を図る医療ですが、私たちの研究室でも、骨芽細胞を培養して骨のような組織をつくることができます。
ここで重要なのは、実は、細胞を培養する「足場」(スキャフォルド)なのです。
そこで、私たちが行っているのは、まず、アパタイトのファイバー(繊維状)をつくり、そこにビーズ状のカーボンを混ぜて焼き、「アパタイトファイバースキャフォルド」と言うアパタイトファイバーの多孔体をつくります。
次に、バイオリアクターという装置を使い、このアパタイトファイバースキャフォルドに細胞を付着させると、そこが細胞培養の「足場」となるのです。この手法による細胞培養を三次元循環培養と言います。
例えば、ラットの骨から骨髄を採り、そこから間葉系幹細胞を採取します。間葉系幹細胞とは組織への分化能をもつ体性幹細胞なので、これを使って三次元循環培養を行い、骨芽細胞に向かわせると、「再生培養骨(骨のようなモノ)」ができます。これを自家骨の代わりにします。
現在はラットを使った実験の段階ですが、ほぼ成功するレベルにきています。
この、細胞培養の「足場」をつくる研究は、人工骨の開発にとどまらず、あらゆる細胞培養に応用できます。すなわち、再生医療技術の基盤になる可能性があるのです。
例えば、最近では、細胞培養によって人のミニ肝臓をつくることに成功していますが、その組織は、大きさにして1mm程度です。これを実際の治療に使おうとすれば、何百万個も必要になります。
そのとき必要なのは、効率性の高い細胞培養技術であり、その基礎となるのが、いま、私たちが行っている細胞培養の「足場」であると考えています。
すなわち、臨床応用可能な大きさをもつ組織をつくることが可能になってくるのです。そこも、私たちの目指しているところです。
いま、人生100年時代と言われるようになっていますが、大切なのは、「健康寿命の延伸」です。そのために、多くの研究者たちが、日々、研究を続けています。
その成果を実用化していくためには、基礎研究への理解や、そこに予算をつけてもらうこと、さらに医工連携や産学協働など、様々な取り組みが必要になります。
多くの皆さんに、こうした研究に関心を寄せてもらい、期待してもらうことが、その取り組みをスムーズに進ませることにも繋がります。
そのために、私たちも情報発信を進めていきますので、皆さんも、ぜひ、そうした情報に関心を寄せてもらいたいと思っています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




