インドネシアの気候変動について支援するプロジェクトが進行
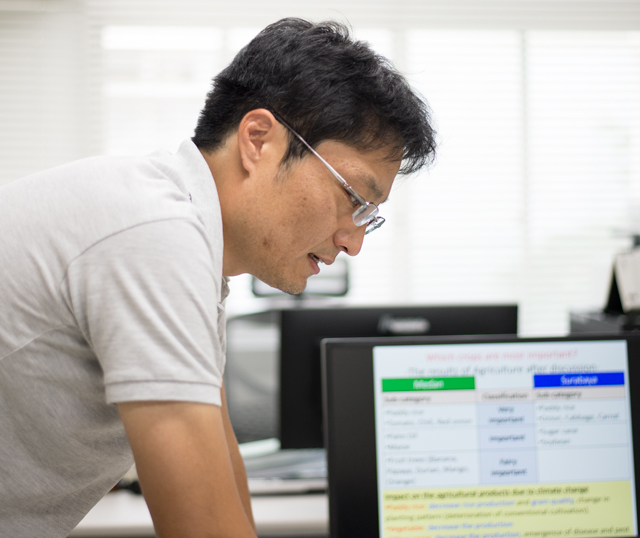 インドネシアは東南アジア諸国の中では最も人口が多く、国土も広く島嶼も多いことから気候変動の影響を受けやすいといわれています。一方、インドネシアは急速に経済発展をしており、国土整備、都市整備などが進んでいます。その開発のなかに気候変動に関する適応策や緩和策を考慮することが求められていますが、十分な対応ができていないのが現状です。こうした経緯もあり、私は、インドネシアの気候変動について支援するプロジェクトの中で、稲作における適応策の開発プロジェクトに加わっています。インドネシア人も米が主食で、年間1人あたり120~160kgを消費しています。53kgほどの日本の約3倍にもなります。また、稲作面積は日本の150万ヘクタールに対して、約1300万ヘクタールあります。これだけの面積があれば、生産量が十分にあると思われますが、人口増加によって米が不足する、気候変動が原因で米の生産量が伸びないなどの状況もあり、インドネシアは米を輸入することもあります。現在でもすでに、米生産には様々な問題が生じているのですが、プロジェクトでは、将来の米の生産量を確保するために(食糧を確保するために)、気候変動が稲作に及ぼす影響評価、つまり、将来、米の収量や品質がどうなるのかについて解析し、その結果に基づき、インドネシア側に適応策を提案し、その適応策をインドネシアの開発計画に主流化することを目的としています。これまでに、インドネシアの農村を訪問し、老齢の農家に話を聞くと、子供の頃は定期的にスコールがあったのに、最近は不順で、水の利用がしづらく、農作物の管理がやりづらくなっていると言います。しかし、そう言いながらも、気候変動による危機感はあまり高くないです。極端な例かもしれませんが、インドネシアでは伝統的な米の在来品種は非常に大切に栽培されていますが、それはお祭りや儀式のお供え物に使われるものです。もし、将来、気候変動によって、在来品種が栽培できなくなった場合、その地域の伝統的な風習・文化が廃れる可能性もあるのかもしれません。このような事態を避けるためにも、将来のインドネシアの稲作に対して有用な適応策を検討し、備えておくことは重要です。
インドネシアは東南アジア諸国の中では最も人口が多く、国土も広く島嶼も多いことから気候変動の影響を受けやすいといわれています。一方、インドネシアは急速に経済発展をしており、国土整備、都市整備などが進んでいます。その開発のなかに気候変動に関する適応策や緩和策を考慮することが求められていますが、十分な対応ができていないのが現状です。こうした経緯もあり、私は、インドネシアの気候変動について支援するプロジェクトの中で、稲作における適応策の開発プロジェクトに加わっています。インドネシア人も米が主食で、年間1人あたり120~160kgを消費しています。53kgほどの日本の約3倍にもなります。また、稲作面積は日本の150万ヘクタールに対して、約1300万ヘクタールあります。これだけの面積があれば、生産量が十分にあると思われますが、人口増加によって米が不足する、気候変動が原因で米の生産量が伸びないなどの状況もあり、インドネシアは米を輸入することもあります。現在でもすでに、米生産には様々な問題が生じているのですが、プロジェクトでは、将来の米の生産量を確保するために(食糧を確保するために)、気候変動が稲作に及ぼす影響評価、つまり、将来、米の収量や品質がどうなるのかについて解析し、その結果に基づき、インドネシア側に適応策を提案し、その適応策をインドネシアの開発計画に主流化することを目的としています。これまでに、インドネシアの農村を訪問し、老齢の農家に話を聞くと、子供の頃は定期的にスコールがあったのに、最近は不順で、水の利用がしづらく、農作物の管理がやりづらくなっていると言います。しかし、そう言いながらも、気候変動による危機感はあまり高くないです。極端な例かもしれませんが、インドネシアでは伝統的な米の在来品種は非常に大切に栽培されていますが、それはお祭りや儀式のお供え物に使われるものです。もし、将来、気候変動によって、在来品種が栽培できなくなった場合、その地域の伝統的な風習・文化が廃れる可能性もあるのかもしれません。このような事態を避けるためにも、将来のインドネシアの稲作に対して有用な適応策を検討し、備えておくことは重要です。
一方で世界のグローバル化は進んでおり、農産物も例外ではありません。様々な農産物を輸入したり輸出することは、国の経済にも関わったり、重要な食料の安定供給にも関わっているのです。どこかの国や地域で、特定の農産物が大凶作となると、その影響は数珠つなぎの連鎖となり、世界中がパニックになりかねません。実際、2006年にはオーストラリアで干ばつにより小麦が、2009年にはインドで干ばつにより米が非常な不作となり、緊急輸入などが行われました。日本は食料自給率が先進国の中でも特に低く、38%です。世界のどこかで農作物が大凶作になることは、他人事ではないのです。また、世界には食料が足らずに栄養不足になっている人が約8億人いるといわれます。こうした状況を改善していくためには、その国の文化やライフスタイルを認めつつも、気候変動に対する日本の優秀な適応策の技術を提供していくことは、非常に重要だと考えています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




