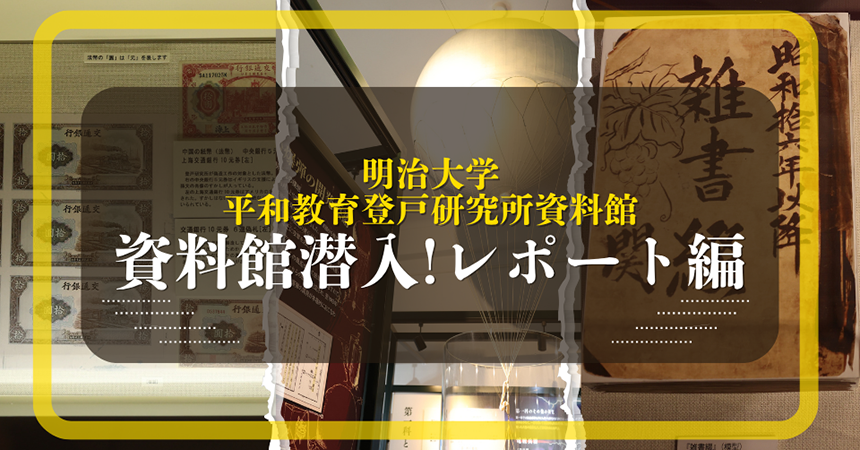【戦後80年】秘密戦を語り継ぐ“明治大学平和教育登戸研究所資料館”で戦争の真実をたどる〈インタビュー編〉
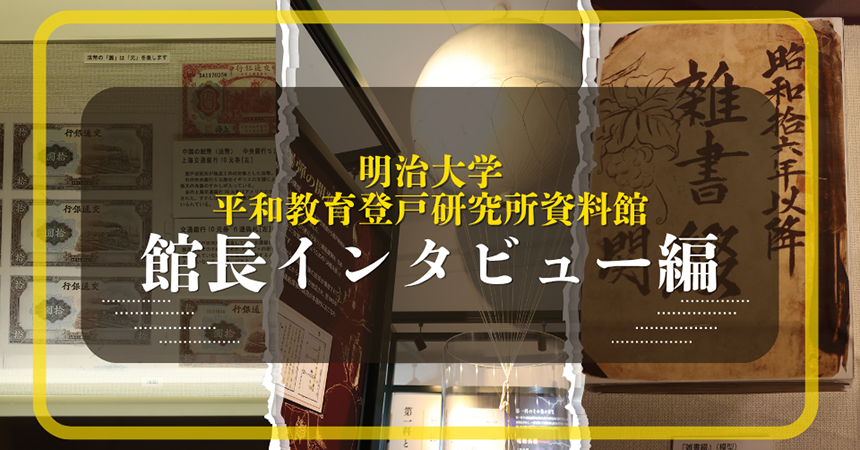
登戸研究所が実在していた場所にキャンパスがあるというのも大きい
――2025年は戦後80年という節目でもあります。
山田:テレビ番組などでも特集が多く組まれていますね。戦争が終わったときに10歳だった方は、今では90歳です。そして90歳以上の方の割合は、総務省統計局のデータでは総人口のわずか2.7% (2023年10月時点)。当然、今後も減る一方です。いくら日本が長寿社会とはいえ、いずれは戦争を経験された方が一人もいなくなる時代が来てしまいます。だからこそ、この世代から聞けることは必ず聞き、それをつないでいくことが重要です。
また、マスコミも当事者から話を聞くことには一生懸命ですが、次の世代への聞き取りはまだまだです。だけど両親や祖父母がこんなことを言っていた、というのも大事な情報です。さまざまな形で記憶の断片をつなぎ合わせていく作業も、これからはもっと大事になってくるでしょう。
そして図書館や資料館といった場は、これら記憶の受け皿となり得ます。登戸研究所資料館も、記憶のバトンを継承する施設として、あるいはいろんな情報がクロスする中継地点として、皆さんに使っていただくことも意識して組織していかないといけないなと思っています。
――若い世代につないでいくという面でも、大学にある意味が大きいですね。
山田:過去の歴史と現代のことを往来しながら学ぶ「登戸研究所から考える戦争と平和」という全学共通総合講座の授業を、私を含む3人の教員で受け持っているのですが、過去からヒントを得て現代の問題を追究する学生もおり興味深いです。たとえば登戸研究所の歴史をパレスチナやウクライナの問題を照らし合わせると、そこから見えてくるものがあります。逆に近年問題視されているPTSDを抱えた人は昔の戦争でもいたでしょうし、彼らが戦場から戻ってきてどうなったのかを課題にする学生もいます。自分たちの学んでいるこの場に歴史が遺されていることで、戦争への実感も増しているようです。
登戸研究所が実在していた場所にキャンパスがあるというのも大きいんですよね。呼びかけたらボランティアに来てくれる学生もいます。来館者には年配の方も多いのですが、若い人に説明してもらって嬉しかったという感想も多くいただきます。「次の世代に継承されている」と受け取ってくださるんでしょう。
――多くの人にとって、貴重なきっかけをつくっている場でもありますね。
山田:毎年の企画展を楽しみにしてくださっている方も、多くいらっしゃいます。とても小さな資料館ですが、大きな存在感は示せているんじゃないでしょうか。
親族から戦争の話を聴くことも、今では非常に少なくなってきています。戦争とのつながりが希薄になるなか、ここは場所として戦争の時代と今がつながっている。80年も前の話になると、教科書の中に存在している別世界の出来事のように感じてしまいがちですが、戦争は自分から切り離されたものではありません。
時間が経てば経つほど、記憶は歪んだり美化されたり消されたりしがちです。だけど戦争の本当の姿が誰にでもわかるように、包み隠さずに提示していくのが、この資料館の使命です。わざわざ大学が資料館を持っていることの意義は、そこにあると思っています。
◆学生スタッフの声より深く知るにつれ、「語り継がなければ」という思いも増していく

学生ボランティア 河原 環さん[明治大学 理工学部 応用化学科 1年生]
来館者の方にパンフレットをお渡ししたり、ご要望があれば館内のガイドをしたり、裏手の弾薬庫を見学したいという方がいらっしゃったら案内したり、イベントのお手伝いをしたりしています。ご遺族から提供いただいた資料の整理なども行っています。
地元が調布なので、調布飛行場など戦争に関するものが身近に多くありました。また、祖父は戦争を経験しており、現在「こどもの国」になっている弾薬庫に爆弾を運び込む仕事をしていたと父から聞いています。こういった環境に育ったこともあり、同世代のなかでは戦争に対して関心が高いほうだと思います。資料館へは入学後、何気なく訪れて衝撃を受けました。その後、山田先生の授業でボランティアの募集があり、週に1回参加しています。
ボランティアを始めてからは、戦争を経験された方から当時のお話を伺う機会も増えました。戦争について詳しくなるにつれ、「知ったからには語り継がなければ」という気持ちが増してきています。この資料館は、戦争について受発信するプラットホームでもあるのだと感じています。
戦後80年が経ち、このまま忘れ去られてしまうのは怖いことだと思います。あくまでも語り部はニュートラルな存在ですから、私見は持ち込まず、情報・歴史を伝えるのが自分の役割だと意識しています。「若い人が知って案内してくれるのが嬉しい」「若い人に語り継いでほしい」というお声も頂戴できていてありがたいです。
僕自身、応用化学を専攻しているので、毒物や細菌は今後、自分が研究することに近い内容でもあります。「知識の使い方は気をつけなければならない」という思いも強まり、貴重な戦争遺跡が学びの場にあることに感謝しています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。