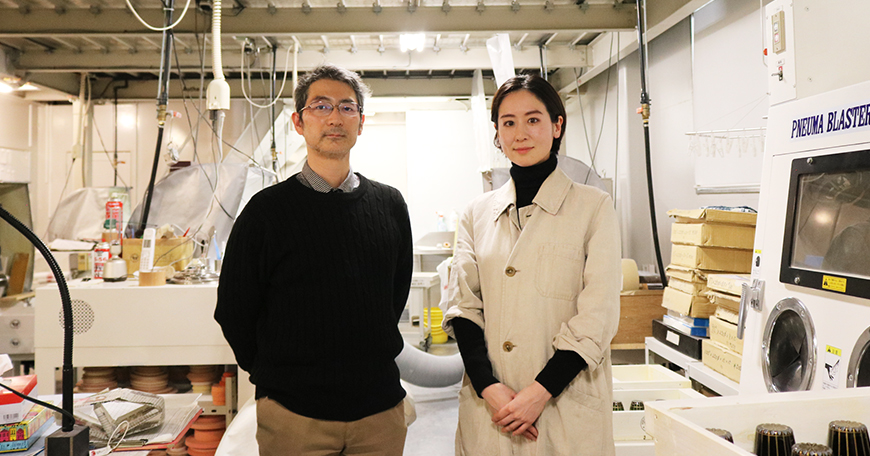ボルボ・カー・ジャパンのトップと語る 自動車業界の未来とブランディングの重要性

日本の産業をリードしてきた自動車業界が近年、グローバル化という大きなうねりの中で目まぐるしい変貌を遂げています。これまで優れた技術で世界をリードしてきた日本の自動車業界ですが、高性能の「モノづくり」だけでは勝ち残れないという岐路に立たされています。
そこで、グローバル戦略で重要視される「ブランド」が、日本の自動車業界でより醸成されていくことが必要なのかもしれません。この「ブランド」をテーマに、日本での留学経験を持ち、世界と日本を知るボルボ・カー・ジャパンCEO マーティン・パーソン氏と、グローバル・ブランド管理を専門として、長きにわたり自動車業界を研究対象としてきた原田将教授が対談。
あらゆる業界に共通する「ブランディング」構築の難しさ、自動車業界のコスト高を跳ね返す方策、サスティナビリティとブランドの考え方、リテールセールスの大きな変化、グローバルなマインドセットの重要性など、話は多岐にわたり、興味の尽きない対談が展開されました。
Martin Persson(マーティン・パーソン)
ボルボ・カー・ジャパン代表取締役社長(CEO)。スウェーデン出身。明治大学経営学部へ留学経験あり。
原田 将
明治大学 経営学部 教授。グローバル・ブランド管理、ブランド価値経営が専門。自動車業界も研究。

マーケティングの仕事が好きなパーソン社長と、自動車業界のマーケティングを研究している原田教授。すぐにマーケティングやブランドの話に火がついた
「ブランド」は、コスト高を跳ね返す力にもなる
原田:世界的な自動車メーカーのボルボ・カーズの日本法人、ボルボ・カー・ジャパンの代表のお話をお聞きできると楽しみにしていました。よろしくお願いいたします。
まず、国際的に自動車業界は今、変革期と言われていますが、パーソン社長はどのような変化が起きていると思われますか?
パーソン:自動車メーカーが成長を続けるためには、ガソリン車など今後縮小する事業ではなく、EV(電気自動車)やオンライン・セールスなど収益性が高まる事業にシフトしなければなりません。今、その転換点だと感じています。
原田:EVにシフトするという点で、自動車の開発費や製造費が上昇し、コスト高になっていますね。
パーソン:そのとおりです。自動車メーカーはコスト削減の努力を強いられているわけですが、それには限界がありますからコスト高を乗り越える戦略が必要です。
原田:その戦略のカギは何だとお考えですか?
パーソン:コスト高の問題を跳ね返すグローバル戦略の一つが「強力なブランド」だと考えています。
原田:私も、まさに「ブランド」が鍵の一つだと考えています。自動車メーカーに限らず、グローバル・マーケティングにおいて非常に重要な戦略ですね。
しかし、海外の企業に比べて日本の企業はブランディングに少し消極的なのでは?
パーソン:それは感じます。日本のメーカーは“技術”に焦点を当て過ぎなのかもしれません。新車がドーン!と登場して「さあ、試乗して、技術に驚いて!」みたいなね。
原田:確かに、「ブランド」より商品の機能にフォーカスする傾向があるように感じます。
パーソン:自動車はメカですから先進的な技術はもちろん重要です。しかし、それとともに「強力なブランド」を持つことが大事ですね。日本企業が今よりも「ブランド」に目を向けたらグローバル・マーケティングがより面白くなりそうです。

パーソン社長は明治大学経営学部留学後、スウェーデンの大学院の修士課程を修了し、日本からキャリアをスタートさせた。スウェーデンのボルボ本社、中国やロシアでの活躍を経て2020年に再来日
ボルボ自体がサスティナブル、という強力な「ブランド」
原田:ボルボはブランディングに成功している企業ですが、「ブランド」の重要なファクターは何だと思われますか?
パーソン:“エモーショナルな部分”が重要だと思っています。
原田:私もそう思います。ボルボのブランドは“エモーショナル”で、それが世界に通用する強みですね。
現在のボルボの「ブランド・コンセプト」を教えていただけますか?
パーソン:ボルボには「Freedom to Move」というプランディング・プロミスがあり、その3つのキーワードが「セーフティ」、「サスティナビリティ」、「パーソナル」です。
「セーフティ」つまり安全性は我が社のコアで、大きな強みです。
原田:安全性のイメージはボルボにとって非常に強力ですね。約60年前に3点式シートベルトを生み出したメーカーですから。
パーソン:よくご存知ですね。
そして「サスティナビリティ」は持続可能性、まさに未来に必要な思考であり、今、ボルボの最も優位性の高いところだと考えています。
原田:2050年のカーボンニュートラルを目指して、グローバル企業のほとんどが「サスティナブル」を表明しています。その中でも「サスティナビリティ」に高い優位性があると考えているのはなぜですか?
パーソン:今、どこの企業も「サスティナブル」をうたっています。しかし、本質的にSDGsを理解した上で「サスティナブル」と言っているのでしょうか?
原田:確かに、それは分かりづらいですね。
パーソン:ボルボは伝統的に「サスティナビリティ」であり、それを言うだけでなく「必ず実行する」企業です。そして、全モデルを電動化にした最初のブランドです。
原田:真に、ブランド・プロミスを実行しているわけですね。
パーソン:EVの C40のフロアカーペットはペットボトルの再利用によって作られます。また、数年前から紙のカタログを全廃しました。
つまり、ボルボを選ぶこと自体が「サスティナブル」なのです。
原田:それは本当の「サスティナブル」であり、まさに優位性の高い「ブランド」ですね。
パーソン:はい。そして、第3のブランド・プロミスである「パーソナル」は一人ひとりの顧客に適応させ、ユニークな体験をもたらすことです。
原田:確かに、「ボルボ車とともにあれば、どんなライフスタイルを描けるか」みたいな“エモーショナルな面”やボルボと顧客の“絆”とか、そういうところにも焦点を当ててブランディングしていますね?
パーソン:そうです。“エモーショナル”を含むソフトバリューに注力しています。
原田:“一人ひとりの顧客にふさわしい体験”というのは、昨今の消費者動向から見ても重要なポイントだと思います。
パーソン:ボルボは高級車メーカーなので、ブランドと顧客満足度を何よりも重視しているのです。
原田:さらに、スウェーデン発のデザイン力というか、優れたデザイン性もボルボの優位性だと感じています。
パーソン:ありがとうございます。あらゆる企業が、ブランドの“エモーショナルな面”や“メーカーとの絆”などのソフトバリュー面にもう少し目を向けてくると、グローバル戦略の中の「ブランド」の価値がもっと高まるでしょうね。
グローバル戦略で、日本企業のプレゼンスは再浮上する
原田:そういえば新型コロナウイルスの影響で、世界的に自動車の需要が減少していたにもかかわらず、ボルボのセールスが伸びていました。
今、パーソン社長のお話をお聞きしながら、ボルボの「強力なブランド」が下支えしているのかなと感じましたが、いかがでしょうか?
パーソン:もちろん、「ブランド」も一役買っていたはずですよ。
セールスの話をすると、2020年の第4半期には需要は戻っていました。現在の課題は半導体の入手です。でも、日本のお客様は車を手に入れることができています。これはボルボ本社が日本市場を信頼し、優先していることの証なのです。
原田:なるほど、半導体の問題もコスト高に影響していますね。
ところで、世界的に自動車業界への異業種参入が増えています。これは「業界を大きく変革するのではないか?」と感じています。以前はトップにメーカーがあって、その下にサプライヤー、セカンドティア、サードティアといったサプライがあったわけですが、そういう階層も変わっていくのではないでしょうか?
パーソン:消費者は異業種からの参入であろうと関係なく「その車を選ぶ」。選ばれるためには、やはり「ブランド」が重要になる、ということです。
ところで、原田教授は自動車メーカーのマーケティングも研究されていて、以前、ボルボ・カー・ジャパンも調査してくださったとか。
なぜ、自動車メーカーのマーケティングに興味を持ったのですか?
原田:1980年代や1990年代,海外に行くと日本企業のブランドであふれていました。その頃、欧米では「トヨタ車やホンダ車がバンバン走っていて、TVならパナソニック製、ソニー製だ!」という感じで。
パーソン:その頃、日本企業のプレゼンスはすごかったですから。
原田:しかし、今は「ヒュンダイ、キア、サムスン、LG…」と状況は一変しています。
「日本企業のプレゼンスは、なぜ、弱まってしまったのだろうか?」
そう感じたことが興味を持った理由です。
パーソン:それを聞いて思い出しました。日本企業のプレゼンスにも関わりますが、一つ不思議に思っていることがあるのです。
「なぜ、日本の自動車メーカーは世界的なEV化のリーダーにならなかったのか?」
プラグインハイブリッドカーを最初に作ったのは日本ですからね。
原田:確かに。日本企業はグローバルな動向より日本市場の方を向いていたのかもしれません。
パーソン:そうですね、特に以前は「日本市場は特別、日本市場はユニーク」という意識が感じられました。
日本のマーケットが大きかった頃は、特別でユニークな日本市場に合わせていれば良かったのでしょうが。
原田:日本の自動車マーケットは今500万台を割り、中国やアメリカ市場がどんどん拡大しています。今はグローバル戦略を展開しなければいけませんね。
パーソン:実は、ボルボのマネジメント仲間も「日本の市場は今だって特別だ。日本でデジタル化やオンラインセールスは無理だと思うよ」と言っていました。
でも私は、日本を知っているからこそ「日本は特別な国じゃない、他の国と同じだよ」と確信しています。グローバル戦略に転換しきっていないだけなのです。
注)プラグインハイブリッドカー(PHEV):ハイブリッドカーの電池容量を拡大しに外部充電機能を加え、電気だけでの走行距離を伸ばしたエコカー

パーソン社長は「日本の自動車のCMは芸能人の起用が多いと感じる。他国では、企業自体のブランドを打ち出す戦略がほとんどだと思う」と話す
今、誰にとっても必要「グローバルなマインドセット」
パーソン:2020年に来日した私のミッションは「ボルボのグローバル戦略を日本に根付かせること」。ボルボのグローバル戦略もしっかり理解し、日本についても熟知している私だからできると信じていて、今、挑戦しているところです。
原田:そのミッションを達成するために、何が必要だとお考えですか?
パーソン:グローバルなマインドセットです。
原田:なるほど。グローバルなマインドセットについては、実際、国際ビジネス研究などでも大きなテーマになっています。
しかし、どうすれば「マインドセットを変えられる」のでしょうか?
パーソン:それは私たち経営陣が社員に「ほら、できるじゃないか。トライし続けよう」と見本を示すことです。そして、「失敗しても大丈夫」と言い続けることでしょうね。
原田:確かに日本人は失敗を避けよう、リスクを最小限に抑えようとしがちです。
パーソン:いつも社員に「何もしないより、何かを試みて失敗してくれる方がいいんだ」と言っていますよ。「挑戦」が大事です。
原田:挑戦して、失敗するのはOKですか?
パーソン:もちろんです。そこでペナルティが生じるとイノベーティブにならないでしょう?
リスクを抑え込もうとすると、ビジネスの速度が遅くなるという弱点が出てくると思うのです。
原田:確かに、多少のリスク覚悟で、テック企業のアジャイル開発のようにやっていかないとグローバルから遅れをとってしまいますね。
注)アジャイル開発:スピーディーにソフトウェアなどをリリースするために適した開発手法

「私の仕事は『挑戦すること』。挑戦しない言い訳を考えてはいけない。ボルボのグローバル戦略を日本に根付かせてみせますよ」と語るパーソン社長
短期間のアップデート、それが産業界で起きていること
パーソン:そう、ビジネスの世界で“遅れ”は大きな弱点になります。
今、自動車の開発現場ではほとんどがソフトウェアの開発にシフトし、つまり、原田教授が言ったようにアジャイル開発になっているのです。
ボルボはだいたい3カ月でソフトウェアパッケージなどをアップデートしているんです。
それをOTA(Over The Air)といってネットを通じて無線アップデートを進めています。
原田:たった3カ月ですか?
パーソン:はい。スピードが求められる時代です。
原田:それは、ネットに繋がっているからできることなのですか?
パーソン:厳密に言うと各国のネットに関する法律が違うので、全てを実行できない国もあります。日本はまだ実施できませんが、そこは織り込みながら開発しています。
原田:近い将来的には、どの国でも実施できるのでしょうね?
パーソン:はい。自動車もiPhoneみたいにネット上から新しいソフトウェアが入るようになりますよ。
原田:それは全てのボルボの車で可能なのですか?
パーソン:はい、全ての車で可能です。現にボルボではEV以外にも対応しています。
全てOTAでできるようになるとビジネスモデルが変化するでしょう。例えば、サブスクリプションしたい車をOTAで取得して支払う……、そういうビジネスになっていく。
原田:“挑戦的な”ソフトウェアのアジャイル開発がなおさら重視されるわけですね。
注)OTA(Over The Air):無線通信によるデータ送受信を活用して、車載コンピュータのソフトウェアをアップデートする手法

「以前、ボルボのショールームを訪れた時、スタッフの皆さんの『顧客の気持ちを洞察し、捉えようとする姿勢』に感銘を受けた」と原田教授
オンライン化が「ブランド」重視に拍車をかける
原田:先ほどパーソン社長が話されていたとおり、ボルボ・カー・ジャパンはグローバル戦略の一つとしてEVのオンライン販売を始めましたね。
パーソン:はい。昨年、EVのオンライン販売とサブスクリプション販売を開始しました。難しいトライでしたが、非常にやりがいと手応えがありました。
原田:着実にボルボのグローバル戦略を日本に根付かせているんですね。
そういう中で、リテールセールスの現場で何か大きな変化はありますか?
パーソン:大きな動きとしては、オンライン販売が今後ますます拡大するはずなので、そうすると顧客と商談をする従来的なセールスパーソンは減り、オンライン販売をサポートする人材が増加するでしょう。
原田:O to O(Online to Offline)、つまりオンラインとオフラインをスムーズに橋渡しできる人材みたいな?
パーソン:そうです。オンライン販売を始めた時にコールセンターを設置しました。以前はセールスパーソンが行っていた顧客とのハンドリングを、今はコールセンターのスタッフが担っています。
原田:車を買う前に、ディーラーへ行く回数が減りますね。
パーソン:以前、顧客は車を買う前に3、4回いらしていましたが、今は1回程度に減りました。疑問点や知りたいことにはコールセンターが幅広い時間帯で年中無休で対応しますから、顧客はいつでも自由な時間に、ソファに寝転がりながら車選びができますよ。
しかし、納車やアフターサービスは当然オフラインですから、O to Oが加速していくのではないでしょうか。
原田:ディーラーへ行かない、セールスパーソンと商談する必要がないなら、なおさら「ブランド」が重要になりますね。車を買う時「どのブランドにしようかな?」と。
パーソン:おっしゃるとおりです。今や誰でもインターネットでスペックなど機能を調べられますから、そこを説明する必要はなくなっています。
原田:リテールセールスの現場でも「ブランド」がますます重要に?
パーソン:今、顧客が一番知りたいと思っているのは「ブランド」だと思います。
「ボルボ・ブランドは他社とどこが違うのか?」と。だから優位性の高い「ブランド」を世に伝える必要があるのです。
サスティナビリティとEVのリーダーを目指して
原田:では最後に、ボルボ・カー・ジャパンのビジョンをお聞かせいただけますか?
パーソン:サスティナビリティとEVのリーダーになりたいですね。
間もなく、日本でEV化が加速するだろうと私は確信しています。その中で、ボルボ・カー・ジャパンがリーダー的な存在になることを目指しています。
原田:なるほど、それもグローバル戦略からの視点ですね。
パーソン:EVのリーダーであること自体も「ブランド」になります。
原田:まさに、「ブランド」が重要ですね。
本日は、たくさんの興味深いお話をありがとうございました。

私たちも、社員や学生に対してアジャイル開発のように「トライ、トライ、トライ」だ。それが「若い人に魅力を感じてもらう」鍵なのだから
対談を終えて
パーソン:自動車業界についての知見があり、アカデミックな見地を持つ研究者の原田先生との対談には、とても興味深い視点がいくつもありました。
原田:リーディング・ブランドであるボルボ、ボルボ・カー・ジャパンの代表から、現在の取り組みや考え方をお聞きできたことは、私の研究にとっても非常にプラスとなりました。
Profile
Martin Persson(マーティン・パーソン)
ボルボ・カー・ジャパン代表取締役社長(CEO)。スウェーデン出身。大学院時代、明治大学へ留学。1999年 ボルボ・カー・ジャパンの前身である、ボルボ・ジャパンに現地採用社員として入社。2008年 本社採用となりスウェーデンに異動。グローバルCRMの責任者となる。ロシア、中国でカスタマーサービスの責任者を経て、2019年 ボルボ・カー・ロシアの社長に就任。2020年 ボルボ・カー・ジャパンCEOとして再来日、ボルボのグローバル戦略を日本で展開中。
原田 将(ハラダ・ススム)
明治大学 経営学部 教授。明治大学大学院 経営学研究科 博士課程修了 博士(経営学)。2012年 The University of York(UK)The Centre for Evolution of Global Business and Institutions Visiting Fellow、2015年 兵庫県立大学経営学部 教授を経て、2017年 明治大学 経営学部で教鞭を執り、2018年より教授。専門分野はグローバル・ブランド管理、ブランド価値経営など。日本流通学会(副会長、理事)、多国籍企業学会(理事)、国際ビジネス研究学会(幹事)などに所属。著書に『ブランド管理論』(白桃書房刊)がある。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。