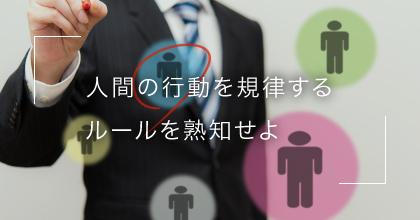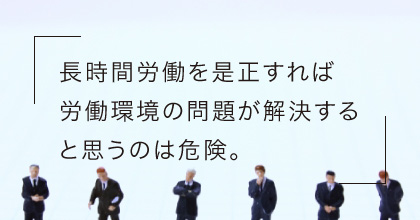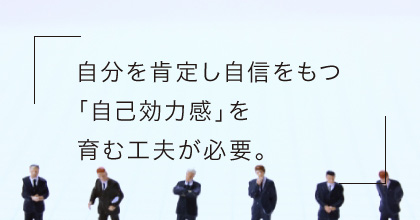人生のターニングポイントアメリカで学んだ現実主義と戦争の緊張感
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【37】
私のターニングポイントは、アメリカへの大学留学と米国国立公文書館での史料調査です。
アメリカ留学では、米国流の現実主義の理論を学べただけでなく、外側から日本を見る機会となったのが大きかったですね。
私は1958年生まれで、学生の頃にはまだ、世の中に左翼的運動の勢いが残っていました。大学の先輩からは『毛主席語録』を貰ったりしましたし、若者同士で集まると「日本は非武装中立を貫くべきだ!」と論じたりもしました。
ですが、いざアメリカに渡って国際関係論や安全保障問題を勉強しはじめると、ある種の理念や思想はなかなか通用しそうにないなと感じるようになりました。
たとえば、アメリカにおける外交は、政治家が外遊して重要人物と歓談したり、国際パーティで挨拶したりするといった、日本人が想像しがちな交渉だけの「外交」とはタイプが異なります。
専門用語でcoercion(強制)とかcoercive diplomacy(強制外交)と言いますが、つまるところ、相手を実力で脅かしながら交渉し、自分に有利な結論を導くのが、ひとつのアメリカ流の外交なのです。
それはある部分では自分勝手にも思えるのですが、同時に、交渉には軍事力や経済力など力の要素が必要であるという基本を痛感させられた部分もありました。
私がアメリカにいた1990年の8月、イラクがクウェートを侵攻しました。そして翌年1月には湾岸戦争が始まりました。
新聞やテレビでは、米軍の空母を何隻送るとか、どれだけの軍隊を派遣するかといった情報が、次から次へと報じられます。アメリカ社会の空気が張り詰めていくのが、肌で感じられました。
私にとってそれは、日本ではまるで経験したことのない緊張感でした。日本が考える平和主義と、世界的な常識としての平和主義には、明らかなズレがあるのだと実感しました。
ある場面では、どうしても軍事力に対する配慮が必要になる。その気づきは、研究分野への理解を深めただけでなく、日本の政治や外交の見方にも大きな影響を与えたと思います。
日本を出てアメリカで学んだ前後で、自分の考え方が大きく変化したのは、非常に興味深い体験でした。みなさんも機会があれば、海外の方と国際的な話題について語り合ってみるとよいのではないでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。