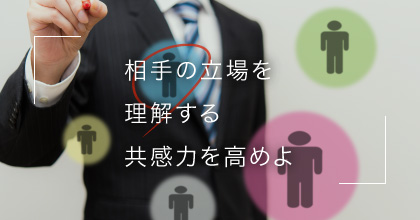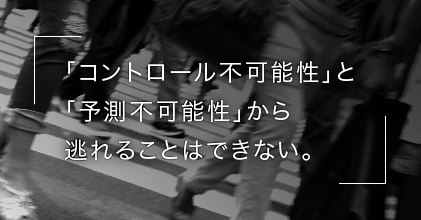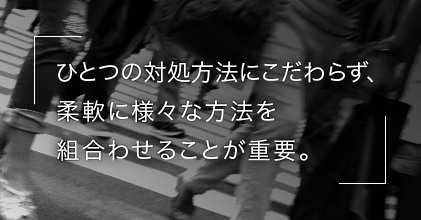人生のターニングポイントアプローチを変えて見つけた、研究する喜び
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【22】
私のターニングポイントは、大学で「理論」から「実験」へと研究手法を変えた時です。
学部時代は、世界的に有名な「理論」社会学者が著した分厚いドイツ語の原書を翻訳するという作業を黙々と続けていました。
しかし現実の問題をある学者の理論だけに依存して解明する「理論」社会学よりも、事実をそのまま実証的にとらえる「実験」社会心理学への興味が湧いてきたのです。
そこで卒論を「学歴主義の実験」にしました。ある講師が授業を行う動画を見て、その講師の学歴情報が異なると印象や評価が異なってしまうという実験結果でした。
この体験が私を変えてくれました。自らの手で実験をして、新たな結果を導き出せたことがとても意義深く感じたからです。
博士課程でちがう大学に移った時には、いきなり経験も知識もない「コンピューターコミュニケーション」の研究をするように言われて驚きましたが、実験手法のよいトレーニングになりました。
これを機に『協調か対決か コンピューターコミュニケーションの社会心理学』という博士論文を書き上げ、さらに内容が評価されて受賞し出版することもできたのです。
本学では、商学部の学生がゼミに来るようになり、今度は金融という現実的な問題に目が向き始め、あまり研究が進んでいない金融の心理学分野の研究を進めるきっかけになりました。
知らない世界や異質な人々とコミュニケーションをすると、自分の研究手法が役立つこともあり、コラボレーションやイノベーション、そして分野を超えて知の共創ができると感じました。
社会人の皆さんも、これまでとは異なる課題に面したり、畑違いだと感じる場合でも、枠組みを超えて努力し協力しあうことで新しい世界に踏み出せるかもしれません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。