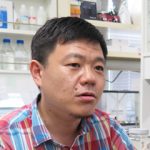>>英語版はこちら(English) 植物ホルモンの研究は、近年、大きく進展しています。一般には、まだあまり知られていない分野ですが、植物ホルモンの作用を利用すれば、作物の収量を上げたり、環境問題の解決にも繋がる可能性があることがわかってきました。この研究は本学の農学部でも進められています。
農業生産の世界的革命に繋がった植物ホルモン
 植物ホルモンとは、植物の体内で生成され、その植物の生長・形態形成や環境応答を制御する物質のことです。あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、植物ホルモンの機能を利用して、農作物の増産や品種改良などが行われています。
植物ホルモンとは、植物の体内で生成され、その植物の生長・形態形成や環境応答を制御する物質のことです。あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、植物ホルモンの機能を利用して、農作物の増産や品種改良などが行われています。
ところが、どんなホルモンがどのように生長に関わっているかなど、まだまだ未知の部分も多く、逆に言えば、非常に大きな可能性を秘めている研究分野です。
例えば、種なしぶどうは、食べやすいことで非常に人気ですが、どうやって作るのかご存じでしょうか。
これは、受粉前のぶどうの房をジベレリンという分子の溶液に浸すと、受粉しなくても実を作ることができるため、種のないぶどうができるのです。このジベレリンも植物ホルモンのひとつです。
種なしぶどうも画期的な農作物ですが、実は、このジベレリンは農業の歴史における革命にも関与しているのです。
1940年代から60年代にかけて穀物の生産量を上げる研究が盛んに行われ、その結果、高収量の品種が見つかり、その後、世界中の穀物の生産量が劇的に向上した歴史があります。これは「緑の革命」と呼ばれています。
実は、このとき見つかった品種とは植物の背丈が従来のものよりも低い、半矮性の品種でした。
どういうことかと言うと、植物は肥料を与えれば背が伸びます。植物が大きくなることは、一見、高収量に繋がるように思えますが、あまり背が高くなると、風などによる倒伏の危険性が高くなります。
例えば、日本をはじめ東南アジアなどでも、台風によって稲が倒伏し、大きな被害が出ることがあります。稲の背が高ければ高いほど、その被害は大きくなるでしょう。つまり、作物に良い肥料を与えても、収量に結びつかないということになるわけです。
ところが、背丈がある程度のところで止まり、それ以上は伸びない品種が見つかったのです。それによって、倒伏の危険性が低くなり、さらに、与えた肥料は実に繋がるため、結果的に、革命的な高収量になったわけです。
ところが、なぜ、肥料を与えても背丈が伸びないのか、実は、その仕組みは当時わかっていませんでした。それを解明したのは、2000年代になってからで、日本の研究者たちです。
それが、ジベレリンの作用でした。この植物ホルモンの重要な機能は、植物の背丈を伸ばすことです。
実は、半矮性の形質を示すイネの品種では、体内でジベレリンを作る機能が低下していて、そのためにジベレリンの量が減っていることがわかったのです。
この歴史的事実は、植物ホルモンの働きが変わると、世界規模の農業革命にも繋がるということを示しています。
しかし、私たちにとって、植物ホルモンは、まだまだ未知の部分がたくさんあります。これを解明し、正しく理解することができれば、その機能を人為的に改変することも可能になってきます。それは、第二、第三の緑の革命になる可能性を秘めているのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。