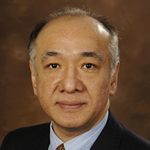人生のターニングポイント特異な経済制度からも見えた、変化を恐れる日本人気質
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【82】
私が経済制度とその変化などを比較分析する「制度経済学」に傾倒するようになったターニングポイントは、大きく3つあるように思います。マクロ経済政策も非常に重要ですが、その前段階としての枠組みが整っていなければ、一国の経済発展は難しい。これらのターニングポイントを経て、制度が非常に重要だという認識に至りました。
1つめは、1989年に始まった日米構造協議です。これは日米両国の対外収支の不均衡是正に向けて構造問題を指摘し合い、必要な改革に取り組むことを目的にした協議です。そこで終身雇用や企業系列などの日本的制度の特異性が指摘されました。もともと私は1970年代に経済学を学び始め、マクロ経済を中心に研究していましたが、それらの制度がなぜ生じたのか、その合理性は何なのかといった点に興味を持ち始めたきっかけとなりました。
2つめは、ノーベル経済学賞を受賞したロナルド・コースの「The Nature of the Firm(邦題:企業の本質)」という論文を手に取ったことです。アメリカ留学時に学んだ縁もあるのですが、コースは同論文で、なぜ企業という組織が市場とは別に存在するのか、企業の規模や市場との境界はどのように決定されるのかといった問題を提起しました。その考えを踏まえると、日本独特の制度は市場での取引費用が高い時代には上手く機能しえたものの、情報通信技術の革新や新興国の台頭などを通じた経済のグローバル化により取引費用が低下していったことで、その有効性を失いつつあると解釈できます。そこに過去30年間、日本経済が低迷している一つの理由を見いだせました。
3つめは、1990年代に定点観察と称してたびたび訪問していたシンガポールでの見聞です。当時のシンガポールは、制度改革によって、かつての労働集約型産業主体の経済から、資本集約型、頭脳集約型の経済へと転換していく過渡期でした。市場の実態に先行する形で人為的に経済制度を構築し、経済を将来望ましいと思われる方向に誘導することで、飛躍的に成長していく姿を目の当たりにしたのです。
以上のターニングポイントを経て経済制度をフォーカスするようになりましたが、どういった制度を構築したら良いかという点よりも、「どうして制度の転換が難しいのか」といった点に研究の比重を置かざるを得ないのが日本の現状です。理論面からも実体験からも制度の大事さが見え、結果的になぜ変わらないのだという疑問に集約されていきました。
過去の成功に引きずられ、昔のやり方に安住して、泥舟が沈むような形で日本経済が駄目になってきています。必要なのは、コンフォートゾーンから脱出することです。個々人の生き方も同様です。日本のように便利な社会だと、安住するほうが楽でしょうが、勇気をもって外に出てみると、また違った景色が見え、それらは自身の成長につながります。失敗することもまた、次につながる良い経験となります。2つ道があったら難しい方に挑戦することが、飛躍するために大切だと言えるでしょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。