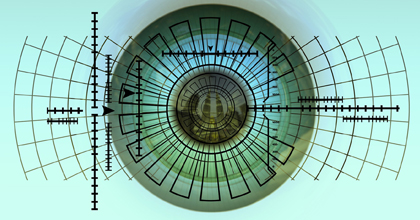安全と権利自由の「両立」に重要なのは私たちの「関心」
 インテリジェンスが一般の人々にも注目される分野の一つにテロがあります。例えば、「オリンピックの開催に当たり、テロの未然防止は万全か」といった文脈で、インテリジェンスの機能が注目されることがあります。
インテリジェンスが一般の人々にも注目される分野の一つにテロがあります。例えば、「オリンピックの開催に当たり、テロの未然防止は万全か」といった文脈で、インテリジェンスの機能が注目されることがあります。
西側先進国におけるテロ、特にイスラム過激主義によるテロは、従来は「中東地域等で訓練を受けて送り込まれて来るプロのテロリスト達による集団的・組織的な攻撃」が中心でした。2001年に米国で発生した911事件が典型例です。しかし最近は、こうした形態ではなく、いわゆる「ホームグローン(その国で生まれ育った人々)」による少人数あるいは単独犯(ローンウルフ)による形態が中心となっています。
こうした形態のテロは、インテリジェンス機関を始めとする治安機関にとっては、その行動を事前に察知して未然防止策を図ることは非常に困難です。こうした形態のテロに備えて安全の確保に万全を期すための有力な施策としては、インテリジェンス機関等の権限の強化、高性能な装備の導入(例えば、顔認証機能と連動した高性能の街頭防犯カメラシステムの導入)等が考えられます。
しかし同時に、こうした動きに対しては、「権限を濫用されて権利自由が侵害されるのではないか」との懸念が示されることも少なくありません。
例えば米国では、911事件の後、CIA等がテロ対策名目で権限や手法の強化を図りました。しかしその後、そうした新たな権限や手法の一部については、人権侵害の疑いがあるとの指摘を受けて見直しが図られています。日本においても、特定秘密保護法やテロ等準備罪の立法の際には反対デモ等が行われました。こうした動向は、同様の懸念の現れと考えられます。
このような場合、日本において従来から多くみられる対処法は、法学的アプローチ、すなわち、インテリジェンス機関等に権限を付与する根拠法令の立法に際して可能な限り制限を加えることによって権限濫用の危険性の低減を図るアプローチです。「法の支配」の社会においてこうしたアプローチが重要であることは言うまでもありません。
しかし、こうしたアプローチは、インテリジェンス機関等がテロ対策等の任務遂行のために本来必要とする権限が十分に与えられなくなる可能性を含みます。つまり、こうした法学的アプローチのみでは、安全か権利自由の「どちらかの二者択一」となるきらいがあり、結果として、安全と権利自由の「両立」が実現できなくなる(あるいは両者が共倒れとなる)可能性があります。
欧米諸国においては、こうした法学的アプローチに加えて政治学的アプローチ、すなわち、インテリジェンス機関等に対する民主的な統制制度を設けることにより、安全と権利自由の「二者択一」ではなく「両立」を図るアプローチが採られる例が少なくありません。
言い換えると、インテリジェンス機関等に対して任務遂行に必要な然るべき権限を与えると同時に、これらの機関が権限の濫用・逸脱を起こさないようにその動向を監督する民主的な制度を構築するというアプローチです。
こうしたアプローチの背景には、「民主的統制機関による適切な監督に服することにより、インテリジェンス機関等による強い権限行使に一定の正統性(Legitimacy)が与えられる」との考え方があります。
こうした制度の例としては、米国における連邦議会上下両院の情報特別委員会、イギリスにおける議会情報保安委員会などがあります。日本の場合、現時点では同様の制度はありません。敢えて言えば、2014年12月の特定秘密保護法の施行に合わせて国家の衆参両院にそれぞれ設置された情報監視審査会が部分的に類似の機能を有しています。
今後、日本において、テロ対策等の安全確保のためにインテリジェンス機関等の権限強化等が図られるならば、併せてこうしたインテリジェンス機関等に対する民主的統制の制度の整備が求められる可能性があります。
現時点ではこうした制度が存在しないことから、具体的にどのような制度を構築すべきか、という点からの検討が必要となります。ある特定のモデルが普遍的に正しいとは限らず、それぞれの国の社会的、政治的特徴に応じて最も相応しいモデルを構築することが求められます。こうした点も、インテリジェンス研究の重要な課題の一つです。
さらに、「安全と権利自由の両立」が実現されるためには、監督制度が構築されるのみならず、こうした制度が実際に効果的に運用されることが必要です。
そのためには、国民自身が、こうした組織の運用状況に興味を持ち、場合によってはその運用に積極的に関与することが肝要です。社会全体が「自分たちには無関係な世界だ」との無関心な姿勢であるとすれば、たとえこうした制度を構築したとしても「絵にかいた餅」に終わってしまう可能性があります。
すなわち、こうした制度の運用に健全な関心を払い積極的に関与することは、民主主義社会における「安全と権利自由の両立」の実現のために国民自身が負担すべきコストであると言えるかもしれません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。