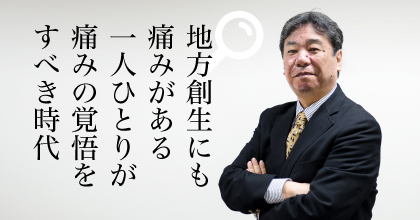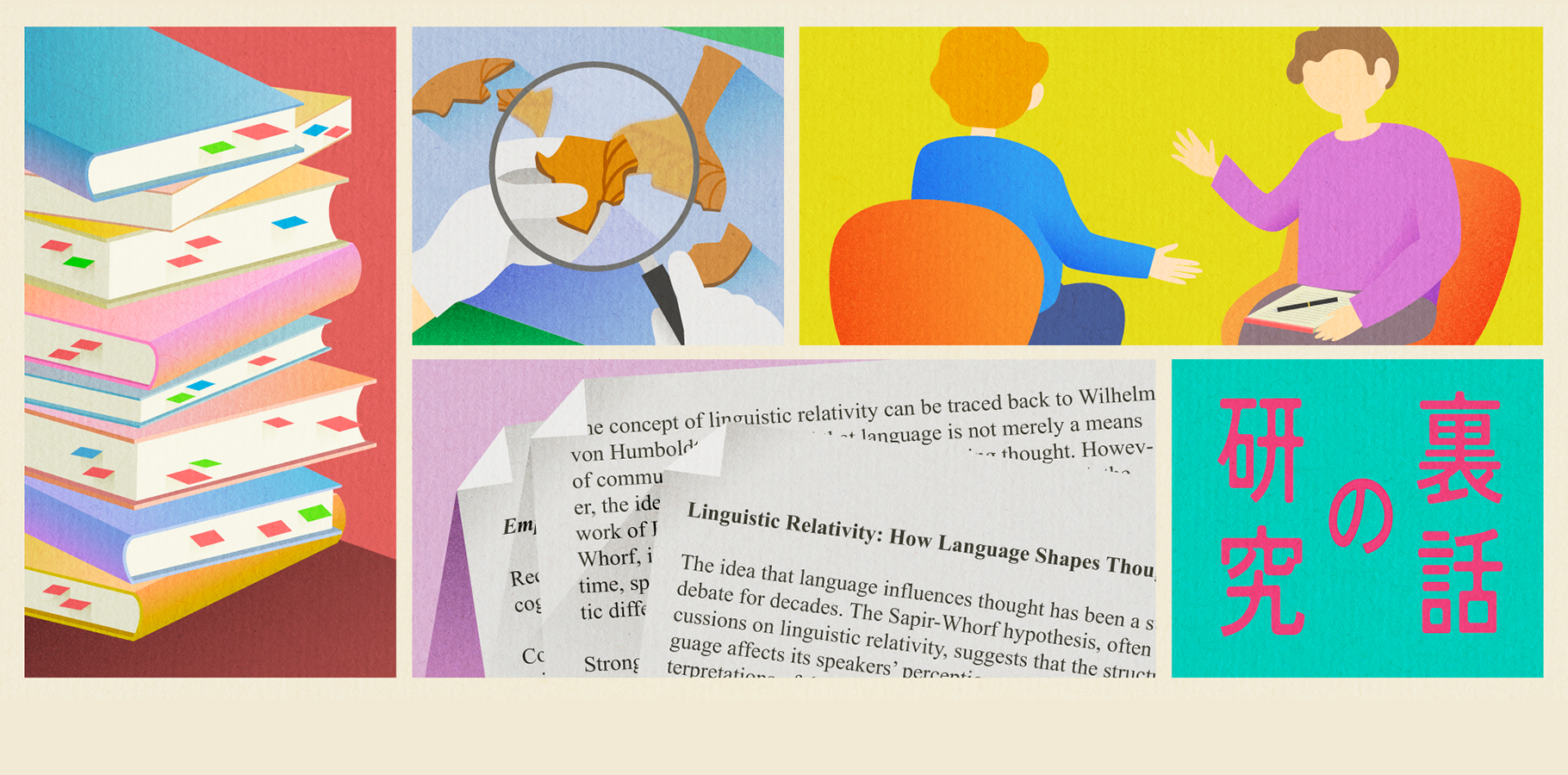
研究の裏話「今」の目で「過去」を探ると「新しさ」が見えてくる
教授陣によるリレーコラム/研究の裏話【2】
「歴史の研究って、もう掘り尽くされているんじゃないですか?」と、よく聞かれます。たしかに、私が専門とする19世紀イギリスの大気汚染対策については、現地イギリスで数多くの先行研究があります。研究を始めた当初は、「いまさら何が新しく言えるのか」と自問する日々でした。
特に20世紀に書かれた公害研究では、「企業vs.民衆」という対立構図が定番です。つまり、資本家たちが利益を優先し、公害に苦しむ市民はそれに抗議する──そんな構図が19世紀にも当てはめられ、1980年代ごろまでは「当時は大衆運動がなかったから公害対策は失敗した」と結論づける研究が主流でした。
しかし、2000年代以降の社会の変化を見る中で、私は考えが変わってきました。現代では、多くの企業が自ら環境対策に取り組んでいます。利益と環境が必ずしも対立するものではなく、むしろ両立する動きが広がっている。そんな現在の視点を持って19世紀のイギリスを見直してみたところ、また違った風景が見えてきたのです。
たとえば、当時制定された煤煙規制に至る過程を追い、史料を丹念に読み込んでいくと、一部の工場主や資本家たちは規制にむしろ積極的だったことがわかってきました。煤煙で自らも損害を被っていた彼らにとって、煙害対策は経済的にも合理的だったのです。
このように、「今」の感覚で「過去」を見直すと、それまで見過ごされていた事実や、新しい構図が浮かび上がってきます。学生時代に読んだE・H・カーの『歴史とは何か』には、「過去は現在の光に照らされて初めて知覚できるようになり、現在は過去の光に照らされて初めて十分理解できるようになる」と書いてありましたが、まさにその通りでした。
また、史料そのものは変わらなくても、見方を変えれば全く違う意味を持つようになります。企業側から公害問題を見るというアプローチも、以前の研究にはあまりなかった視点です。「使い古されたテーマ」と思われる研究分野であっても、時代に応じて見直せば、新たな発見のチャンスは十分にあります。
これは、きっと研究に限った話ではないでしょう。ビジネスでも、教育でも、何かに行き詰まったときは、視点を変えてみると、思わぬ可能性が見えてくるかもしれません。古いものの中にも、新しさを見出す余地はいつもあるのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。