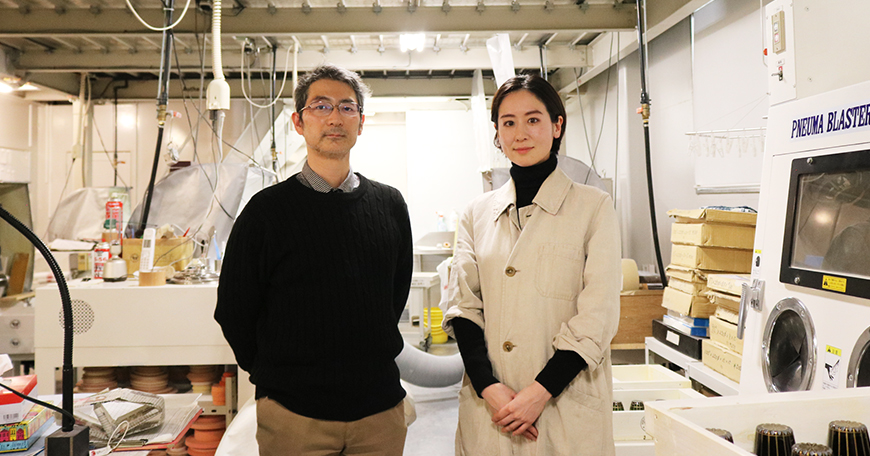【QuizKnock須貝さんと学ぶ】「愛ある金融」で社会が変わる、もっと身近な投資

2023年12月、東京ビッグサイトで「SDGsWeek EXPO エコプロ2023出張授業」が開かれました。登壇したのは明治大学商学部・三和裕美子教授と、東大発の知識集団「QuizKnock」の須貝駿貴さん。2人は「クイズで知る、身近な投資! 社会をよくするお金の流れ」をテーマに、会場を訪れた中学生らと「投資」について考えました。
三和 裕美子
明治大学 商学部 教授
主な研究分野は、機関投資家とコーポレート・ガバナンス、機関投資家の社会的責任投資・ESG(環境・社会・ガバナンス)投資など
須貝 駿貴
東京大学大学院総合文化研究科後期博士課程を修了。2017年に東大初の知識集団「QuizKnock」に加入。資産運用に関する講演会やYouTubeへの出演など、金融教育にも取り組む。エコプロの出張授業に参加するのは今回で3回目。
投資は企業への応援
―今年は「投資」という言葉をよく耳にした気がしましたね。
三和:はい。株式投資をして利益を得た、という学生もいました。
―一方で、投資は「よく分からない」「お金持ちの人が余裕資金でやるもの」みたいな声も聞かれると思いますが、須貝さんご自身はどうですか?
須貝:まさに僕も同じで。今でこそ、YouTubeの「まなぶわかるとうしチャンネル」に出演したり、日本証券業協会の冊子に登場させていただいたり、投資のこともずいぶん勉強して詳しくなったのですが、大学生のときに父親からNISAについて教わり、投資を勧められたときは全く自分には関係のない話だと聞き流していましたね(笑)。投資したお金が目減りするリスクもあると聞いたので、それならそのお金で「ステーキ食べたい!」と考えていました。
三和:須貝さんが言うように、投資というと「怖い」「よく分からない」という人が多いと思います。実は学生にお金についてアンケートを取ると、「だまされそう」とか「お金持ちのものでよくわからない」とかネガティブなイメージが出てくるんですね。そのため投資と聞くと、ハードルが高く感じるのだと思います。しかし、例えばみなさんがコンビニでフェアトレードのチョコレートを購入することも「投資」と同じ意味に考えることが出来るんですよ。
須貝:チョコレートを買うことと投資が同じ、とはどういうことなんですか?
三和:みなさんがチョコレートを買えば、その商品を作っている企業の売り上げにつながります。それは、その企業を応援するためにお金を投資しているのと同じ。日常の何気ない行動の一つ一つが、企業に関わることだと意識してもらえたら良いのかなと思います。
たとえば、今回の「エコプロ展」では、環境問題の解決に役立つ技術や製品、素材について展示されていますね。そのような研究や技術開発には当然、莫大なお金がかかりますが、そのお金の確保には「投資」が重要な役割を果たすわけです。
ただ、開発現場を見たり、技術者に会ったりして投資をするか否かの判断ができれば良いのですが、実際にはそのようなことはほとんどできませんよね。ですから、多くの人は株式市場での株価の上下の動きだけに関心が向いてしまい、株価が下がる局面での「怖さ」のイメージが先行していると思います。しかし、株式市場を通じて投資するということは、自分のお金が企業の研究や技術開発に役立っているということなんです。そのようなイメージを持ってもらえれば、お金の損得とは違う捉え方ができると思いますよ。
須貝:なるほど。株式市場で株価だけを見るから、その企業のことがよく分からず、投資が怖いものだと思ってしまうんですね。
三和:大好きな商品があれば、企業にはその商品を作り続けてほしいし、もっと好きになる商品を開発してほしいものです。そのような応援の気持ちから投資を始めれば、より投資を身近に感じてもらえるのではないでしょうか。最初はささいな動機でも、その会社に投資するとなれば経営者はだれか、売り上げはどれぐらいか、など興味が広がっていろいろ調べるようになると思います。
年金を通じてみんなが投資に関わる?
―私たちにとって身近なものの一つに「年金」があります。これも運用によって成り立っているんですね。
三和:はい。私たちの年金はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)によって運用されています。運用資産はなんと200兆円を超えていて、世界最大の機関投資家とも呼ばれているんです。そして運用にあたっても、環境に配慮した事業をしているか、人権を大事にしているか、といった点も配慮して投資先を選んでいます。国民の年金を運用しているGPIFですから、社会課題の解決に取り組んでいる企業に投資した方が良い、という考え方なんですね。このような取り組みは「責任投資」とも呼ばれています。
須貝:単純に、儲かっている企業に投資すれば良い、というものではないのですね。
三和:もちろん配当が出たり、株価が上がったりする方がありがたい、というのは大前提としてあります。しかし、だからと言って環境問題を無視して、自社の利益ばかりを追求するような企業に投資してもいいの?という疑問を多くの人に持ってもらいたいんです。
クイズで知る、身近な投資!
―ではここからはクイズでもっと投資について学んでみたいと思います。ぜひみなさんも須貝さんと一緒に挑戦してください。
須貝:僕も答えは知らないので、“ガチ”でやりますね。中学生のみんな、クイズバトルだ!
【第1問】
GPIFはその投資額の大きさから「資本市場の〇〇〇〇」と呼ばれているでしょうか。
A:コンドル
B:ゾウ
C:クジラ
【正解はC】
須貝:やはりクジラに手を挙げた人が多いですね。一番大きいからでしょうか。(笑)
三和:GPIFの運用資産が200兆円に上るという話をしましたが、これは日本の国家予算110兆円に比べてものすごく大きい額ですよね。この規模で株式や債券を買って投資する、という様子が、まるでクジラが大きな口を開けて魚を一気に食べていく様子に似ている、ということから「資本市場のクジラ」と呼ばれることがあるんです。
【第2問】
経済的な価値に関する情報ではない非財務情報も考慮した投資のことを「〇〇〇投資」と呼ぶでしょうか。
A: USA
B: ECO
C: ESG
【正解はC】
須貝:「USA」や「ECO」はみなさんも聞いたことがあると思いますが、「ESG」はどうでしょうか。中学生の皆さんは知っていましたか?
三和:ESGというのは、環境の「Environment」、社会の「Social」、ガバナンスの「Governance」から頭文字をとった言葉です。「G」のガバナンスは少し難しい言葉ですが、企業が健全な経営をしているかどうか監視、統制するような意味があります。環境・社会・企業統治、それぞれの課題解決に資する投資のことを意味する用語です。
【第3問】
次のうち、ESG投資はどれでしょうか?全て選んでください。
A:温室効果ガス排出量の削減に取り組む企業に投資する
B:男女平等を掲げ、女性の管理職の多い企業に投資する
C:働きやすい環境の改善に取り組む企業に投資する
【正解は全部】
須貝:やっぱり全部が正解なんですね。素晴らしい! 「C」で言われていることも、“ブラック”な企業は応援できないし、投資もすべきとは思えないから当てはまっていると思いました。
三和:はい、「C」の「働きやすい環境の改善に取り組む企業」というのは、その企業で働く人たちを“人的資本”と考え、誰もが居心地よく働ける企業を目指そう、というものですね。
須貝:ESG投資が注目されるようになってきている。それはつまり、ESGに関連する事業や活動をしていれば応援してくれる人が増える、ということですよね。GPIFからも応援してもらえる可能性があるのですから、企業は地球のため、従業員のためを考えた取り組みにぜひ力を入れるべきですね。
【第4問】
環境や人権などに配慮した消費行動のことをなんというでしょうか?
A: マジカル消費
B: エシカル消費
C: ロジカル消費
【正解はB】
須貝:「エシカル消費」という言葉は僕も聞いたことがあります!英語の「エシカル(ethical)」は「倫理的・道徳的」という意味ですよね。
三和:須貝さんの言う通りで、環境や人権に配慮した商品やサービスを購入しようということですね。須貝さんはエシカル消費を意識して、買い物をされたことはありますか?
須貝:あります。たとえばコーヒーショップの店頭で、児童労働をさせないコーヒー農園の豆を使っていることを知って。そのような案内を見てからは安心して購入できるようになりました。
三和:労働環境を大切にしている企業のコーヒーを買う、フェアトレードのチョコレートの商品を選んで買う、ということはまさにエシカル消費ですね。
【第5問】
近江商人の三方良しとは「売り手良し」「買い手良し」「〇〇良し」と言われます。最後に入る言葉はなんでしょうか。
A: 安全良し
B: 世間良し
C: いつでも良し
【正解はB】
三和:「売り手良し」は会社の利益が上がって良かった、「買い手良し」は商品を買って良かった、そして「世間良し」は地域や社会が豊かになって良かった、という意味で、3つを合わせて「三方良し」なんですね。これは江戸時代、近江商人によって全国へ広まった日本に昔からある考え方です。現在のESG投資とつながる部分もありますよね。
この考え方が滋賀県から関西、全国と広がっていったことと同じように、私たち一人ひとりの投資行動も世界、もっと言えば宇宙も良くする未来へつながっているんだ、というイメージを持ってもらえるとうれしいですね。
須貝:エシカル消費の話ともつながりますよね。先ほどの話でも、コーヒーショップと僕だけではなく、コーヒー豆の生産者のためにもなる、ということですよね。Win-Winではなくて、Win-Win-Winだ!
投資は推し活!?三和教授の考える「愛ある金融」
―今日はクイズも含めて投資について学んできたわけですが、いかがでしたか。
須貝:その企業のことをよく知らないのに、株式市場で株価の変動だけを見て投資し、それで自分のお金が増えたとしてもハッピーではないと思いました。今日はさまざまな角度から、投資が社会をよくすることにつながっている、ということを見てきて、投資の本質を改めて理解できた気がします。
三和:いろいろなお話をしてきましたが、まとめますと、未来を考え、環境や人権に配慮した企業や、従業員の働きやすさを考えている企業に株主として応援するのも投資だということです。
これを私は「愛ある金融」と呼んでいます。多くの人がお金を儲けたいと思っていますが、環境問題への配慮が足りない企業とか、ブラックな環境で従業員を働かせている企業には誰も投資したいと思わないですよね。投資は難しいものではなく、未来のために応援したい企業へ自分のお金を投じる、ということ。そういう視点で投資を捉えてもらいたいと思います。
須貝:「愛ある金融」、僕もこれからこの言葉を使っていきます!
三和:投資は冷たいものではない。愛があって温かみのある行動なんだ、と思ってもらえれば。言い換えれば“推し活”みたいなものですかね。
須貝:確かに! 今日は僕のファンも来てくれていますけれど、応援してくれる人がいるから僕も頑張れるし、その頑張った分をファンや社会に還元していく、ということですね。投資は社会を良くするお金の流れ、という意味がよく分かりました!
■三和裕美子教授の関連記事
・世界を変える あなたのお金の流れ方(研究紹介アニメ)
・株式投資は「愛ある金融」に変わり始めている
■QuizKnock
東大クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。
HP: https://www.portal.quizknock.com/
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。