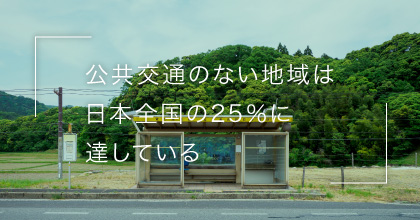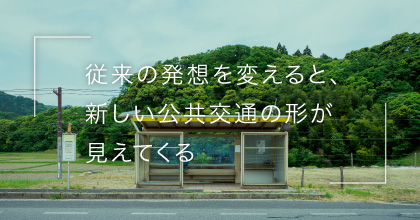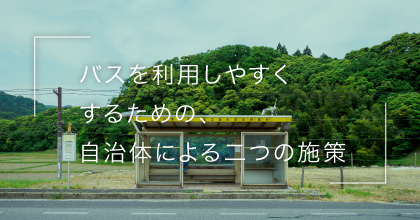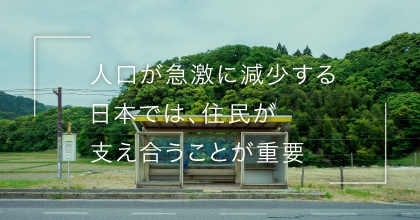受益者負担金や広域連携の導入
この連載でも解説したコミュニティバスの運営に、新たな発想を取り入れている自治体があります。
コミュニティバスは、料金収入と税金によって運営されますが、長野県上田市では、さらに地域支援金を加えています。
地域支援金とは、いわゆる受益者負担のことです。コミュニティバスが回る集落の住民は、1世帯ごとに支援金(上田市の場合は年間1000円)を出すのです。バスを利用する家族がいない世帯であっても、同額を出します。
この取り組みに、住民からはほとんど異論はなかったといいます。コミュニティバスによって病院に行きやすくなったり、買い物に行きやすくなった高齢者の便益を個人のものとして捉えるのではなく、集落全体の便益と捉える、共助の意識、自治の意識を地域全体で共有していることが、こうした取り組みが円滑に行える根底にあると思います。
コミュニティバスの運行のために、複数の自治体が協力する広域連携を行っているのが、青森県八戸市と周辺の市です。
この地域では、八戸市が中心都市と呼ばれ、病院、ショッピングセンター、高校などの施設が集中しています。そのため、八戸市周辺の市の住民は、昼間は八戸市に行くことが多いのです。しかし、そこに公共交通がありません。自家用車を運転できなければとても不便です。
そこで、コミュニティバスを運行しようと思っても、周辺の市は規模が小さく、経済的に運行が難しかったのです。そこで、八戸市と周辺の自治体で負担金を出し合い、各自治体を回って八戸市に行くコミュニティバスを走らせることにしたのです。
こうした広域連携により、高齢者はもちろん、高校生の子どもを自家用車で毎日、高校まで送り迎えしていた家庭も多かったので、住民は非常に助かっています。
ここで紹介した4つの自治体の取り組みは、それぞれの住民たちの需要や課題を解決するために、各自治体が独自に行っている取り組みです。
国からいわれたり、指導されて行うのではなく、各自治体が、自分たちのことを自分たちで考え、既存の発想を捨て、新しい発想で、自分たちにとってより良い取り組みを実施していることが、非常に新鮮であり、重要なことだと思います。
次回は、私たち住民になにができるのかについて解説します。
#1 交通空白地域って、なに?
#2 コミュニティバスって、なに?
#3 バスを利用しやすくするためには?
#4 コミュニティバスの財源をどうする?
#5 公共交通を支えるために住民にできることは?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。