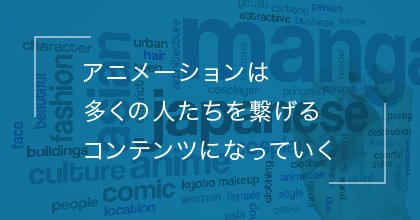アニメーションには国境や言語を越える国際言語性がある
コンテンツのネット配信ビジネスが拡大した現在、外国の大手配信会社から、日本のアニメ制作会社に作品の制作を依頼するケースも多くなってきました。
それに比べ、日本のドラマはテレビで放送しづらいものなど一部を除き、なかなか売れません。なぜなのか。ひとつには、日本社会独特の文化がある種の壁となって、世界的な親しみやすさに繋がらないのだろうと思っています。
それに対して、アニメーションは省略と誇張を使った記号的な表現なので、登場人物が日本人に見えなかったりして感情移入がしやすいのです。事実、日本のアニメーションを海外で放送したとき、視聴者がそれを自国の作品だと思っていた例もあります。
また、動く絵によって表現される楽しさは、たとえ、言葉がわからなくても、観る人に伝わるものです。視覚的な動きの刺激から人が感じる楽しさは、基本的に同じなのです。それを、前回述べた「ハルヒダンス」は見事に実証しています。
今年の7月、この「涼宮ハルヒの憂鬱」の制作会社(京都アニメーション)が放火されるという痛ましい事件が起きましたが、同社の作品から幸福感や生きる意欲をもらったというコメントが、国内からだけでなく、世界中から数多く寄せられました。
その事実は、アニメーション作品に、観る人を絶望から救ったり、ネガティブなものを乗り越えるポジティブな力を与える力があることを教えてくれます。これは、本当にすごいことだと思います。
いま、観る人にそこまでの力を与えられる国際的なコンテンツは、なかなか見当たらないのではないでしょうか。
そして、これは、「涼宮ハルヒの憂鬱」だけの現象ではないと思います。日本のアニメーションには、諦めずにやれば良いことがあるとか、友だちとちょっとしたことで気まずくなっても仲良くすることができるとか、自分の心を見直すささやかな努力で人は幸せになれるという前向きなメッセージが共通してあると思います。
制作している人たちが、思い詰めて説教のようにしているわけではないのも、良いところだと思います。観る人を喜ばせたい、幸せな感じを届けたい、とシンプルに思っているだけ。そんな作品が、国境や言語を越えて、それ以上のなにかを観る人に与えているのです。
その意味で、アニメーションは世界平和的なツールであることを認識してほしいです。観る人が同じ感情を共有できるような国際言語性があると思います。そして、いま、それを多くの作品で実現しているのが、日本のアニメーションなのです。
次回は、日本のアニメーションの特徴について解説します。
#1 日本のアニメはいつから世界で人気になったの?
#2 アニメはオタク文化?
#3 アニメを観て、幸せになる?
#4 日本のアニメの特徴って?
#5 日本のアニメの未来はどうなる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。