アカデミアのリアルに迫る、現役大学教員たちが語る「“大学教員”という選択肢」


大学や公的研究機関に勤め、学術的価値のある基礎研究を主に扱う研究職のことをアカデミアと呼び、認知されていますが、アカデミアをめざすためのキャリアパスや大学教員という仕事について、その実情を知る人は、そこまで多くないのではないでしょうか。
Meiji.netでは、これまで「リレーコラム」などの記事を通して明治大学の研究者の仕事を身近に感じてもらえるような記事を発信してきました。
今回は、明治大学の大学院生向けキャリアプログラムの一環として開催された、現役教員たちが自身の経験を語るパネルディスカッション「“大学教員”という選択肢」にMeiji.net編集部が潜入。あまり知られていないアカデミアのリアルな世界を垣間見られたイベントをレポートします。
登壇者紹介
大学院へ進学するきっかけ・進学後の院生生活
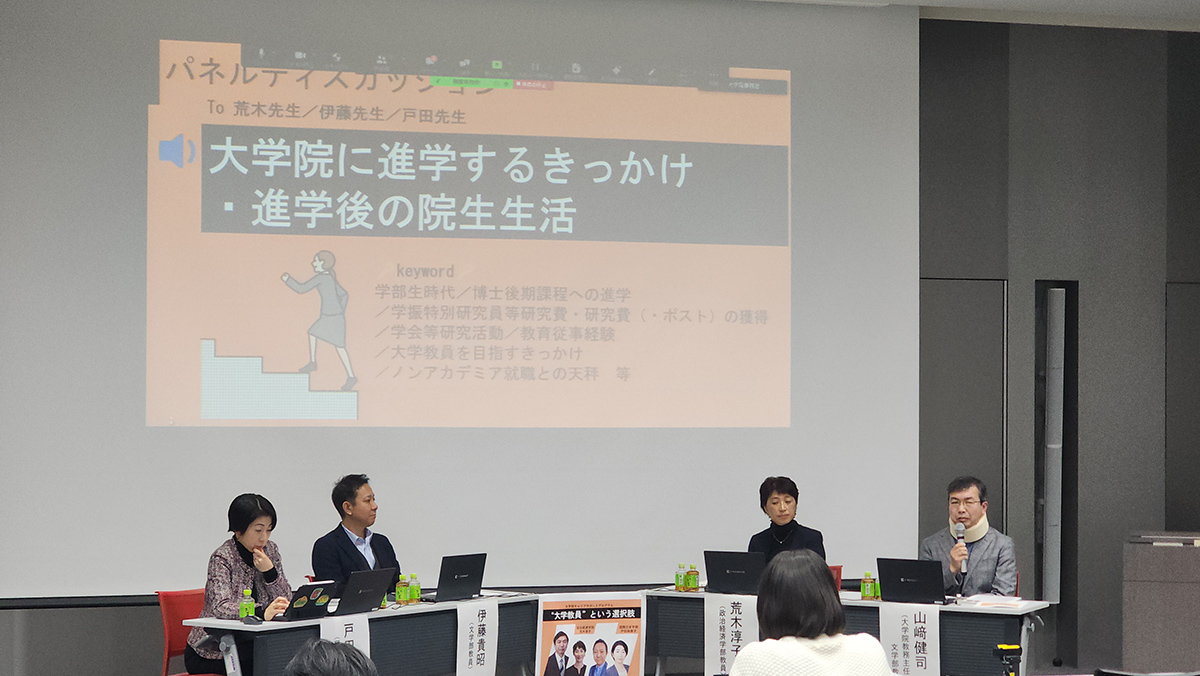
山﨑 通常の企業への就職とは異なり、アカデミアのキャリアパスは簡単な道ではないと言われますが、皆さんの経験を聞かせてください。
伊藤 学部生の時に履修していた教職の授業に関心を持ち、大学教員になりたいという思いが芽生え、大学院に進学して教育心理学を専攻しました。私が学んでいた分野では通常、6年かけて博士論文を作成します。修了する頃にはほぼ30歳になってしまう状況を覚悟していましたが、27歳を過ぎた頃から自分の将来に対する不安が増し、モチベーションを維持するのが大変でしたね。教員免許を取得していたので中高の教員として就職できる道があることを支えに、なんとか乗り切って博士論文を提出しました。
荒木 大学院に進学したのは、学部での学びに留まらず、もう少し大学で専門知識を付けたいと思ったからです。社会学の研究室で博士課程3年まで研究を続けましたが、自分が教鞭を持つイメージが沸かず、社会人経験を積む目的で、シンクタンクに就職しました。5年半働き、そこで出会った先生に触発され、社会人大学院生として再び大学院に戻りました。以前とは別の分野で、また修士から研究を始めました。夜間やオンラインで2年間学び、はじめは会社員に戻るつもりだったのですが、先生の勧めで博士課程に進学。その後、大学の助手として働き、現在に至ります。私の場合、なんとなく大学院に進学し、いろいろ経験してから自分のやりたいことを見つけたというルートですね。
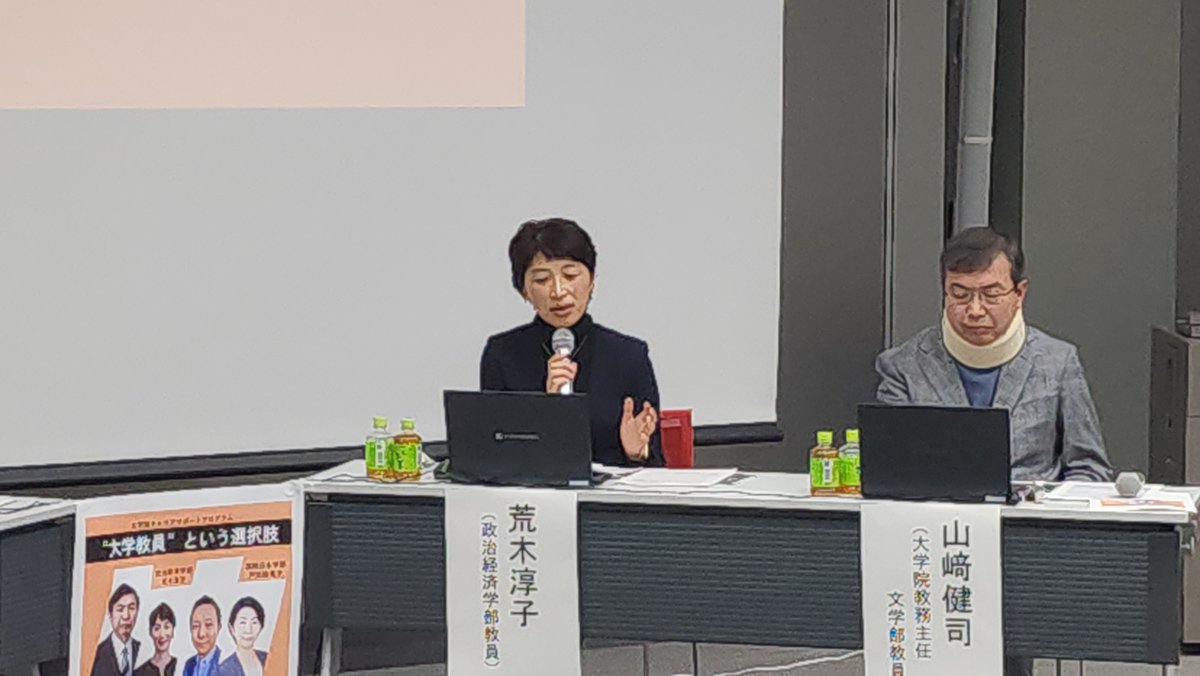
荒木淳子准教授と、今回のパネルディスカッションで司会を務めた山﨑健司教授
戸田 学部生の時のゼミで指導教員が論文指導をしている様子を見て、指導が加わると論文がこんなに面白くなるんだと思ったことから、大学教員という世界に魅力を感じたんです。自分も指導する立場になって後進を育成したいと思って教員を志し、学部からそのまま修士・博士課程に進みました。伊藤先生と同じように、当時は博士課程を3年で修了するのは難しく、6年かけて博士論文を提出しました。幸いにも、博士課程の後半では助手として働きながら研究を続けることができました。その後半3年間は研究よりも英語力を向上させることに力を入れていて、英会話学校に毎日通っていました。
大学教員へのそれぞれのキャリアパス
山﨑 私は北関東の国立大学で5年間の博士課程を修了し、その後、学振(日本学術振興会)の特別研究員として研究を続けました。東北の新設大学に務めた後、九州の公立大学で11年間過ごし、親の介護の必要があって出身地である東京に戻ってきました。私が就職した当時は18歳人口が増えて新設大学が多かったため、順調に就職することができましたが、皆さんはどうでしたか。
伊藤 博士課程6年生の時に指導教授から北陸の大学で教職の教員を探していると聞き、面接を受けて採用されました。博士論文を出す前に就職が決まるとは思っていませんでしたが、晴れて大学の教員になりました。
戸田 私は出身の大学で、そのまま助手から講師になったわけではなく、博士課程修了後に1年間、スコットランドのエジンバラ大学でビジティングアカデミックとして過ごしました。在籍しながら国内国外問わずに職を求めて大学に書類を出しまくっていましたが、まだまだ業績がない状態でなかなか採用に至らず、やっと関東の大学で専任講師の職を得ました。
就職に関しては運と縁が大きいと感じています。大学にポジションが空いているか、どのような人材が求められているかなど、さまざまな要素が影響します。大学教員以外では、在野の研究者として研究を続ける方法もあります。実際、一般企業に勤めながら研究を続け、雑誌に論文を発表している知人もいます。
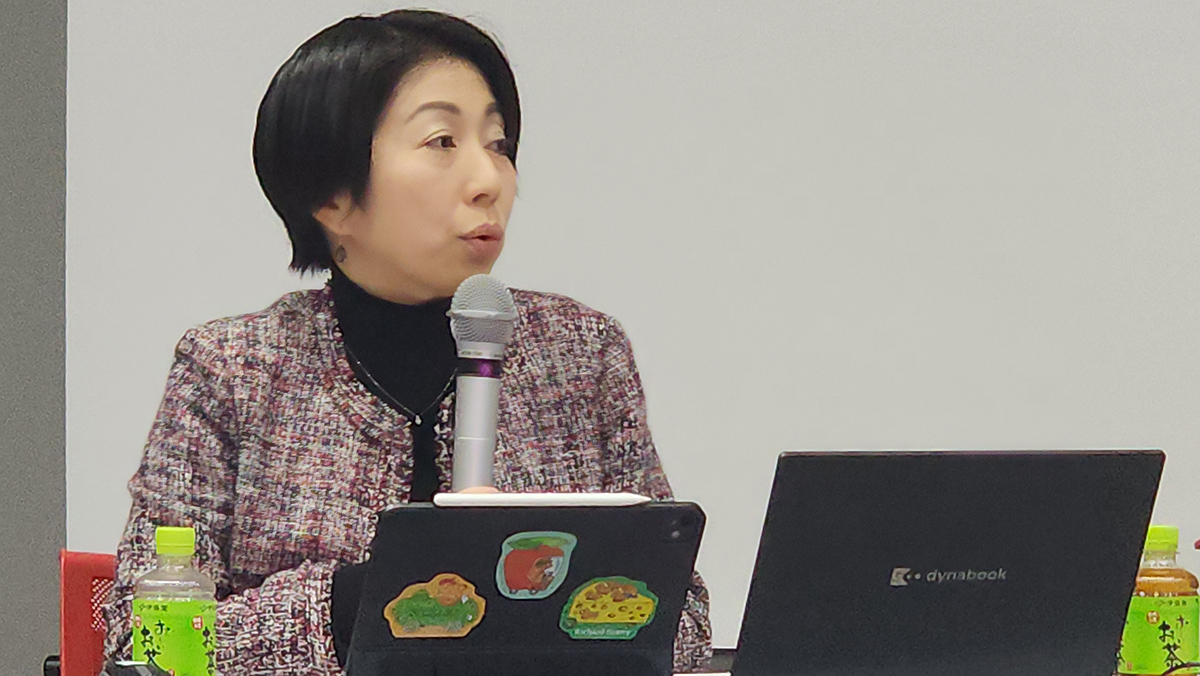
戸田裕美子准教授
伊藤 研究を続けながら仕事をするのなら、文系でも研究所をめざすのが一つの方法だと思います。授業がなく研究に専念できます。ただし、大学の数に比べて研究所の数は少ないため、選ぶのは難しいかもしれません。
荒木 民間のシンクタンクで受託調査をしていた経験がありますが、やっていることは似ているけれど、大学では自分でテーマを見つけてエンジンを回してやっていけることが、難しくもあり、一番の魅力でもあります。私は大学教員の方が自由度という点で良かったと思っています。
戸田 海外大学の教員という選択肢もありますが、アメリカの大学で働く日本人の知人は、母語ではないため学生からの授業評価が厳しいと言っています。同様に海外の大学院進学も、院生同士の競争も激しいと聞くので、覚悟が必要でしょう。苦労が報われるかどうかはわかりません。
大学教員の仕事環境とワークライフバランス
山﨑 それぞれ、いろいろなキャリアパスを経て現在に至っているのですね。では、大学教員になって感じたことは?
荒木 研究をしたくて大学に職を得たのですが、教えることの比重が大きい点が大変でした。ゼミを受け持つと、学生を密に指導することが求められ、リーダーシップやコミュニケーション力も必要となります。とはいえ、ゼミには授業では得られない楽しい交流があり、学生と向き合い勉強を教えることにもやりがいを感じます。
伊藤 大学によって求められる役割が全然違うと思います。大学によっては、研究よりも学生の教育に重点を置いている等のこともあります。明治大学では担当する授業の科目数もバランスが良く、自由に使える時間が多いため、非常に恵まれた環境で働いていると感じています。
文学部の教務主任を務めていますが、学内業務の負担が誰かに偏らないように配慮されており、非常に働きやすいです。ワークライフバランスも良く、両親の手助けが得られない環境でも3人の子供を育てることができています。

伊藤貴昭教授
荒木 私は修士論文を書くタイミングで出産し、娘が小学生の時に博士論文を書きました。特に女性の研究者は、出産や結婚とキャリアを天秤にかけて迷うことが多いでしょう。生活と研究の両立はやはり大変で、私は夫婦双方の両親の手を借りて娘を預けながら研究を続けました。ワークライフバランスについては、ライフの方は自分のタイミングで自由に選択し、ワークを合わせるというぐらいにずぶとくなった方がうまくいくかもしれないと思っています。
教育と研究の両立を求められる、大学教員という仕事
山﨑 大学教員に期待されることは何だと思いますか。
戸田 日本の大学では校務がたくさんある大学も多く、入試対応や学生対応、各種委員会、産学連携のミーティングなどの業務によって、研究時間が削がれる環境にあるというのが現状です。研究、ティーチング、学生サポートなど、多岐にわたる役割をこなすことが求められます。学生サポートにおいては人間力も問われます。
けれども、自身のスキルアップを考えた時、評価されるのはティーチングではなくてリサーチです。ですから、どんな過酷な労働環境でも論文を書き続けなければなりません。大学人であると同時に研究者であり続けることは私自身、難しいと感じています。短期・中期・長期の研究計画を立て続け、本物の研究者としての道を諦めないことが必要だと思っています。
伊藤 以前、学内の業務をやればやるほど大学内で評価されるという環境にいた時、もうこれでいいかなと思いかけたこともありました。でもそれに満足せず研究を続けて今があるのは、面白い研究ができたときの達成感や価値や意義が自分の中に残っていたからだと思います。教育に追われる時間が増えますが、研究の方面で良い仕事をしたいという気持ちを常に持ち続けることが大切です。
山﨑 一流の研究者とは何かと考えた時、研究対象によって手応えは違うと思いますが、私のように言葉の意味を突き詰める研究をしている場合、辞書で説明されている意味とは違う意味を見つけることに喜びを感じます。そうした積み重ねが現在につながっています。
荒木 個人的には、一流の研究者になることを目的にしたら、そうなれないと思っています。身近な優れた研究者を見ていると、自分でやりたいことを見つけて自律的に動ける人が一流の研究者なのかもしれないと感じます。
戸田 私が研究者をやめてもいいと思えるほどの論文を書けたのは39歳の時です。それまでに依頼原稿や学会発表に取り組み、研究者として一歩一歩、前へと進んできました。こんなレベルの内容の論文を公表していいのかな、なんて思いながらも論文執筆の経験を積み重ね、気がついたらゴールにたどり着いていたという感じで良いと思います。
終わりに
今回は、明治大学の現役教員の具体的な経験を踏まえた話をたくさん聞くことができました。Meiji.netでは、さまざまなテーマに沿って個性豊かな明治大学の教員が自身の経験をリレー形式で語るリレーコラムを公開しています。
▷Meiji.netリレーコラム
明治大学大学院では、今回のイベントを含め、アカデミア志望の大学院生を支援する多彩なキャリアサポートプログラムを展開しています。今後もアカデミアの道を志す学生たちに向けて、大学院独自の支援を実施して参ります。
▷大学院キャリアサポートプログラム
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。








