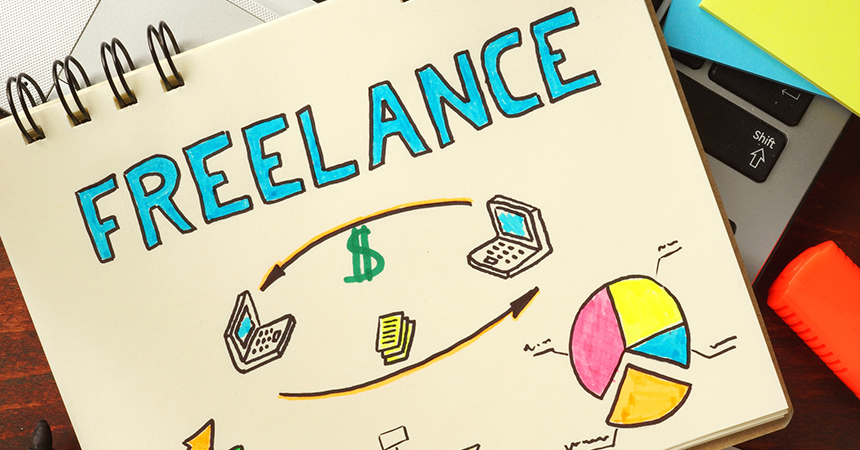社会保険料の負担などを軽減し、経営のスリム化を図るためにも、企業はこれまで労働者にさせてきた仕事を新たに自営業者などへ発注する傾向がみられます。では、そのような仕事をするなかで自営業者が怪我をしたらどうなるでしょうか。労災保険法は、「労働者災害補償保険法」という名称通り、基本的に労働者を補償の対象とします。働き方が多様化するなか、自営業者に任意加入の途を開く労災保険の「特別加入」枠が広がってきていますが、現代の「新しい自営業者」の労災問題を解決することは果たしてできるのでしょうか。
フリーランスの増加とともに近年、一気に拡大した労災保険の特別加入制度
 労働者災害補償保険法(労災保険法)は、独自の労災補償制度をもつ公務員・船員および農林水産業で労働者5人未満の個人経営事業などを除いて、労働者を使用するすべての事業に強制的に適用される法律です。
労働者災害補償保険法(労災保険法)は、独自の労災補償制度をもつ公務員・船員および農林水産業で労働者5人未満の個人経営事業などを除いて、労働者を使用するすべての事業に強制的に適用される法律です。
労災保険は政府が管掌し、事業の開始した日に保険関係が成立して事業主は保険料を納付する義務を負うことになります。保険事故が発生すると、被災労働者および遺族に給付請求権が発生します。労働基準監督署で認定を受けられれば、原則、無償で療養補償給付などを労災保険から受けられるようになるのです。反面、労働者、すなわち企業から指揮命令を受けて(言い換えれば企業との間で使用従属的な関係下で)働いている者(とその遺族)でなければ、基本的に労災保険からの給付を受けることはできません。
日本では、これまで、自営業者のための社会保障も充実化されてきています。たとえば国民年金や国民健康保険(国保)は、もともと自営業者のためにつくられました。労災保険の適用がない自営業者が仕事中に怪我をした場合、基本的には国保からの給付を受けることになります。
自営業者は、自身で国民健康保険に加入します。国保では、被用者保険に加入する者は適用除外としつつ、「住所」を有する者を強制加入としているため、被用者保険に入っていない自営業者は国保に入ることになります。
他方で、労災保険法は労働者に準じた働き方をしている自営業者に対して、「特別加入」といって、本人が保険料を自己負担し、任意加入する途を用意しています。特別加入制度は1965年に創設されました。保険料は各自がそのリスクに見合うと思われる額を選びます。対象となるのは、中小事業主・家族従事者等、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者です。このうち海外派遣者以外は団体加入が原則であり、労働保険事務組合などを経由しての加入となります。
「中小事業主」は全業種加入可能ですが、「一人親方」として認められてきたのは、長らく7事業(個人タクシー・個人貨物運送業者、建設業の一人親方、漁船による自営漁業者、林業の一人親方、医薬品の配置販売業者、再生資源取扱業者、船員)でした。
また、「特定作業従事者」も、とくに危険有害な事業に従事する自営業者や、業務実態から労働者に準じて保護を与えることが妥当である7種が対象(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者、家内労働者、労働組合の常勤役員、介護作業従事者)でした。
しかし社会の変化や関係者の声を受け、特別加入制度の対象として2021年4月以降、柔道整復師が行う事業、高年齢者雇用安定法の創業支援等措置に基づく事業、あん摩マッサージ指圧師、はり師または灸師が行う事業、歯科技工士が行う事業が、そして芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、ITフリーランスが加わりました。(なお、2021年9月以降、「個人タクシー・個人貨物運送業者」に、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も加わりました)
さらに2024年11月に施行となった「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス法」に合わせ、企業等から業務委託を受けているフリーランスは誰もが特別加入できるようになりました。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。