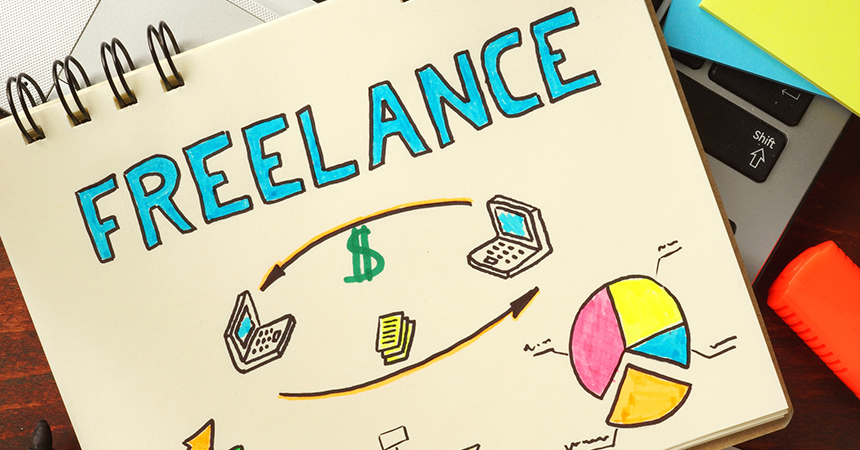企業の責任と考えられてきた被用者に対する保険料の負担を回避する傾向に
今日では、ひと口に自営業者といっても、かつて典型例として考えられていたような農林水産業の従事者(仮に「古い自営業者」と呼びます)ばかりではなくなってきていると思います。本来は労働者として企業が雇うべき人を、経費削減等のために「非労働者化」するようになったとしたら、それに呼応するように増えてきた「新しい自営業者」の保護のしかたについても新たに考えなくてはならないのではないでしょうか。
特別加入という方法で自営業者に労災保険の適用が広がること自体は望ましいことかもしれません。しかしこのしくみではあくまで、保険料を負担するのは自営業者本人です。フリーランス協会の平田麻莉氏は、2021年2月に国会で参考人として、特別加入制度は保険料が自己負担であり、会社員であれば企業が負担する部分もすべて自分でまかなわなくてはならず負担が増えることを問題点として指摘していました。
特別加入制度では、自身で保険料を選び、作業内容を申告する契約保険のようになっています。このことが意味するのは、特別加入の場合、本人が申告した通りに働いていない部分については給付が出ないということでもあります。不正を防ぐためという側面もありますが、給付の条件はシビアになります。
ところで、日本が社会保険制度をつくるのに際して参考としたドイツの労災保険において、強制的保険対象者は(労働者より広義の)就業者とされ、それと同程度の要保護性がある者にも拡張されています。この結果、職業訓練生や一定のボランティアも強制的保険対象者とされているのは日本とは異なる点です。考えてみますと、日本の労災保険は「労働者」と「自営業者」に分け、自営業者のうち労働者に準じた者には任意(特別)加入させるとして、本人の保険料負担で保護しようとしているようにもみえますが、それでよいのでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。