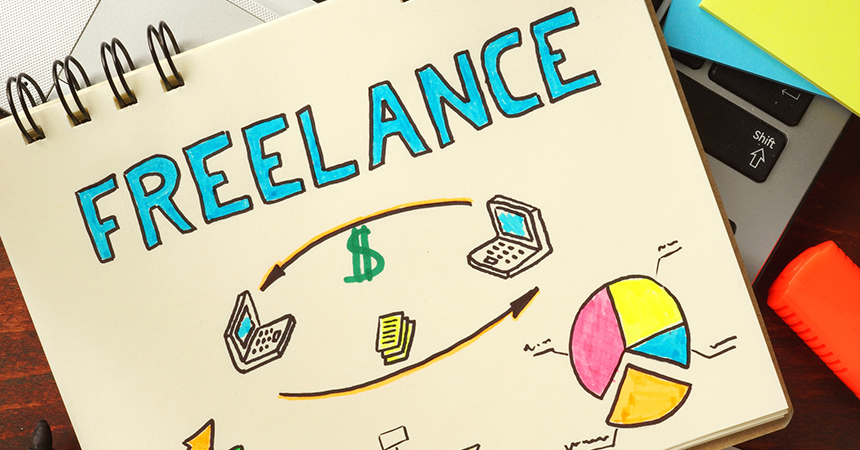「任意」で「自己負担」の特別加入制度が適切かは、なお一考の余地がある
先ほど「新しい自営業者」に触れましたが、これには、たとえばメディア、文化ないしクリエイティブな営み、さらには運送セクターや建設に従事する人々などが想定されます。場合によっては自営業者、場合によっては被用者というように、自営業者と被用者を行き来することもあり得ます。
もちろん、引く手あまたな自営業者なら企業といわば対等に渡り合える立場にもあるでしょうけれども、「新しい自営業者」の多くが、今まで雇われてきた人の代替を安いコストでさせられているのが現実ではないでしょうか。
もともと労働者というのは、本人が休みたいと思っても簡単に休めない、従属的な働き方をしている人たちです。だからこそ働いていていざ事故が起きた場合には、雇い主側の責任で補償しようとしたのが労働基準法であり、補償を確実にするために、資本家(事業主)が保険料を出しあい財源を用意するというのが―ざっくりと言えば―労災保険法の考え方です。
特別加入制度は、労働者ではない自営業者にも任意とはいえ加入を認めるという意味で、労災保険を社会保障化させる象徴(シンボル)として、これまで肯定的に捉えられてきました。たしかに、「古い自営業者」のように、自らリスクをコントロールできる人たちであれば、危険な農機具を使用しての怪我に備えて必要な保険に入る、というのもわかります。しかし、「新しい自営業者」、たとえば個人で請け負う宅配業であれば、むしろリスクを顧みず、危険な雨天の方が儲かるからといって無茶を承知で休まず働く人もいることでしょう。実際にネット通販で働く配達員(個人事業主)が配達中に怪我をした際に、労働基準監督署から労災認定を受けたという例もあります。
特別加入制度を拡張すれば拡張するほど、リスクに対して任意加入で自己負担せざるを得ない事態に甘んじる人を増やすことにならないでしょうか。このような拡張を「社会保障化の進展」と言って手放しに喜んでいてよいものでしょうか。
厚生労働省は、労働安全衛生法を改正し、フリーランス等個人事業主の労働災害を防ぐため、仕事を発注する企業に事故の報告を義務づけるとのことです。しかし「新しい自営業者」の働き方を念頭においた場合、それで十分でしょうか。先ほど特別加入は団体加入が原則であると述べましたが、近い将来、この制度の普及のためといって、個人加入が解禁されるという選択肢もありうるかもしれません。最近、厚生労働省が「労働者性」の判断基準を見直すための研究を開始したという報道にも接しましたが、従属の度合いに応じて、「労働者に準じた」どころか「労働者と変わらない」リスクのある働き方については、労災保険本体の適用下におくべきであり、安易に特別加入制度に頼らない解決策を模索すべき時期に差し掛かっているのではないかと考えています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。