新しい技術やツールに人が奉仕するような状況が進行している
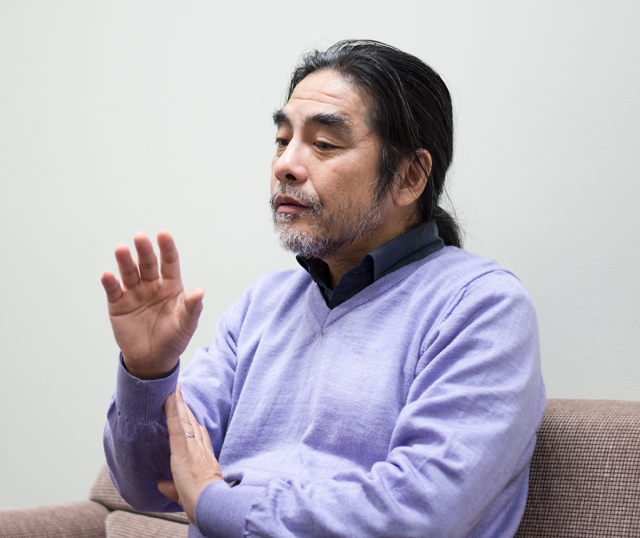 つまり、私たちは技術的環境の真新しさに目を奪われるべきではなく、どのような情報の需要構造がどのような機能と役割を求めているのか、そこにどのような技術やツールが用いられているのかを認識することが重要なのです。例えば、いま、多くの人がインスタグラムを楽しんでいますが、ここに至る大きな転換点は、2001年に起きたアメリカの同時多発テロ当時にはっきりとあらわれていたと考えられます。マンハッタンの高層ビルにハイジャックされた航空機が突入することなど、誰も想像もしていなかったことなのに、いまでも1機目の突入の映像が大量に残っています。あのとき、私たちは、自分たちが常に記録し、発信できる状況にあることを認識し、その技術やツールが私たち自身の映像情報の需要に応えるものだとわかったのです。それが、インスタグラムのような使い方を受け入れるタイミングになったといえます。しかし、一方でこうした技術やツールは監視社会の構築にもつながっています。私たちに、犯罪の抑止であれ、生活の利便性であれ、監視情報の需要構造があるからです。しかし、そのための新しい技術にばかり目を奪われていると、人が技術に奉仕するような抑圧的な状況が、知らぬ間に進行しかねないのではないでしょうか。
つまり、私たちは技術的環境の真新しさに目を奪われるべきではなく、どのような情報の需要構造がどのような機能と役割を求めているのか、そこにどのような技術やツールが用いられているのかを認識することが重要なのです。例えば、いま、多くの人がインスタグラムを楽しんでいますが、ここに至る大きな転換点は、2001年に起きたアメリカの同時多発テロ当時にはっきりとあらわれていたと考えられます。マンハッタンの高層ビルにハイジャックされた航空機が突入することなど、誰も想像もしていなかったことなのに、いまでも1機目の突入の映像が大量に残っています。あのとき、私たちは、自分たちが常に記録し、発信できる状況にあることを認識し、その技術やツールが私たち自身の映像情報の需要に応えるものだとわかったのです。それが、インスタグラムのような使い方を受け入れるタイミングになったといえます。しかし、一方でこうした技術やツールは監視社会の構築にもつながっています。私たちに、犯罪の抑止であれ、生活の利便性であれ、監視情報の需要構造があるからです。しかし、そのための新しい技術にばかり目を奪われていると、人が技術に奉仕するような抑圧的な状況が、知らぬ間に進行しかねないのではないでしょうか。
最後に、私のマイブームをひとつ。昨年の秋、テレビドラマの原作者が、そのドラマの放送を見ながら感想を随時ツイートしたところ、多くの視聴者とツイートを共有することになったことが話題になりました。実は、私もテレビドラマを見ながら、ネタをツイートし合うという楽しみ方をしています。新しい技術の普及にともなって、それ以前のメディアは廃れていくと思われがちですが、定時放送というテレビドラマを、ツイッターとメディアミックスすることで、同期性を楽しむメディアとして再評価する人が増えてきているのです。エンターテインメントを多くの人と共有したいという自分たちの需要をしっかり見つめれば、そこに必要なメディアは真新しいものばかりではないことが、見えてくるはずです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




